おもしろいシーンがいくつもある。いちばん印象に残るのは、コリン・ファースが吃音を直すために、ジェフリー・ラッシュの家に行き、そこで会話するシーンである。二人が対話するシーンというのは、顔がスクリーンの中央にこない、視線がまっすぐにカメラをみない(少しずらしたところから映す)というのが基本だと思うが、この映画では、その基本をさらに拡大している。コリン・ファースが語るとき、スクリーンの右半分は完全に空いている。壁が大半を占めている。そのスクリーンの構造が、そのまま治療を受けるときのコリン・ファースのこころそのものなのである。片隅にとじこもっている。感情がおしつぶされている。窮屈なところに自分を閉じ込めている。
それは彼が怒りを爆発させるシーンと比較するとはっきりする。そのときスクリーンには空白がない。アップというわけではないが、スクリーンからコリン・ファースが飛び出してくる感じである。怒るとき、コリン・ファース、ジェフリー・ラッシュの距離が、ぐいと縮む。怒りをとおして(感情の爆発をとおして)、二人の距離が縮むとき、コリン・ファースの吃音が直っている、というところが非常におもしろい。
その「距離の変化」に注目すると、映画は、英国王が吃音を克服するということがテーマになっているのだが、そういう見かけのテーマとは別に、この映画は人間と人間の「距離」のありかたをこそテーマにしていることがわかる。
コリン・ファースの演じる英国王は、相手との「距離」がうまくとれないときに吃音になる。距離がないときは、吃音ははげしくはならない。王の緊張は、自分の感情を自分自身の奥に閉じ込め、自分と他者とのあいだに不必要な「距離」をかかえこむときに生まれる。そして、それが吃音となる。
そして、この吃音が、さらに距離を増幅させる。
この距離が、単に個人的な「場」において存在するだけなら、問題ではない。王が「家庭内」で吃音である分には、問題はない。家庭内でどんな「距離」をかかえこんでいても、それは家庭の事情というものだろう。しかし、この距離が国民と王という場に入り込むと、非常に困るときがある。ふつうは、困らない。王と国民は、一緒に生活などしないからである。
けれど。
この映画で描かれている「戦時」の場合は、困る。戦争するとき、国民は団結しなければならない。国民と国民のあいだに距離があってはならない。同じように、王と国民とのあいだにも距離があってはならない。人間として団結しなければ、ナチスとは戦えないだろう。
この映画が感動的なのは、単に吃音の王が吃音を克服し、国民に「戦争スピーチ」をしたというところにあるのではない。王が自分の抱えている距離の問題を克服し、その克服した結果生まれたあたらしい距離のなかへ国民を引き込み、団結するからである。
この映画は、そういう距離の変化をきちんと映像として表現している。
クライマックスのコリン・ファースのスピーチ。そのとき、コリン・ファースはマイク越しにジェフリー・ラッシュと真っ正面で向き合っている。このとき、冒頭に書いたような余分な「空白」はない。変な空白を排除することで、コリン・ファースがジェフリー・ラッシュと正面で向き合うだけではなく、その距離を縮めていることがわかる。それを補うように、ジェフリー・ラッシュの台詞がある。「わたしに向かって語りかけなさい」。スピーチは国民に向けたものである。けれど、国民というラジオ越しの遠い(距離のある)相手にではなく、いちばん近い相手にだけ向かって語れという。「声」から距離が消えるとき、それは王と国民との距離をも消してしまうのである。
この距離を印象づけるためだと思うのだが、映画には随所におもしろい距離が出てくる。コリン・ファースがジェフリー・ラッシュと喧嘩別れ(?)をするシーン。コリン・ファースはどんどん道を歩いていく。ジェフリー・ラッシュは立ち止まったまま。距離がどんどん開いていくのだ。この広げた距離を、コリン・ファースは直接出向いて謝罪するということで縮めてみせるというのも、非常におもしろい。王が庶民に謝罪しにやってくるというのは、それだけで特別なことだが、その距離をつくりだしたのがコリン・ファースであることを、コリン・ファースの「歩き」としてきちんと映像化していたからこそ、それが効果的になるのだ。
ジェフリー・ラッシュの家での、彼と妻の会話のシーンもおもしろい。妻はスクリーンの左側、ジェフリー・ラッシュは右側。ただし、このとき二人は会話をするにもかかわらず、互いに背を向けている。背を向けたまま、体をひねるようにして、話す。その距離と、角度。離れているけれど、接近する--どこかで接しようとするこころの動き。コリン・ファースの治療中の映像の構造とは対照的である。
ストーリーが、映像、その構図そのものとしてスクリーンに定着している。コリン・ファースの演技そのものも非常にすばらしいけれど、映像の構図、そのカメラそのものも演技している(役者の演技を演出している)。構図だけではなく、映像自体もとても美しい。落ち着いている。映画を見た--という気持ちが、ずん、とこころの奥にたまる映画である。
*
補記。
「間」の問題を、空間ではなく「ことば」に置き換えると、「吃音」が見えてくる。そういう意味では、この映画は「吃音」を映像化(空間化)した作品とも言える。
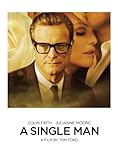 | シングルマン コレクターズ・エディション [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| Happinet(SB)(D) |