探すのはマラルメ的な
オブジエではないだろう
もつとつまらないオブジエだろう
淋しさを探すだろう
町で聞く人間の会話
雑草の影が映る石
魚のおもみ
トウモロコシの形や色彩や
柱のふとさ
なにも象徴しないものがいい
つまらない存在に
無限の淋しさが
反映している
ここには西脇の夢が結晶している。シンボルにならいなもの、意味にならないもの。そこに淋しさかある。淋しさとは「意味以前」なのである。
--と、私のことばは、どうしても動いてしまう。「意味以前」という「意味」に触れてしまう。これは、こうの行を書きつづけた西脇にも起きる。
さきの行につづけて、西脇はすぐに書いている。
淋しさは永遠の
最後のシムボルだ
このシムボルも捨てたい
永遠を考えないことは
永遠を考えることだ
考えないことは永遠の
シムボルだ
しかし、どうしても「矛盾」になってしまう。堂々巡りになってしまう。これは詩の宿命なのだ。
詩はことば以前を書く。意味以前を書く。しかし、書いた瞬間、それはことばになる。そして意味になる。だから、それを否定する。そして、その否定すらが、ことばになり、意味になる。
問題は、それを自覚して書くか無自覚で書くかということになる。西脇はつねに自覚している。
という、うるさいことは、もうやめにして、少し前に戻る。きょう引用した最初の部分、そのうちの、
雑草の影が映る石
魚のおもみ
この2行が、私は非常に好きだ。
「雑草の影が映る石」は夏の明るい陽射しがまぶしい。太陽そのもののまぶしさではなく、空気のなかに広がって散らばった光の美しさがある。石はきっと白い。そして影はきっと黒いのだが、その黒は、藍色に見えたり水色に見えたり灰色に見えたりするのだ。
「魚のおもみ」。この1行は、私を不安にする。この魚の重みは、私にとっては手では測れない重みである。私は水のなかを泳いでいる魚を見てしまうのである。「雑草の影が映る石」から夏を想像してしまうのでそうなるのだが、夏の川で泳いでいる魚を私は思うのである。それは手で触れることはできない。つかまえようとしても逃げてしまう。逃げることができることをしてってい悠然と冷たい水の、その冷たさをここちよげに味わっている魚。その重さ。西脇は「重さ」ではなく「おもみ(重み)」と書いている。「おもさ」と「おもみ」のことばの違いも、私の想像力に影響しているのだと思う。
触れえないものがある。確かめようがないものがある。これが「淋しさ」である。触れえない、確かめようもないとき、感じてしまうのが「淋しさ」である。
しかし、その触れることができないもの、確かめることができないものにさえ、人間のこころは動いてしまう。動いて何かを感じてしまう。(だから、「淋しい」。)
そして、その何かを感じさせるもの、感じさせる力が「シムボル」だとすれば、感じてしまう力、感じる動きこそが「永遠」かもしれない。「シムボル」と「永遠」はそんな具合にして出会うのだ。
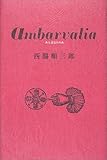 | Ambarvalia (愛蔵版詩集シリーズ) |
| 西脇 順三郎 | |
| 日本図書センター |