ラストシーンがとてもおもしろい。フェイスブックの創業者が、昔の恋人がフェイスブックに登録していることを知る。そこでメッセージを送り、コンタクトを取ろうとする。そのとき、メールを送り(?)しばらく待つ(半日とか1日とか)のではなく、ひっきりなしに「更新」コマンドを押して相手の反応を確認している。まるで電話の呼び出し音を聞きながら、相手がいつ出るかいつ出るかと待っている感じなのである。
ネット社会は、ここまで来てしまったのか。
手紙・はがきの時代は何かメッセージを送っても反応が帰ってくるまでに早くて2-3日はかかった。1週間くらい反応がないときもある。それが電話になって、瞬時に連絡がとれるようになった。しかし、この電話も固定電話の時代は電話のそばに人がいないかぎり連絡はとれない。携帯電話になって、いつでも、どこでも、相手の都合など関係なく連絡が可能になった。それでも、まあ、電話に出ないということもある。
ネットはパソコンの前に座って、パソコンが起動した状態でないとメッセージのやりとりはできない。電話で言えば、いわば固定電話のようなものである。それなのに、主人公の男は、相手がパソコンの前にいる、そしてメッセージを読んでいると想定している。
フエイスブックでは、相手がオンラインであることがわかるのかな? たとえ、相手がオンラインにいるとわかっても、この主人公の態度は、かなり「わがまま」である。
女は男の態度が気に入らないと去って行ったのである。男がコンタクトをとろうとしたときも、迷惑だ、とはっきり言っている。その、女の「拒絶」が男にはわかっていない。--と、ここまで書いてきて、この映画が少しわかりかけてきた。(書きたいことが、変わってしまった。)
あ、そうなのか、この映画は、人と人の接触を描くと同時に、拒絶も描いているのか。むしろ人と人との関係の遮断こそが隠れたテーマかもしれない。
どこまでもどこまでも増殖していくネットのつながり。そこではつながりができたとたんに、そこで起きていることがどこからはじまったかわからなくなる。フェイスブックのアイデアを考えたのはだれなのか。その出発点をつきつめることは難しいし、第三者にはアイデアを思いついた人間よりも、そのアイデアを実現した人の方がはっきりわかる。アイデアはそれを実現した人のものとして見えてしまう。アイデアと、それを実行するプログラムを切断し、ふたつに分けることは不可能なのだ。ネットワークのシステムにおいては、実行プログラムのなかにアイデアは吸収されてしまう。その吸収されることを拒絶することはできない。そして、その拒絶できず、吸収されてしまったことに対する解決として「和解金」が支払われる。
他方、映画では、それとは別の「拒絶」を描いている。システムは、人間ではないので、どんどん吸収されてしまうが、人間はそうではない。アイデアを出した人間はシステムから拒絶され、最初に資金を提供した友人も、会社の組織からは拒絶され、はみ出してしまう。会社の中では、人間関係ではなく、金(マネー)のシステムが支配している。
情報処理システム、マネー流通システムのなかで、人間は、どんな関係を作り上げることができるのか。なんだか、よくわからない。フェイスブックの創業者は、最後まで、人間関係を作り上げることができずにいる。彼ののぞむ人間関係をつくれずにいる。彼がつくれたのはフエイスブックという情報処理のシステムとマネーを稼ぐシステムだけである。主人公は、現実の人間関係のなかでは「拒絶」と向き合っているだけである。
(フェイスブックのアイデアを出したひと、最初に資金を提供した友人との人間関係も、主人公は築くことはできなかった。)
--しかし、もし、この映画が、そういう「拒絶」を描いているのだとしたら、つまらないねえ。いやだねえ。
フェイスブックはグーグルを超えて暴走している。その暴走がどこまで行くか、その可能性の方を私は知りたい。若い知能が考え出したアイデアがどこまで暴走し、社会そのものをつくりかえてしまうのか、それをこそ描いてほしいと思うけれど、そこまで、想像力が働かないのかもしれない。この先を想像できるのは、主人公だけということかもしれない。
そうだとしても、そこからはじまる幸福と不幸を、もっとスピード感をもって描いてほしかった。主人公が、ひとりさびしくパソコンのキーボードを叩いて女からの返事を待っているのというのは、なんとも、げんなりする結末ではないだろうか。
ちょっと映画とは関係のない感想になってしまたかなあ。
映画そのものとしては、主人公を演じたジェシー・アイゼンバーグの早口にまいった。膨大な台詞をものすごいスピードでしゃべる。途中で悩むということがない。加速するコンピューターの世界そのものである。ジェシー・アイゼンバーグが増殖するネットをそのまま具現しているということかもしれない。
一方に、情報処理が加速化し、他方で人間関係が途絶する。ネット社会で「人間関係」が成り立たないと、それが現実に反映されない。ネットのなかで関係を作り上げるシステムはどんどん巨大化するが、それを現実の人間社会に反映できない--ネット社会が現実より大きくなり、現実がそれを受け止められなくなっている。現実とバーチャルが逆転しはじめているのだ。
そういう世界が、いいとか、悪いとかいう時代は、もう過ぎ去ったのかもしれない。私のこの感想もそうだが、この映画も、なんだか「人間」に寄り添いすぎているかもしれない。「倫理的(?)」であるすぎるかもしれない。
ネットの暴走のなかで人間は孤独を深めている--というのは、映画としてはおもしろくなさすぎる。センチメンタル過ぎる。
バーチャルが現実をととのえる--ということを、もっと前面に押し出して、別の展開になればおもしろいのになあ、というのは、まあ「ないものねだり」なんだろうなあ。
デヴィッド・フィンチャーは、いつでもセンチメンタルだからねえ。人間の「情」を生きているからなあ。どんなに「非情」を描いても。
私の感想も中途半端だが、映画も中途半端だね。--これが、私の「結論」。
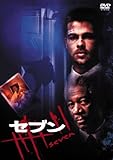 | セブン [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ギャガ・コミュニケーションズ |