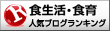全世界に占める、
日本の国土面積はたった
「0.25%」
そんな極東の小さな島国周辺でマグニチュード6以上の地震が起こる割合は、
"17.9%"
世界における大きな地震の約2割が日本、及び日本の周辺で起きている(2011年~2020年のデータ)。
日本は世界で最もキケンな地震大国といえるのです。
そんな日本において、原子力発電所を稼働させること。このこと自体にムリがある。
日本人と原発とは同居できない。このことが今回の能登半島地震で明らかになりました。
いや、福島の段階で、すでに明らかになっていたとは思うのですが、でも今回の地震で
「トドメ!」
を刺されたといえるのではなかろう?
地震そのものによる石川県・志賀原発へのダメージ。これも甚大なのですが、それにも増して深刻なのは、
"情報の出し方"
問題なしと言ったかと思えば、訂正。被害軽微と発表したかと思えば、大きな被害・・・。
朝令暮改、大本営発表だなんていったりもしますが、そんなことを地震直後から繰り返しているのです。
「水位計に優位な変動は見られない」、そういったかと思えば、約1~3メートルの津波が複数回、発電所に到達していたと発表を訂正。
2号機の変圧器からの油漏れについても当初は約3500リットルと発表していましたが、実際は1万9800リットル。約5倍の量に訂正されるに至りました。
油は敷地内に留まっていると発表したものの、実際は海に漏れ出ていたことが後に判明。
火災が起きたと発表したものの、その後に火災はなかったとこれまた訂正。
志賀原発は活断層の上にあるのではないか?こうした長らくの疑念を打ち消し、"上にはない!"と断定するに至りました。
こうして再稼働に向けての準備を進めていたところでの今回の地震。
活断層の上にある危険性が拭えない、疑念はより一層深まっている。これまた前言撤回といえるのでしょう。
地震直後から、さまざまな情報が錯綜しているのがいま現在の状況です。
※参考:『石川・志賀原発「情報誤発表&訂正」のお粗末…北陸電力そして政府に渦巻く不信と不安』
志賀原発は2011年5月から停止中となっていますが、もしこれが稼働中であったのなら、どんな事態になっていたのか?
背筋が凍るような思いになります。
被害を極力小さく見せることで、どうにか隣県の新潟・柏崎刈羽原発を再稼働に漕ぎつけたい。
これが情報の発表⇒訂正を繰り返す理由であると、元経済産業省官僚の古賀茂明氏は解説しているのです。
※参考:『能登半島地震で露呈した原発の「不都合な真実」 政府が志賀原発を“異常なし”と強弁した理由』
株価が低迷し、苦しい経営状態が続く東京電力をV字回復させていく。そのための切り札となるのが、世界最大級といわれる総出力を誇る、柏崎刈羽原発の早期再稼働。
これを成し遂げることを目的に、迷走に次ぐ迷走を繰り返しているのが現在の状況なのだと古賀氏は説明するのです。
今回の地震で、再稼働はますます難しくなったと思いますが、この問題は時を置いてまたゾンビのように復活してくるのが毎度のパターン。
私たちは冷静に事態の推移を見守る必要を思うのです。

■災害と樹木
日本は世界有数の地震大国なのですが、私たちの祖先が最も苦しんだ災害はといえば、
「火事」
になるのでしょう。
"火事と喧嘩は江戸の花"、そんな言葉がありますが、当時から世界最大の人口密集地である江戸においては、一たび火事が起こると被害は甚大なものとなりました。
特に1657年に起こった振袖火事こと、「明暦の大火」においては、当時の江戸の人口80万人のうちの約10万6千人が焼死するに至りました。
1921年の関東大震災の際の焼死者も約10万人といわれていますが、その当時の東京の人口は約400万人。
明暦の大火の被害がいかに甚大であったかが分かると思うのです。
江戸時代264年の間に、100回以上の大火があったといわれますが、正直、その消火能力は現代に比べて著しく低いといわねばなりません。
でもその反面、防火活動においては様々な素晴らしい知恵と実践の痕跡がみられることも一方の事実。
火事を出さないようにと、将軍、大名、役人、庶民に至るまで一致団結。平素からの様々な工夫を施していたことが分かるのです。
江戸には様々な神社仏閣がありますが、その門前はといえば道路の幅を広く取り、イチョウや青桐といった樹木が植えられているのが情景です。
なぜイチョウの木が神社の境内に多いのかといえば、火にすこぶる強い性質があるため。
火事の際のイチョウの木は溜め込んだ水を吹くといった性質があるからです。
実際に火の手が樹木に阻まれて鎮火した。こうした事例も多々あったそうなのです。
今でも、街路樹にイチョウが多い理由は火除けのため。それは青桐も同じであるというわけです。
■困ったときには?
また当時の大名は概ね、上・中・下の三つの屋敷を江戸に持っていましたが、それぞれが分散して各地に点在している。
敷地が広いため家屋部分は少なく、大きな庭園になっているのが大名屋敷の構えになります。
たとえ火事が起こっても広大な屋敷で阻むことができるわけだし、人口密集地から逃げ出してくる庶民たちの一時避難場所にもなっていく。
現代でいえば、ちょうど住宅地と公園のような関係といえるのでしょう。
神社仏閣に加えて、大名屋敷も江戸っ子の大切な火除け地としての役割を果たしていたと説明されるのです。
火事の際は助けてくれるわけだから、江戸の庶民は日頃から、各大名や宗教施設を大切にし崇めていた。
お互い様の相互関係が庶民と大名との間にはあったというわけです。
また各庶民の住宅も蔵造りといって、柱や垂木がムキ出しにならないように漆喰で固めていました。
明暦の大火の教訓から、屋根には不燃性の瓦が推奨され、お金のない庶民には幕府が補助金を出して援助していたとのこと。
商家と商家との間には、「うだち」といわれる一種の泥土による防火壁を作って、燃え広がりを防ぐための工夫を施す。
そしてイザ!という時のために、幕府は江戸城内に"救い米蔵"という米蔵を建て、火事の際などには庶民にお粥を振る舞っていたことが伝えられているのです。
百万人の餓死者を出した「天明の大飢饉」(1783~1786年)においては、日本各地で一揆が頻発しました。
でも江戸ではそれが起こらなかった理由は、救米制度によるものと言われているのです。
まだまだ様々な工夫があるのですが、火事に弱いという江戸の町の特性に対して各種の防火対策が施されていたことが説明されるのです。

■浅ましき人々
10万人以上が亡くなった明暦の大火において、その火の手は江戸城にまで及んでいきました。
そして天守閣は焼け落ちてしまったのが経緯になります。
直後の評議において、これでは幕府の威信が保てないとして、天守閣を再建しよう。そう主張する幕閣たちも少なくなかったそうなのです。
でも時の老中・保科正之は、
「住むところを失った武士町人が家屋の再建を急いでいる時に、天守閣の再建などをはじめると邪魔になる」
そこに費用を使うくらいなら江戸の人々に
「粥を施せ!」
そう述べて、食料に困る人々を救済したことが伝えられているのです。
江戸城こと、現在の皇居に天守閣がないのは、こうした理由からなのだそうです。
大阪万博にかかる人手や資材、そして10兆円もの予算を被災地の復興に回せ!
SNSを中心にこうした声が高まっているのですが、大阪府にも日本政府にも。今のところ、どうやらその気はなさそうです。
万博の後には2029年開業予定のIRこと、カジノ・リゾート構想が控えている。計画を後ろにズラしたくないことも、大きな理由のひとつなのかもしれません。
老中・保科正之が現代を見たら、どんなことを思うのか?おカネゾンビたちが跋扈する惨状に、浅ましきこと限りなし。
そんなことを思わずにはいられないのですが、いかがでしょう?
■参考文献