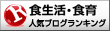心と体は
"密接不可分"
心の状態は、体の変調となって現れます。
恥ずかしい!と思えば、スグに赤面していきます。 顔全体への血流の流れが上がることが理由です。
心配や不安に心が覆われ続ければ、頭皮への血流の流れが弱っていく。
毛根への血液供給に支障が生じて、「円形脱毛症」などの心因性の症状を起こしやすくなってしまうのです。
また、怒りやイラ立ち、心配などのマイナス感情に心が捉われてしまうと、加齢臭の原因になることも指摘されています。
ニオイの元はノネナールという物質の分泌によるものですが、これは体内で活性酸素が過剰になることで生まれやすくなります。
活性酸素の過剰は同時に過酸化脂質の過剰分泌も招いてしまう。それが油臭くて、青臭いような加齢臭の原因になっていく。
活性酸素は怒りやイラ立ち、不満などのストレスによっても増えていくもの。加齢臭の強弱は、ストレスの強弱と比例関係にあることが分かっているのです。
不安や心配は胃腸にも不具合をもたらし、呼吸器系にも悪影響を及ぼしていく。
それが、ガンやアレルギー、糖尿病などの深刻な病気の原因になってしまうのです。
また最近では、怒りや不安などのマイナス感情に捉われたままだと、唾液の成分にも影響を与え、虫歯を増やしてしまうこともいわれているのです。
病は気からだなんて言ったりもするのですが、かつては非科学的!な考え方の代表として、一顧だにされていませんでした。
でも今ではそれが科学の力によって、密接不可分な関係にあることが証明されつつあることも事実。
体の健康を願うなら、心の健康も欠かせない!こうした事実が次々に明らかになっているのです。

■最大化の条件とは!?
でも、これらのことは、今から2400年前にすでに指摘されていた事がらでもあります。
医学の父といわれるヒポクラテスが提唱した
「病者への愛」
といわれるものがそれに当たります。
ヒポクラテスが登場するまでの病気の症状は、すべからく神の呪い・・・。
そう広く一般に信じられていたようなのですが、ヒポクラテスはそれに対して大いなる疑問を覚えたと伝えられているのです。
症状は神の祟りといわれているが、
「果たして本当だろうか・・・?」
ヒポクラテスは病人の症状をじっくり観察し、病気が治っていく過程に注目し続けたのです。
発熱や炎症、それに伴う痛みや苦しみは、治癒に向けて避けては通れない大切なプロセス。
だからいたずらに悲観すべきものではない。症状とは治るための過程なのだから、むしろ積極的に捉えるべきだ。
このように主張したのです。
病者に備わる治癒力が高まっていけばいくほど、病気は早く克服できるもの。
問題はどうすればその治癒力を高め、その力を最大化させることができるだろうか?
ヒポクラテスの観察と思索はそこに及んでいきました。
そして試行錯誤の結果、導き出した結論は病者に
"慰めと励まし"
とを与えること。それこそが治癒の最大化をもたらす大切な治療行為に当たるもの。
ヒポクラテスはこのことに気づいたことが伝えられるのです。
■医者の仕事とは!?
神の呪いだなんて、絶望的な言葉を苦しむ病者に向って決して、浴びせかけてはならない。
それは病者の心を折り、砕いてしまといった結果を招きかねない。心が絶望で覆われてしまえば
治るものも治らなくなってしまう
生きるための体内資源をフル稼働させるために、必要なことは、未来に希望を与えること。それこそが
"医師の仕事である"
ヒポクラテスはこのように主張しました。
治すのはあくまで患者自身。医師とは患者が自然に治そうとする力に、ただサポートを与えるだけの存在に他ならない。
症状を恐れさせたり、浮き足立たせたりすることなく、痛みや辛さは治癒に欠かせないプロセスであることを病者にハッキリ理解させる。
これが有名な「病者への愛」といわれる提言です。さらにヒポクラテスは、
「患者に発熱する機会を与えよ。さらばどんな病気も治してみせる」
このようなことまで述べているのです。

■2400年後の今
コロナだ!インフルだ!ガンだ!アレルギーだ!
こんな風に騒ぎまわる、そんな私たちの状況をヒポクラテスが見たら、何を思うのでしょうか?
検査で陽性ともなれば、その段階から本人も家族も隔離され、あたかも犯罪者であるかのように扱われてしまう。
それが患者の心にどれだけのダメージを与えてしまうか?
そして医療機関においては、発熱も咳も痰もくしゃみも、すべて悪いものとみなされ、解熱剤や咳止め薬、抗生物質などを駆使して、ひたすら熱を下げ、咳も鼻水も止めることばかりに終始している。
それは患者自身の治そうとする力を薬剤の力で抑え込む。こうした行為に他ならない。
またドクハラなんて言葉があるように、医者は患者に恐怖と恫喝とを与えることに余念がない。
「手術を受けないのなら、棺桶を用意しておきなさい」
こうしたことを平気で述べる、そんな医者だって中にはいるようなのです。
現代医療の振る舞いと言説は反自然で非科学的で、そして病者への愛からはホド遠い。
そのようにしか私には映らないわけなのです。
「主」は患者自身。医師や医療はあくまで「従」の位置。
これは肥料も農薬も一切使わない『自然栽培』においても同じです。
主は作物自身であって、人はどこまで行っても従の位置に過ぎない。作物が本来持つ力を最大限に引き出すのが、この農法というわけです。
耕作者の仕事とは、作物を育てるところにはない。作物が気持ちよく育つことができるだけの環境を整えてあげること。
このことに尽きるというわけです。この作物は、
・水を好むのか、好まないのか?
・どのくらいの湿度が適正なのか?
・この土の状態でこの作物は育つのか?
・作物がより快適に過ごすために何が必要か?
このように作物の側に立てるかどうか?栽培者には、このことが求められるというわけです。
■涙溢れて・・・
自然栽培リンゴの生産者・青森の木村秋則さんは、肥料の投入をやめてから8年もの間、1つの実も収穫することができませんでした。
リンゴの木は虫と病気の巣になっていったと話します。
本来、春に咲くべきリンゴの花が秋に咲く、そうした事態にも直面しました。肥料と農薬を止めたことによる
「禁断症状」
にリンゴの木が見舞われ始めたのです。中にはタテに真っ二つに割れてしまった木もあったと話します。
その姿からリンゴの木が苦しみうめく声を感じ取ったと木村さんは話します。
「今まで間違ったやり方をしてしまい本当に申し訳ない。実なんかつけなくていいから、どうにか生き残ってくれ!」
この思いから、リンゴの木、1本1本に声を掛けたそうです。
こんな状態になりながらも、懸命に生きようとするリンゴの木を目の当たりにし、自然と言葉があふれてきたと話すのです。
でも、隣の家に面した側のリンゴの木には声をかけなかったそうです。
理由は、周囲の人々から"変人!"と思われないようにといった配慮からです。
すると、声をかけた方の木は8年経って見事な実をつけましたが、かけなかった方は枯れて朽ち果ててしまったそうなのです。
木村さんは、生き残れたはずの木を枯らしてしまった。そう残念そうに振り返ります。
人と作物との関係が何であるかを物語るエピソードといえるのではないでしょうか。
ヒポクラテスの提言に当てはめれば、患者はリンゴの木・医師は木村さん。苦しむ姿に励ましと慰めを与え続けた。
それにより絶対不可能とされていたリンゴの無農薬栽培が可能になった。この事実は、私たちの今に多くの教訓を与えてくれているように感じます。
作物には肥料・農薬、症状に対してはクスリなどの薬剤。
農業においても、医療においても生命をモノとして考える習慣がすっかり身についてしまっているようにも感じます。
私たちはとかく心と体、精神と物体とを分けて考えてしまいがちです。
でも、それらは本来分けることができない、一体であるはずのもの。そうした感覚を取り戻す必要性を感じます。
今世紀は「生命科学の世紀」と言われています。木を見て森を見ず、森を見て木を見ず。
そんなことがいわれますが、物質だけでも、精神だけでもない、そんな感覚に今後も光を当てていきたいと思います。
■参考文献