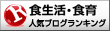「農薬」
には大きく分けて、4種類あります。
虫を殺すための農薬が『殺虫剤』。病原菌を退治するための農薬は『殺菌剤』。
栽培のジャマとなる草を退治するためのものが『除草剤』。
さらには作付けの前に無菌状態を作り出す。あたかも予防接種のように土の中に打ち込まれる毒ガスが、
『土壌消毒剤』
日本の農地には、大きくいってこの4種の農薬が日々散々に撒き散らかされているです。
そして殺虫剤と殺菌剤とをホド良くブレンドした農薬は『混合剤』。
一度撒けば、害虫も病原菌も同時に殺すことができてしまう。いわば皆殺し用の兵器・・・、こんな感じのものになるのです。
虫や菌はせっかくの作物をダメにしてしまう忌まわしき輩。
その輩たちを手間ひまかけずに手っ取り早く殺戮するためには、混合剤がカンタン便利。一度の散布で
“二度オイシイ”
それが混合材を使うメリットと言われているのです。さらにそのメリットは手間ひまを省けるだけではなく、もう1つの恩恵までをも享受できてしまう。
それが何かといえば、「相乗毒性」。
醤油とみりんを合わせれば、相乗的なシナジーを発揮して甘辛ダレができ上る。
これと同様に、2つの薬剤を組み合わせることで強力無比なダメージを虫や菌たちに与えることができてしまう・・・。
よく一度に何錠ものクスリを一緒に飲んではならない、そう言われたりもするのですが、それはこの相乗状毒性がコワイからこそ。
医薬の分野では、1つずつのクスリの副作用については結構調べられてはいるものの、AとB。2つ以上の薬剤が組み合わさって体内に入った際の副作用。
これについては、ほとんど何も
“調べられていない”
だからこそ、色んなクスリを一度に飲んではならない。このように警告されているのです。
1と1を足せば、単純に「2」になるのではなく、5にも10にも100にだって、相乗的に毒性は増していく。それは足し算ではなく掛け算の効果。
こうした効果を狙って混合剤は使われている、このように説明されるのです。

■昔と今で・・・
釈迦に説法になってしまい恐縮なのですが、現在農業の主流として使われている農薬は、
「細胞浸透系農薬」
になります。別名、ネオニコチノイド系農薬とも呼ばれています。
従来の農薬は、表皮に散布するタイプのモノばかりが使われていました。
雨や露などの水分が当たると、農薬の成分が流れ落ちてしまう。
このため農家は何度も何度も、繰り返し農薬を散布する必要があったのです。
従来の農薬ならば、食べる側の対策だってカンタンなもの。水で落ちやすい性質があるので、よく洗えばそれで済んでしまう。
また、皮をむいてしまえばそれでオシマイ。この2つの処置で、農薬リスクを低減させることができていたのです。
でも細胞浸透系農薬となると、野菜やお米の細胞の内部にまで農薬成分が浸透してしまう。
細胞の中まで農薬成分が浸透してしまうので、作物の表皮部分が傘やレインコート代わりになっている。
つまるところ、どんなに入念に洗ってみてもムダ。皮をむいても
“一切ムダ!”
今はこのようなタイプの農薬が主流になっているのです。
細胞浸透系農薬は、人はもちろん、ミツバチやトンボといった昆虫類。様々な野鳥、ウナギやエビなどの魚介類。
野生の哺乳類の繁殖、これらにも深刻なダメージ与えることが報告されています。
そのためEUや米国、カナダ、韓国、台湾など、使用禁止や規制強化に踏み切る国や地域が、ここ数年で急増している。
実にリスクの高い農薬と言わねばならないのです。
細胞浸透系農薬の残留濃度はどれくらいのものなのか?それを確かめる実験が2017年秋に農民食品分析センターのよって実施されました。
以前も紹介しましたが、長野県産・山形県産の市販されているリンゴ4種類を使い、皮をむいた皮の部分と果肉部分。
それぞれどれくらい細胞浸透系農薬が残留しているか?このようにして検査は行われた模様です。
結果はというと、皮の部分の残留量は平均で、0.578マイクログラム。果肉部分はといえば平均で2.040マイクログラム。果肉部分には皮の
「3.5倍」
もの、細胞浸透系農薬が残留している。そして細胞浸透系農薬で殺虫剤のアセタミプリドの約78%は果肉部分に残留していた。
こうした結果が明らかにされているのです。
細胞浸透系農薬ではない、いわば普通の農薬の場合は、全てが皮に残留し、果肉部分には一切残留していなかったと報告されているのです。
東京都健康安全研究センターも、2014年度版の「残留農薬実態調査」の報告書の中で、以前は見られなかった果肉部分の農薬の残留がさまざまな作物から
“検出されるようになった”
と指摘しているのです。
■何のために・・・
農研機構の研究グループは今年3月、使われた細胞浸透系農薬は、土の中で
「3年以上」
の長期間残留することを確認したと発表しました。
また秋田県立大の研究グループは今年6月に、八郎潟から高濃度の細胞浸透系農薬を検出したと発表しています。
八郎潟はお米の大規模栽培で知られる大潟村に隣接するエリアになります。
細胞浸透系農薬は、野菜にも果樹にもたくさん使われているのですが、その使用量が何といっても一番多いのは
“お米”
現代の稲作において、もはや細胞浸透系農薬は欠かせないものになっているのです。
どうして稲作の栽培現場で、この農薬が乱用されているのか?それは日本のお米には
『等級制度』
といわれる全くの不合理かつ愚か、そしてキケン。そんな制度が行われ続けていることに理由があります。
消費者にはあまり知られていませんが、お米農家は等級制度で高い評価を得るために、米作りを行っている。そういっても過言ではない現状があるのです。
・食べる人に喜んでもらいたい
・美味しい!といってもらいたい
・安全で何杯でも食べられるお米を届けたい
そんなことは二の次、三の次・・・。とにかく“等級~!”これが今の日本の稲作の現状といえるのです。
なぜ米農家は、そこまで等級にこだわるのか?その理由は「出荷価格」にあります。
高い等級を得られれば、その分高い金額で買い取ってもらえる。
一等米と二等米との出荷価格の違いは、60キログラム当たり600円もの差が出ることがいわれています。
農家の収入に直接跳ね返ってくるものだから、多くの米農家は、良い等級を取ろう!こんな感じで懸命になるのです。

■最上級とは?
等級審査で最も厳しいといわれているのが、
“色つき米”
になります。緑米が混ざっていたり、黒い斑点のある米粒が混ざっていたり、こうしたお米の混入は等級を大幅に下げられてしまうのです
それは農家にとって減収を意味するわけだから、色つき米が混ざらないように!細心の注意を図るものなのです。
お米作りとは、カメムシ対策。こうした面があります。栽培中のお米にカメムシが取りつくと、チュ~と粒を吸ってしまう。
その吸った跡がシミのような黒い斑点になって、残ってしまう。斑点米と呼ばれていますが、それが混ざると米の等級が下げられてしまう。
混入率が0.1%以下なら一等、0.3%以下なら二等、0.7%以下なら三等。
これを防止する目的で細胞浸透系農薬は使われているのです。
斑点米を防止しようと躍起になっているのですが、でもカメムシが吸った後に残る斑点。それを食べたからと言って、別段、何の害もありません。
黒い点という見た目以外は何ひとつ問題がない。そうであるにも関わらず、これを防止するためだけにキケンな農薬を何度も散布し続けている。
こんな行為が堂々と許され続けているのです。
ただ白い米に点!とあるだけのモノを防ぐためだけに、私たちの体、及び地球環境が汚染され続けている。
こんな等級制度に果たして本当に意味があるのかどうか?
意味を持たせるのならば、農薬を使わず安全に、たくさん食べられるお米を作る人にこそ、
“最上級の称号”
を与えるべきでないのか?そう強く思うのですが、いかがでしょうか?
細胞浸透系農薬のリスクは多岐に及びます。特に脳へのダメージが強いことがいわれ、
・人の凶暴化
・発達障害の増加
この問題が頻りに指摘されているのです。でもそれ以外にも、
・免疫低下
・発ガン性
・生殖機能の低下
このような危険性も併せて、報告されています。
細胞浸透系農薬は2005年から日本で使われ始めた比較的新しいタイプの農薬になります。
それが今では日本の農地と作物に、散々にバラ撒かれ続けている。農薬使用のトップはこの農薬となっているのが現状です。
細胞浸透系農薬のリスクを回避するには、とにかく
“無農薬”
の農産物を選ぶ必要があります。
特にお米は主食で食べる量も頻度も多い食材になるので、ココだけはぜひとも無農薬のものを選んで欲しいと思います。
■無肥料無農薬米・自然栽培と天然菌の味噌・発酵食品の通販&店舗リスト
■自然食業界キャリア15年のOBが綴る