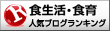世に最高の名医が
2人いる。
ドイツ医科大学のイセルス教授の言葉です。
最高とは、もっとも高いという意味。ならば最高の名医は
“1人ではないか?”
そんな疑問も湧きますが、イセルス教授は
“2人!”と断定
しているのです。
甲乙つけがたいほど優れた、世界にたった2人の名医って誰なの!?
そんな気持ちになるのですが・・・、
私たちは今、
“一億層病人”
といわれるような状況下にあります。
実際に、ガンになるのは国民の2人に1人。
約半分がかかるといった状況です。
また、
新生児の2人に1人は何らかのアレルギーを持って生まれてくるといわれ、
高血圧症は予備軍を含め約4300万人、糖尿病も約2000万人。
実に膨大な数の患者がいるのです。不調、不具合に見舞われる中、人々は、
名医探しに躍起になっている。
それは、名医に関するテレビの特集番組は、高視聴率を取ることからも分かるのです。
様々な症状に苦しむ私たちは、その2人の名医は、
誰なのか?
その2人はどこにいるのか?
そう思うのは当然のことなのでしょう。
そこで今回は、2人の名医について考えることで、医者を遠ざけ、クスリいらずの人生に
必要なまなざしを考えていきましょう。

■名医の正体は!?
2人の名医とは一体誰なのか?
イセルスはそれを、
「食欲不振」と「発熱」
この2人と述べています。
食欲不振が病気を駆逐する。発熱が体を元の健康な状態に戻してくれる。
つまり病んだ体を治すには、
“食べない”こと、そして“発熱”を敵視しないこと。
この2つが最重要であると強調しているのです。
でも、私たちは、
“栄養満点のものをたくさん食べなさい”
“栄養バランスを考え、三角食べをしよう”
”野菜不足は病気を招くから毎日30品目食べよう”
このように言われてきました。
カゼで寝込んで食欲がまったくない時も、
「食べないと治らないよ」
「食べて病気と戦う力をつけなくては!」
とにかく、
食欲不振は悪いこと。
親からも学校でも、このように教わってきたワケです。
一方の「発熱」についても、
“熱が出たらスグ〇〇”
“熱が高いと肺炎の心配が・・・”
“熱もカゼも万病のもとだから・・・”
そんな風に教ってきました。
にも関わらず、なぜ食欲不振と発熱が
なぜ名医なのか?
疑問が尽きないわけなのです。
■ガンと発熱の関係は!?
例えばガン。
ガンは体温が低ければ低いほど
“活性化する”
ことが知られています。
私たちの体温が低ければ低いほど、ガン細胞は活発になり、
増殖を許す結果を招いてしまう。
具体的には、
35℃以下で活性化
すると言われているのです。
ガン細胞は低体温を好む反面、熱に弱い。
36.5℃を越え、熱が高くなるほど活動は弱まり死滅し始める。
そして40度を超え、
42.5℃に達すると極端に生存率が低下する。
こうしたことも分かっているのです。
発熱を一方的に悪いものだと断定することは、ガン細胞の
「無尽蔵な増殖」
を許す結果になる。ガンを防ぎ、その活動を弱めるには、
発熱を敵視しないこと。
むしろ熱が上がるように積極的に促すことが大切。
こう指摘する声もあるのです。

■発熱と白血球
熱が上がると、私たちの自律神経(意識なく勝手に働く神経)は、
血流を促進
するためのスイッチが入ります。
血管を広げ、血液を患部に大量に送り込むために血管拡張物質である、
「プロスタグランジン」
の分泌が活性化します。
プロスタグランジンの活性により血管が拡張されると、患部に大量の血液が流れ込み、
血液の中の免疫部隊、
白血球が駆けつける。
こうしてガン細胞と戦う環境が整えられていくのです。
但し、プロスタグランジンの分泌は熱や腫れ、炎症などの
不快極まり症状
をもたらします。
でも、それは治癒に向かうための体の最善の反応と考えて、
体のことはカラダに任す。
ノーペインノーゲイン、痛みなくして得るものなし。
こうした姿勢で構えることが大切になるのではないでしょうか。
■食欲不振の原因は?
白血球は私たちの体に入る異物と戦い、無害化に向け働く免疫細胞です。
赤血球が酸素と栄養を運ぶのに対して、白血球は体を異物から守る役割を果たしている。
白血球は3つの細胞から構成されていて、
・5%のマクロファージ
・60%の顆粒球
・35%のリンパ球
このようになっているのです。
顆粒球は体内の異物を捕食して、活性酸素を撒き散らす細胞です。
リンパ球は異物に対する抗原抗体を作り、異物に対抗し無害化する細胞です。
そしてこの2つの細胞の司令塔であり、親分のような存在が、
「マクロファージ」
になるのです。
マクロファージは腫瘍壊死因子・「TNF」といわれる情報伝達物質を放出して、
ガン細胞を破壊する役割を担っています。
他にも細菌やウイルス、死んだ赤血球や白血球、血小板などといった体に不要で、存在してはならない、
異物を片っ端から貪食
し、無害化します。
自分の力だけでは手に余る、そんな異物の侵入を感知すると、ヘルパーT細胞を介して、
顆粒球、リンパ球に指令を出し、呼び寄せる。
「仕事入ったから頼むよ」
そんな感じなのでしょう。
細菌などの大きな異物に対しては顆粒球、強力な活性酸素で撃退させる。
小さくて繊細、微妙なサイズの異物に対してはリンパ球に抗体を作らせる。
このようにそれぞれの特性を活かし見極めながら、私たちをキケンから守っているのです。
ありがたくも、頼もしいそんな印象のマクロファージなのですが、
もうひとつの顔がある。
それは栄養の処理。
過剰な栄養を処理する役割までをもマクロファージが担っているのです。

■優先順位が劣位に!
仕事はデキる人に集中する。
職場にデキる人はたくさんはいない。
これは世の常なのでしょう。
野球でも“エース”と言われる人材は右と左で、せいぜい1人か2人が良いところ。
それと同じでマクロファージも白血球全体の
たった5%しかいない
わけです。
私たちの体はそのマクロファージに栄養処理まで担わせている。
そのことがマクロファージを多忙で、余裕のない状態に追い込んでしまうのです。
私たちが食べ過ぎてしまうと、マクロファージはなぜか、
『栄養処理の方ばかりを優先』
してしまう。
血液中の過剰な栄養分を脂肪組織に貯蔵する、その作業に没頭してしまうのです。
そうなると、病気と闘う仕事が疎かになる。栄養処理に追われて、
ガンやウイルスなどの異物と戦うことに
“専念できなくなる”
それは、仕事と家事、仕事と育児の両立がむずかしいのと同じで、
万遍なくはさすがにムリ。
そうなるとガンやウイルスからしてみれば、
「シメたもの!」
となって、増殖に歯止めがかかりにくくなってしまうのです。
■不食が治癒を早める!
この状態は症状への措置が必要な体にとっては最悪・・・。
だからこそマクロファージは自分が戦いに専念し、顆粒・リンパを巧みに指揮できるように、
あえて、
「食欲不振」
を引き起こしている。
ガンに限らず、カゼなどの体調不良で食欲不振に陥るのはこのため。
食欲がない時に食べてしまうのは、
最悪の食べ方
といえるのです。
お腹が空くことは消化器官が食べものを入れても“イイよ”という合図でもあるので、
食べたくない時は、
とにかく食べない。
ムリに食べることは、胃腸やマクロファージにも負担をかけることになってしまうのです。
またマクロファージが放出する腫瘍壊死因子の「TNF」は、体を痩せさせる働きもある。
放出期間は、やせ細って一見、病的にも見えるのですが、
それはマクロファージをはじめとした免疫部隊が
ガンと懸命に戦っている証拠
でもある。
野生動物も不調の時は、何も食べずにじっとしているのは
「治癒のプロセス」
を本能で知っているから。
“やせた”、“顔色が悪い”と思って、無理やり食べさせてしまえば
マクロファージはその栄養の処理に向かわざるを得なくなる。
病気の進行を許してしまう結果を招きやすいのです。
食欲低下はガンに負けているのでは決してない。
勝つための条件整備を行っているだけ。
だから食べてはいけないわけなのです。
そして症状の回復とともに、食欲も上がっていくプロセスを辿るのです。
■栄養過剰はハイリスク!
上記のことから、「発熱と食欲不振」は最高の名医とイセルスは述べたのです。
体は自然な健康状態を保つために、最善の努力をしようとする。
熱があるのも意味があってのことだし、炎症や腫れが起きるのにも大切な意味が込められている。
私たちは症状を“悪”と無条件に断罪する行為を慎み、
勝手な思い込みで、
治癒反応を止めてはならない。
これが自然療法によるガンの治癒を目指したイセルスの研究だったのです。
また、
普段から“栄養!栄養!”と栄養不足を憂いて、食べ過ぎたり、サプリなどを常飲すれば、
マクロファージはその処理に追われる一方になってしまいます。
栄養過剰は大切なマクロファージの
「免疫活動を妨害」
するばかりなので、栄養過多はリスクの高い行為となるのです。
マクロファージは、少ないくらいの栄養にしてこそ、本来の役割を果たせるというもの。
それが昔から伝わる
「腹八分目」、または「七分目」
に込められた意味なのです。

■栄養過多の野菜が体を蝕む!
このことは野菜も同じです。
栄養はたくさんが良い、多い方が良い。
そう思って、凝縮した栄養のカタマリである肥料を作物にたくさん与えてしまいます。
化学肥料の場合は、この作物にはこのくらいと「用量用法」があらかじめ定められていますが、
問題は、
「有機肥料の方」
有機肥料はいわば、個々の農家の“サジ加減”に委ねられているので、莫大な量の肥料分を土に投入してしまう。
こうしたケースも少なくありません。
化学肥料は即効性の高い肥料で、使えば即座に“ギュンッ”と成長しますが、
有機肥料はジンワリゆっくり後から効いていくタイプの肥料。
速効性があまりないので、農家は不安になり、ついついたくさんの量を与えてしまいやすいのです。
化学肥料に比べて有機肥料は遅効性が高いといわれますが、それは
使い始めて数年の間だけ。
過去に投入した有機肥料分が数年後には活性化し、化学肥料以上の肥効を発揮することも確認されています。
そうなると野菜は栄養過剰になり、腐敗しやすく、図体ばかりが大きい。栄養成分の乏しい野菜になりやすい。
また過剰な栄養状態は硝酸性窒素の野菜内部の残留を起こして、
ガン、糖尿病、窒息、アレルギー、アルツハイマーなど
の原因にもなってしまうのです。
※参考:『有機野菜の離乳食・赤ちゃんが葉野菜で窒息する!?』
■医学の父はかく語りき!
人も野菜も、生きとし生けるものは
「不足に強く、過剰に弱い」
これが自然界の教える真理なのでしょう。
自分の体に備わった素晴らしい機能を省みず、医者やクスリといった外部のものに依存する。
それはリスクが高いこともでもあるのです。
医学の歴史は、古代ギリシャのヒポクラテスを祖にしているといわれます。
ヒポクラテスは、それまで「呪術」であったものを医学に変えたことから、
「医学の父」
ともいわれているのです。そのヒポクラテスは、
「患者に発熱する機会を与えよ。そうすればすべての病気も治してみせる」
すでに2500年前に、こう言っていたのです。
発熱などの症状を一方的に“悪!”と断罪するのではなく、体の必要である。
このことを今後もこのブログで考えていきたいと思います。
■食の安全、百冊読むよりこの9章!
■参考文献
・『免疫革命』 安保徹 著 講談社インターナショナル 刊
・『安保徹 「やめてみる」だけで 病気は自分で治せる』長岡書店刊
・『健康不安と過剰医療の時代』 井上芳保 著 長崎出版
・『免疫の仕組み』
・『ヒポクラテス』
・『ガンは熱に弱い』:http://www.admetech.co.jp/cancer_ih.html
・『腹七分目とマクロファージ』:
http://www.kojirakawa-shiseido-hp.com/health/%E8%85%B9%E4%B8%83%E5%88%86%E7%9B%AE%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8/