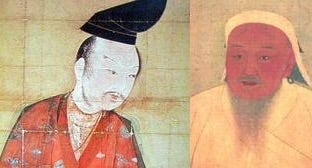モンゴル帝国の建国者のチンギス・ハンが実は源義経だったと言う説は面白いですね!時期的に辻褄が合っているので、つい信じてしまいます。
しかし、モンゴル側にそのような伝説は無いことと、チンギス・ハン、または彼の子孫が故郷の日本に錦を飾らなかったので、例え真実であっても今となってはトンデモ説の域を出ないですね!
① “伊藤博文の片腕”の卒論は「源義経=チンギス・ハン説」だった
文/千葉 信胤
長い逃避行を終え、奥州平泉の高館で非業の最期を遂げた義経。しかし、東北から北海道に至る各地には、死んだはずの義経が立ち寄ったという伝説が数多く残っている。時に英雄として、時に悪人として、時に女性を惑わす色男として、様々に残る「北行伝説」の実像に迫る!
義経が最期を迎えた、持仏堂の跡地に立つ「高舘義経堂」
明治から大正期にかけてのベストセラーとなった義経伝説
近代以降には、義経=ジンギスカン説が「伝説」を新たな局面へと導くことになった。明治12年(1879年)、後に政治家となり伊藤博文のもとで内務大臣を勤めた末松謙澄がケンブリッジ大学の卒業論文として、「征服者成吉思汗は日本の英雄源義経と同一人物也」を書き上げた。当時のヨーロッパでは日本が中国の属国ぐらいの認識であったことを憂えての著述だったという。明治18年、慶応義塾の学生だった内田弥八は、末松の英語論文を邦訳し『義経再興記』として出版、これがベストセラーとなった。
内容が内容だけにアカデミズムが受け入れなかったのは当然ながら、大衆には広く受け入れられて一大センセーションを巻き起こしたのである。
大正13年、小谷部全一郎による『成吉思汗ハ源義経也』も一世を風靡した。大陸を踏査したうえでの著作というのも大きな特徴であるが、国内の伝説については地方の新聞社や地元の郷土史家を巻き込んで収集にあたるなど、独特の調査方法がとられていたようである。刊行するやこれもまたベストセラーとなった。
末松や小谷部の説にアカデミズムからの反論がなかった訳ではない。明治29年、徹底した実証主義者で「抹殺博士」として名高い重野安繹は『学士会院雑誌』誌上で義経の平泉生脱を完全否定したし、また小谷部に対しては、大正14年に雑誌『中央史壇』が『成吉思汗は源義経にはあらず』と題して特集を組み、国史、東洋史、考古、民俗、国文、国語・言語の各学会の研究者により大々的に反論してもいた。
しかし、大衆の耳目を集めはしたものの、小谷部説を封殺するまでには到らなかった。所詮土俵が違いすぎる論争であった。小谷部はその後も『成吉思汗は源義経也 著述の動機と再論』『満州と源九郎義経』『義経と満州』を次々と刊行し、持論の普及に努めている。
注目すべきは、それらの著作のなかで義経の北行ルートが示されている点であろう。平泉からモンゴルに到る経路を一本の線で結んだのはおそらく小谷部による新たな試みであったろうが、それは期せずしてその後の「北行伝説」のありように大きな変化をおよぼすこととなった。
② 源義経=チンギス・ハン説の起源と経緯(wikiより)
源義経という人物は日本史上極めて人気が高く、その人気故数々の事実と確認されない逸話伝説が生まれた。 江戸時代中期の史学界では林羅山や新井白石らによって真剣に歴史問題として議論され徳川光圀が蝦夷に探検隊を派遣するなど、重大な関心を持たれていた。寛文7年(1667年)江戸幕府の巡見使一行が蝦夷地を視察しアイヌのオキクルミの祭祀を目撃し、中根宇衛門(幕府小姓組番)は帰府後何度もアイヌ社会ではオキクルミが「判官殿」と呼ばれ、その屋敷が残っていたと証言した。更に奥の地(シベリア、樺太)へ向かったとの伝承もあったと報告する。これが義経北行説の初出である。寛文10年(1670年)の林羅山・鵞峰親子が幕命で編纂した「本朝通鑑」で「俗伝」扱いではあるが、「衣川で義経は死なず脱出して蝦夷へ渡り子孫を残している」と明記し、その後徳川将軍家宣に仕えた儒学者の新井白石が『読史余論』で論じ、更に『蝦夷志』でも論じた。徳川光圀の『大日本史』でも注釈の扱いながら泰衡が送った義経の首は偽物で、義経は逃れて蝦夷で神の存在として崇められている、と生存説として記録された。沢田源内の『金史別本』の虚偽が一部の識者には知られていたが、江戸中期、幕末でもその説への関心は高く、幕吏の近藤重蔵や、間宮林蔵、吉雄忠次郎など、かなりのインテリ層に信じられていた。一般庶民には金史別本の内容が広まり、幕末まで源義経が金の将軍になったり、義経の子孫が清という国を作ったなどという話が流行した。明治時代初期のアメリカ人教師のグリフィスが影響を受けてその書『皇國(ミカド 日本の内なる力)』でこの説を論じるなど、現代人が想像する以上に深く信じられていた。シーボルトがその書「日本」で義経が大陸に渡って成吉思汗になったと主張したあと、末松謙澄の「義経再興記」や大正末年に小谷部全一郎によって『成吉思汗ハ源義經也』が著されると大ブームになり、多くの信奉者を生んだ。明治以後の東洋史などの研究が西洋などから入り、史学者などの反論が大きくなるが、否定されつつも東北・北海道では今も義経北行説を信じる者が根強く存在している。戦後は高木彬光が1958年(昭和33年)に『成吉思汗の秘密』を著して人気を得たが、この頃になると戦前ほどの世間の関心は薄れ、生存説は俗説にされて、アカデミックな世界からは取り扱われることは無くなっている。我国ではこの様に何世代も渡って語られてきた伝説・仮説も現代では、トンデモ説、都市伝説などと評されている。小谷部全一郎や末松謙澄らのようにこの説に関連し軍功に寄与したため勲章をもらう者もいた。義経がチンギスハンになったという説はシーボルトが最初で、彼の論文の影響が非常に大きいと岩崎克己は記している。
③ 源義経の亡命経路(参考)