昼の紹介はこちらです。
↓↓↓
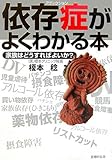
|
主婦の友社
発売日 : 2007-02-01
|
【出会い】
帯広図書館で出会いました。
【本書紹介のねらい】
~Amazonより~
人はなぜ「依存」するのか?40年間依存症と向き合ってきた著者が、その病理を解き明かす。
依存性について知りたいあなたへ。
【響いた抜粋と学び】
著者の榎本さんは1961年、東京医科歯科大学卒業。1969年、成増厚生病院副院長。1975年、山梨大学保健管理センター助教授。1981年、東京工業大学保健管理センター助教授。1988年、東京工業大学保健管理センター教授。1992年、榎本クリニック開院。2006年、医療法人社団榎会・新大塚榎本クリニック開院。現在、医学博士、医療法人社団榎会榎本クリニック理事長・院長、拓殖大学客員教授、日本外来精神医療学会理事長、日本精神衛生学会理事、日本社会精神医学会理事、日本デイケア学会理事などです(執筆当時)。
ストレス過多の現代において、依存性は増加傾向です。
アルコール依存、薬物依存などなど、依存性についての一冊です。
依存症の4つの特徴:・強迫性がある、・反復性がある・衝動的である、・貪欲性がある。
アルコール依存症の人であれば、飲む前には「今日はコップ1杯だけでやめておこう」と思っていても、いざ一口飲むと、もうやめることができません、自分の意思では絶対にやめることができなくなってしまうのです、意思の力でやめられるなどときれいごとをいっても、ちょっとでも飲んでしまえば、意思の力などどこかへ吹き飛んでしまいます。
心の病気:・病識の欠如、・否認、・反省や内省の欠如、・抑制の欠如、・依存的性格(依存と攻撃)、・言葉と心、行動がばらばら。
なぜ若い人に依存性がふえているのか:・豊かな社会、・ゆるくなった社会規範、・少子化・核家族化、・父権の喪失と地域社会の教育力低下。
依存性になりやすいタイプ:・ものごとを深く考えられない、・衝動的になる、・すぐ、かっとなる、・未熟である、・社会性がない、・じっくり話し合うことがない、・人の話を聞く耳をもたない、・自信がない、・新しいことに不安になるが、その不安に耐えられない、・強い信念をもって、それをどこまでも貫いていくことがない、・悪い意味で頑固。
細かい部分については本書を参考にして頂ければ、と思います。けっして依存性になるのは特別な人間、という感じはしないですね。
アルコール依存やタバコ、ギャンブルによくありがちですが、
「もうやめる」
と言っても、断ち切るのは難しいです。
家族なり専門家の助けが必要です。
同じ行動が、問題であるか問題でないかは、周囲の人、あるいは相手の人の判断基準によって変わるという相対的なところでないかは、周囲の人、あるいは相手の人の判断基準によって変わるという相対的なところがあり、それだけにやっかいです、つまり、問題行動などがあった場合、まわりがどのように判断するか、それを問題と考えるかどうかがポイントとなってくるのです。
「援助しないことが、最大の援助」です、つらいでしょうが、心を鬼にするのです、本人が困れば、自分でなんとかしなければなりません、本人に気づかせることが第一です、本人が「どん底体験」をしなければ自覚できないというのは、残念なことですが、それが現実であり、それしか方法はないのです。
回復には、治療を始めてから長い時間がかかります、一般的には3年はかかるといわれます、その間、本人もかなりつらい闘いをしなければなりませんが、また家族も同様に厳しい現実に直面することになります、少し良くなったと思うと、また酒を飲んでしまう、それを何度も繰り返す例がたくさんあります。
内科病院に入院して体を治療しても、多くの人はかなりよくなったところで治療をやめてしまいます、「ああ、肝臓がよくなった。これでまた酒がおいしく飲める」というわけで、再びアルコールを口にしてしまいます、つまり、内科に入院治療すると、かえって「飲める」状態になって退院するので、結局何回も入退院を繰り返している人が非常に多いのが現実です。
男性のアルコール依存性では理由や原因というのは特にみあたらないことが多いのですが、女性の場合は依存性になる「きっかけ」がはっきりしています、子どもや両親との死別、夫の浮気、近隣や友人などとの不和、ペットの死、あるいは子どもたちが独立して家の中で孤独になる、いわゆる「空の巣症候群」など、さまざまです。
パチンコの依存症となる人は、一般的にもの静かで自己主張が乏しく、消極的な性格の人が多いといわれます、ささいなことで傷ついたりして、ほどよい人間関係をつくるのが苦手のようです、半面、強い自尊心をもち、他人からの干渉をきらう傾向があります。
一人での解決、依存性からの脱却は難しいといっても、だからといって家族や支援者が何から何までやってしまうと、それはそれで立ち直れません。
2つめの抜粋にあるように
「援助しないことが、最大の援助」
とあります。
結局のところ、依存性から脱却するのは誰でしょうか?
本人なんですね。
依存性とは違う話になりますが、僕は今長男に勉強を教えているんですが、ここでも似たようなことが起きるんです。
一人では勉強を始めたり、続けたりが難しい。
だからといって、僕が何から何まですべてやってしまうと、長男は僕に言われたことをやるだけになってしまいます。
なぜ勉強をするのか、というと工業高校に行きたいからです。なぜ工業高校に行きたいのか、というと設計士になりたい、という目標があるからです。
その目標を達成するために工業高校の建築科にいく必要があります。工業高校の建築科に行くためには、勉強をしないと入れません。
じゃあ、一人でやれよ、って思われるかもしれませんが、一人で自分の目標に向かってコツコツ頑張れるのは難しいことです。
援助がやっぱり必要なのだと思います。
学校の授業でどこまで習ったのか、テスト範囲がどこなのか、どういう問題が出るのか、という支援はもちろんしますが、最終的にテストをするのは長男です。
長男の力をつけてあげないといけないわけですね。
僕に依存しているわけではないし、依存性ではないですが、人と人との関わりという部分では同じなのかな、と思って読ませていただいてます。
こちらは僕のメルマガです。
↓↓↓
「介護業界のウラのうら」
ブログでは書きづらかった内容を配信します。
介護業界の秘密、認定調査の裏ワザ、資格取得についてなど、現場の職員だから書けることをお伝えします。気軽にご登録してくださいませ。登録した日を0日として一日目、三日目、五日目と奇数日に配信されますよ!
『介護業界ウラのうら』
登録ページはこちらです。
↓↓↓
http://cttform.jp/Qm/fr/kai5/kaigo5
ここまでお読みいただきありがとうございます。
コメントは自由制です。一見さんも読者も大歓迎です。
返信は24時間以内にいたします。
※心無い非難・誹謗・中傷等は削除させていただきます。
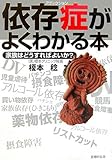
|
主婦の友社
発売日 : 2007-02-01
|