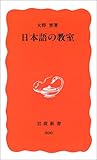みなさん、おはようございます。
今日紹介するのは、
前回の朝活読書会で
発表した書籍です。
みなさまは日本語の起源を
ご存知でしょうか?
漢字は中国からですが、
日本語の起源はとなると
そういえばどこだろう??
と思いませんでしたか?
日本から7000キロ離れた
南インドに日本語とよく似た
言葉があります。
それがタミル語です。
そして、
朝鮮にも
日本語と共通する言葉が
あるそうです。
南インドから
朝鮮を経由して
日本に伝来したのか?
と考えさせられるものでした。
普段何気なく使っている
言葉の起源
語源などなど
読んでみると
「へぇー、そうなんだ」
と驚きの連続です。
遣隋使、遣唐使
・・・
日本の文化は
学ぶ=真似ぶ
真似をする文化。
0から1を作り出すより、
1を100にするのが得意。
歴史を見ると
よりわかりやすかったです。
日本のことを
言葉をもっと知りたい
というかたは1クリック
お願いいたします。
チェック項目39箇所。
「へ」と「に」の違い・・・「へ」は遠いところに向かって移動するとき。
移動・移行の方向のときは「へ」。近い場所、動作の帰着点は「に」
あなたのこと、わたしは・・・+
あなたは、わたしのこと・・・-、女性が自分を低く言うときに使う
「わたしのこと好き?」。
気づきや持続の意味・・・「~た」、驚いた、あった。過去形だけど今使う。
日本語の起源・・・南インドのタミル人。タミル語に似通っている。
7000キロ離れている。朝鮮を経由している。
「解」・・・牛の角を刀で切り分けること。
「分」八をわけると四、四は二、二は一、「分」は刀で2つにすること。
分離できるからわかるということ。
「断」はオノで力を加えて物を2つにすること。判断も2つにわけること。
大きい・・・年配、大きな・・・体が大きい
「でも・しか先生」・・・教育熱心でない人が多かった?
日本語にロゴスに当たる言葉がない。
ロゴス・・・手にとって集める、選び出す、言葉を選ぶ
日本の学問は真似ぶが基本。
文明を作り出すことより、文明を輸入することが得意。
「へ」と「に」の違い・・・「へ」は遠いところに向かって移動するとき。
移動・移行の方向のときは「へ」。近い場所、動作の帰着点は「に」
あなたのこと、わたしは・・・+
あなたは、わたしのこと・・・-、女性が自分を低く言うときに使う
「わたしのこと好き?」。
気づきや持続の意味・・・「~た」、驚いた、あった。過去形だけど今使う。
日本語の起源・・・南インドのタミル人。タミル語に似通っている。
7000キロ離れている。朝鮮を経由している。
「解」・・・牛の角を刀で切り分けること。
「分」八をわけると四、四は二、二は一、「分」は刀で2つにすること。
分離できるからわかるということ。
「断」はオノで力を加えて物を2つにすること。判断も2つにわけること。
大きい・・・年配、大きな・・・体が大きい
「でも・しか先生」・・・教育熱心でない人が多かった?
日本語にロゴスに当たる言葉がない。
ロゴス・・・手にとって集める、選び出す、言葉を選ぶ
日本の学問は真似ぶが基本。
文明を作り出すことより、文明を輸入することが得意。