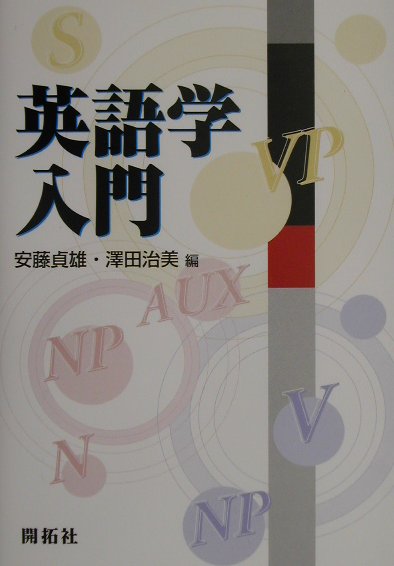前回の記事では、基本的な事柄として、弾音化とは何かを本当に簡単に説明した(馬鹿にしているとかではない)。
今回から早速本題に入ろうと考えたが、その前に、無声歯茎閉鎖音である/t/の異音(allophone)について、弾音化に関係するものだけを抽出してまとめてみたい。
※ 本記事の引用および転載は、一部分であっても絶対に認められない(2024.5.18)。無断引用や無断転載は、筆者がたとえそれに気づかなかったとしても、立派な犯罪である。日本学術振興会の研究倫理eラーニングコースを受講した君たちなら身に染みてわかるだろう。
無気音の/t/
この/t/は、音素(phoneme)としての/t/の、もっとも普通の異音であり、次に紹介する有気音の/t/と対比して、「無気音の/t/」と呼ばれる。表記する際は補助記号(diacritic)を一切つけず、[t]とする。
一般に音韻論においては、音素としての/t/は、無気音であることが前提とされている(Kahn(1976: 97), Kiparsky(1979: 437))。
有気音の/t/
英語の無声閉鎖音 /p, t, k/ において、閉鎖された調音器官が解放(release)されて後続する母音や接近音が調音されるにもかかわらず、声帯振動の開始が少し遅れ、しばらく無声の状態が続く現象を帯気(aspiration)という。これにより、/t/の破裂の際に強い息(気息音)を伴う。
表記方法は、気息音が/h/の発音に似ている点から、補助記号の [ʰ] を付けて、[tʰ]とする。南條(2001: 63)によると、有気音になる条件は以下の2つであるとしている。
(1)a. 語中のアクセントのある母音の前(e.g., re[tʰ]úrn)
b. (後ろの母音のアクセントの有無に関係なく)語頭の位置(e.g., [tʰ]omáto)
有声化された/t/
松坂(1986: 129-131)は、例えばcoming todayの発音では、有声音(voiced)と無声音(voiceless)が混在しており、有声音から無声音への切替えが2回、無声音から有声音への切替えが2回あるが、発音においては、このような切替えの数を減らした方が楽であると述べている(これは、話者の、より一般的な感性である)。
実際、アメリカ英語では、/t/の前後の分節音が有声音である場合、/t/に声がかぶさって、/t/が有声化することがある。表記方法は、有声化を表す補助記号の [ ̬ ] を付けて、[t̬]とする。
有声歯茎弾音
弾音とは、能動調音器官(active articulator)が受動調音器官(passive articulator)を瞬間的に1回だけ軽く叩く(または弾く)動作によって調音される音であり、歯茎弾音(alveolar flap)は、舌先が歯茎を1回すばやく叩くような運動をすることによって発せられる音である(南條(2005: 89))。
言わずもがな、有声歯茎弾音は弾音化された/t/である。表記方法は、[ɾ]とする([r]ではない)。
有声歯茎閉鎖音である/d/と比較して、有声歯茎弾音は、以下の2つの特徴を有する(南條(2005: 89-90))。
(2)a. 有声歯茎閉鎖音である/d/と比較して、閉鎖期間を長く延ばして発音することが
できない。
b. 能動調音器官である舌尖や舌端が、受動調音器官である歯茎に接触する面積が
有声歯茎閉鎖音である/d/と比較して小さく、その閉鎖を作るエネルギーも弱い。
(2a)についてはCatford(1977: 130)が、(2b)についてもCatford(1977: 251)が指摘している。
“tap”と“flap”という用語の違いとは?
弾音には、“tap” と”flap”という2つの用語がある。音声学者の中にはこの2つの用語を区別する人がいるが、両者を区別すべきかどうかについては、意見が分かれている。
南條(2005: 90-91)によれば、概略、2つの用語を区別する場合、両者は主として調音位置によって使い分けられており、歯茎弾音は “alveolar tap”または単に “tap” と呼ばれ、そり舌弾音は “retroflex flap” または単に“flap”と呼ばれる。
ただし、Ladefoged and Johnson(2015: 186-187)は、両者は本質的には調音位置によって区別されるのではなく、能動調音器官の動く方向の違いによって区別されると主張している。
例えば、歯茎の下で舌尖を上げ、それが歯茎にぶつかり、また下に戻る発音方法なら“tap”、歯茎より後ろから舌尖が歯茎の方向に動いて歯茎にぶつかり、そのまま前にいく発音方法なら”flap”といった具合だ。
なお、本ブログでは、Ladefoged and Johnson(2015)の主張を踏まえた上で、“tap”と“flap”を区別せず、「弾音」と呼ぶことにする(どちらの用語を使っても構わない、というわけではない)。英語表記は“flap”とする。
弾音化された/t/はラ行?ダ行?
日本人にとっては、日本語の母音間のラ行子音が[ɾ]であることから、一般的には弾音化によって生じる音は日本語の母音間のラ行子音のように聞こえると考えられるが、日本語のダ行子音のように聞こえることもある。
南條(2022: 79)は、あるデータ(ここでは紹介しません)を再分析し、弾音化された /t/ は「直前に舌の位置が高い前舌母音がある場合」に、ダ行の子音に近く聞こえる傾向があると結論付けている。
無声歯茎弾音
無声歯茎弾音は、上記の有声歯茎弾音に対応する無声音である。表記方法は無声化を表す補助記号の [ ̥ ] を付けて、[ɾ̥] とする。
無声歯茎弾音の使用に言及している音声学者は少ない。そもそも、無声歯茎弾音の存在を認めない学者もいるが、本ブログでは無声歯茎弾音の存在を認める立場をとる。
声門閉鎖音
枡矢(1976: 40)は、声門閉鎖音について「肺から出る呼気によって押し開くことができないくらいほど堅く声門を閉じると、呼気が完全に遮断される。この音を声門閉鎖音という」と定義する。表記方法は、[ʔ]とする。
声門閉鎖音にはいくつかの用法があるが、弾音化に関連するものとして、音節末位にあって、共鳴音に先行され、かつ別の同器官的子音が後続する/t/が声門閉鎖音に変わる「声門閉鎖音による置換(glottal replacement)」というものがある(Carley and Mees(2019: 17-19))。これは1つの語の中でも、2語にまたがる場合でも起こる(e.g., cats /kǽts/→[kǽʔs]やpart time /pάːrt táɪm/→[pάːrʔ táɪm])。
まとめ
1.歯茎弾音(alveolar flap)は、舌先が歯茎を1回すばやく叩くような運動をすることによって発せられる音であり、有声歯茎弾音[ɾ]は有声歯茎弾音[d]と比較して、調音器官の接触面積、閉鎖時間、エネルギーの観点で異なる。
2.弾音化された /t/ は「直前に舌の位置が高い前舌母音がある場合」に、ダ行の子音に近く聞こえる傾向があるというデータがある。
3.弾音化と声門閉鎖音の関係は意外と重要である(この点は別のブログで詳しく紹介)。
参考文献
Carley, Paul and Inger M. Mees(2019)American English Phonetics and Pronunciation Practice. Abingdon: Routledge.
Catford, J. C.(1977)Fundamental Problems in Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Kahn, Daniel(1976)Syllable-based generalizations in English phonology. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA[Published 1985, New York: Garland; Published 2015, Abingdon: Routledge].
Kiparsky, Paul (1979) Metrical structure assignment is cyclic. Linguistic Inquiry 10: 421-441.
Ladefoged, P. N. and K. A. Johnson(2015)A Course in Phonetics. Seventh edition. Boston: Cengage Learning.
枡矢好弘(1976)『英語音声学』東京: こびあん書房.
松坂ヒロシ(1986)『英語音声学入門』東京: 研究社出版.
南條健助(2001)「音声学・音韻論」安藤貞雄・澤田治美(編)『英語学入門』東京: 開拓社. pp. 32-71.
南條健助(2005)「Flap / Tap」日本英語音声学会(編)『英語音声学辞典』東京: 成美堂. pp. 89-91.
南條健助(2022)「アメリカ英語の“有声のt”について」『英語教育』第70巻 第11号. pp. 77-79.
竹林滋(1996)『英語音声学』東京: 研究社.