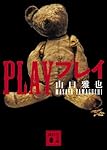外科医が、愛するぬいぐるみたちと興じる、秘密の「ごっこ遊び」。
怖ろしい罠が待ち受ける「ボード・ゲーム」。
引き篭もりたちが、社会復帰のためにと熱中する「隠れ鬼」。
自分の家族がそっくりそのまま登場する「RPGゲーム」。
四つの奇妙な「遊び」をモチーフにした超絶技巧の、ミステリ・ホラー短編集。
「ぬいのファミリー」
ぬいぐるみを愛し、ぬいぐるみを家族同然に扱う外科医の物語。
一方で本当の家庭(妻と娘がいる)は崩壊寸前というところが皮肉。
ぬいぐるみのことを「ぬいさん」と呼ぶのが気持ち悪くて可笑しい。
オチはいまひとつ。凡庸。
「蛇と梯子」
タイトルの「蛇と梯子」は実際にあるボードゲームの名前。
なんだかおどろおどろしいけれど、実態は西洋における双六である。
完全に運任せで技術や戦略の入り込む余地がないので大人向けではないけれど、
そのぶん、大人でも子供でも対等に遊べるという点では日本の双六と同じ。
物語ではこのボードゲームの呪いで猿のようになってしまった息子を救うために、
精神科医を訪れ、そこで家族四人でボードゲームをやる羽目になる。
この短編集の中では一番のお気に入り。
人がゲームに支配され、どうすることもできない無限連鎖に嵌まりこんでいく結末が眼目。
スティーブン・キング調のホラー。
「黄昏時に鬼たちは」
ネットで知り合ったものたちによるかくれんぼ。
実際にこういうサークルはいくつも存在する。
この物語では、かくれんぼが「ひきこもり」の人たちの社会復帰プログラムの一環として使われているところが特殊であり、ミステリとしての肝にもなっている。
この短編集の中で唯一、ミステリらしいミステリらしさがあるね。
ちょっとねたばらしになるけれど、使われているのは叙述トリック。
ネットではハンドルネームが使われるし、顔が見えないから叙述トリックが仕掛けやすいのだが、伏線もしっかり張ってあって、オーソドックスだけどフェアなトリックに仕上がっている。
「ホーム・スウィート・殺人」
最後の一篇はコンピュータゲーム。
現実とゲームが徐々にリンクし、重なり合い、そしてどちらが現実が(主人公も読者も)わからなくなってくる……というのは、ありきたりすぎて面白味はないね。
このタイプのミステリの白眉は岡嶋二人の「クラインの壷」で、それを超える作品には今のところ、出逢っていない。