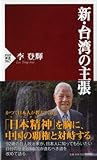
¥842
Amazon.co.jp
本書の冒頭、李氏は、台湾映画「KANO」について、この映画に描かれているのは、「日本精神」だと指摘。これは「日本統治時代に台湾人が学び、日本の敗戦によって大陸からきた中国人が持ち合わせていない精神として、台湾人が自らの誇りとしたもの」で、具体的には。「勇気」「誠実」「勤勉」「奉公」「自己犠牲」「責任感」「遵法」「清潔」などを指すのだという。そして本作を観た感想として、「私はあらためて家内と『日本の教育は素晴らしかったね』と語り合った」とある。本作について台湾では、植民地時代を美化しすぎているという批判もあったようだが、李氏は鑑賞後、記者団にむかって、「台湾人はこの映画をみるべきだ」と発言している。
李元総統には、2歳違いの兄君があったが、大東亜戦争で海軍陸戦隊員としてマニラの地で散華し、靖国の英霊となられた。李氏ははっきり述べている。「靖国神社に兄を祀ってくれてほんとうに感謝している」と。さらに「日本は英霊の魂をもっと大切にしなければならない」と叱咤までしてくれているのだ。
李氏にみるように、台湾は無類の親日国だ。これらはリップサービスでないことは、3・11の被災地への同国からの義捐金が200億円で、世界最高額だったことでも裏付けられる。戦後70年も経って、未だ我が国に恨み節全開の国家がある反面、日本を正当に評価し、感謝してくれる台湾のような国家もあるのだ。加えて李氏は、「尖閣諸島が日本の領土であることは歴史的にも、国際法上も明白である」とまで言い切ってくれている。それなのにそれなのに時の民主党政権は、東日本大震災一周年記念式典において、台湾代表として出席した駐日代表処(大使館)の羅坤燦副代表を、あろうことか各国や国際機関の代表が座る一階の来賓席ではなく、二階の企業・団体関係者の席に座らせたのだった。恩知らずもここに極まれりか、嗚呼…。
さて李氏は大戦中、京都帝大に学ぶも、1年2か月で陸軍に志願。戦後は台湾大学に編入学し、農業経済学を専攻。49年には同大学農学部の助手となり、さらに国民党による白色テロが吹き荒れる中の52年に米アイオワ州立大に留学し、修士号取得。65年には米コーネル大に留学し、農学博士号取得。同年帰国後、台湾大学教授に就任という具合に、一貫して、学究の徒としての人生を歩んでこられた。それが蒋経国(当時行政院副院長=副首相)との面会を経て、49歳で思いがけず、農業政策の政務委員(国務大臣)に抜擢されたのが、李氏にとって人生の転機となった。その後、国民党の副主席を任じられ、88年には蒋経国の急死にともない総統に就任。96年には台湾初の総統の直接選挙によって、再び総統に就任。2000年に、後継に総統候補を譲るまで、台湾の民主化と経済発展に、トップリーダーとして尽力された。
「指導者は信仰をもたねばならない」
「指導者に必要なのは『私』の心を捨て去り『公』のために奉仕する精神である」
「台湾は今こそ『公』と『私』の区別の基づく武士道的倫理観を軸に社会を再建しなければならない」
李氏は、これらの言葉を総統在任期間を通じて実践躬行された。武士道の本家本元であるわが日本は、朝野も老若男女も問わず、李登輝氏に教えを請わなければならない時にきている。
昨年11月に行われた台湾の統一地方選は、来年の総統選の前哨戦と位置付けられていたが、結果は、下馬評どおり、与党・国民党は大敗を喫した。その原因は、馬英九政権の対中融和路線にあることは明らかで、馬氏は国民党主席を辞した。
李氏いわく、「存在すること――これこそが台湾の外交である」。その意味するところは深長だが、経済関係にしても文化交流にしてもプラグマティックな現実外交なのだという。日本も台湾も今こそ李登輝氏の精神に帰らなければならない。
齢92という李登輝氏は、今なお活力と明敏さに満ちている。「女性活用」についてだけは、意見を異にするものの、政治を志す者は言うに及ばず、リーダーたる者はすべからく、本書の一言一句を拳拳服膺すべし。