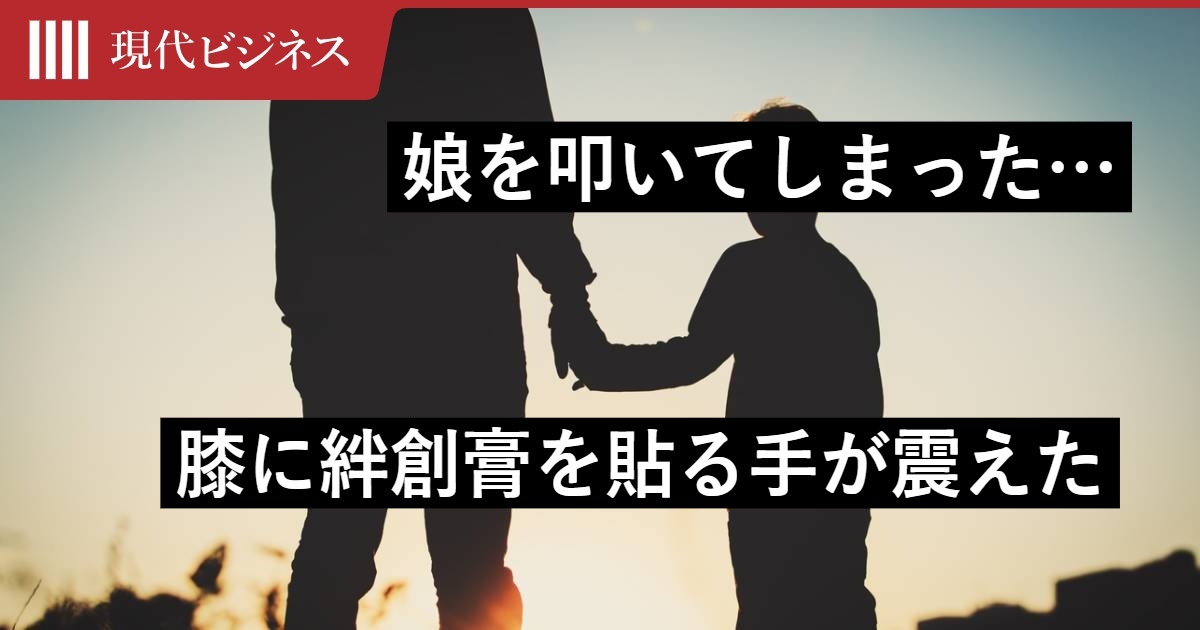大雪のなか仕事帰りにバスに乗ってたら、河原町通りのバス停じゃないところで急に停車した。運転手が「お手洗い失礼します」とアナウンスしてからドアから飛びだしてミスドに走っていった。しばらくして帰ってくると笑顔で「失礼しました」とまた発車させた。ミスドの店員さんびっくりしたやろな。
- 前ページ
- 次ページ
「ウンジュンとサンヨン」(NETFLIX)最終話まで観た。10代から40代にわたる、ふたりの女性の憧れと妬みと嫉妬と憎悪の入り混じった友情を描いた作品。キム・ゴウンとパク・ジヒョンの演技がものすごくて毎回泣かされた。尊厳死のモチーフがこのうえなく慎重に描かれる。最終話はしんどすぎて何度も中断しながら観た😭
現代ビジネスの連載を更新しました。今回は、子どもたちがまだ小さかった頃に何度か手を挙げてしまった経験を振り返り、子育てをするうえでの苦しみや、苦しんだ先に見えたきたものについて書きました。ぜひ読んでみてください。
>わたしの前に知らない男性が立っていた。「お子さん泣いてますよ。かわいそうですよ」とその人は言った。わたしは泣いている次女を抱きあげてその場から離れた。駅のベンチに次女を座らせて、膝に絆創膏を貼る手が震えた。
チェンソーマンの映画また観に行きたいねと長女と喋ってたら、次女があのラスト変やったと乱入してきた。「どうせあのラストがよかったんやろ。あんな戦ってたのに、デンジもベロ切られてたのに会いたがってんのはおかしい。あのままレゼ逃げたほうが助かるし絶対いい」。パパはラストでいきなりレゼの過去が明かされるのがいきなりな感じしたな。夜の学校のプールシーンで伏線張っといてほしかったな。長女「レゼはプールのシーンでめっちゃ楽しそうやったよ」パパ「そういうことか!」
次女「パパ、リゼロのエミリアとスバルの声優さん結婚したんやで」
わたし「そうなんや!」
次女「エミリアの人の名前は五時・間目さんで、スバルの人は六時・間目さん」
わたし「どっちも苗字は違うけど名前はカンメさんなん?」
次女「そう。結婚してふたりともロクジ・カンメさんになってん」