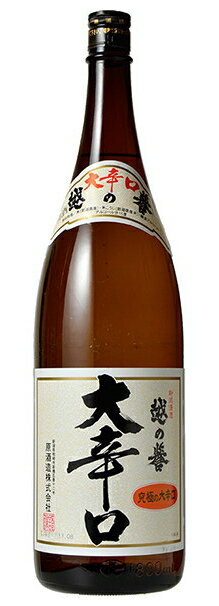越の誉 大辛口を飲んでみました。
原酒造の越の誉は日本酒41、49、342で紹介しました。
酒屋で大辛口という文字が目にはいり買って来ました。
早速飲んで見ると
辛いです。
純米酒ではないので
うまみとかはあまり期待していませんでしたが
辛口でうまいです。
純米でなくてもこんなに旨みが出せるんだと言う感じ。
好きなタイプのお酒です。
えぐみもありません。
ラベルにある「究極の辛口」というのは
辛さではなくて美味しさかもしれません。
原酒造は新潟県柏崎市にある酒蔵です。
HPを見てみると
「清酒本来の旨味の中に辛さを追求。
辛口ファンに自信を持っておすすめする
スッキリと旨い辛口酒。」
とあります。
なるほどその通りかも
日本酒度はなんと+15だそうです。
このお酒はお手頃だしかなりおすすめかも。