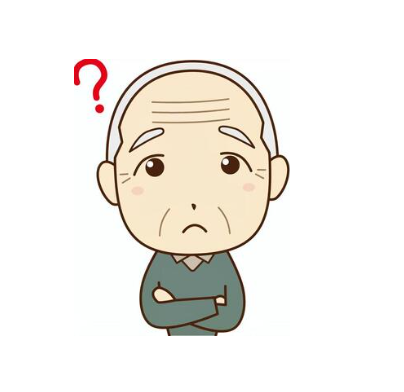以前のブログで斎藤幸平教授の「人新生の資本論」の紹介をした。
温暖化の元凶は資本主義であり、脱成長を実現しない限り温暖化は止まらない。資本主義の代りに目指す物は、人が生きる上で必須の要素である水や生活インフラを私物化せずにコモンとして共有する世界であり、先駆的な例としてスペインのバルセロナ等のフィアレスシティが紹介されていた。
私としては、資本主義が問題の根源と言う処は理解しつつも、そういう世界が実現可能なものか、俄かにはイメージ出来ずモヤモヤが消えなかったのだが、斎藤幸平教授の新著「ゼロからの資本論」が出たので、モヤモヤが消える事を期待して読んだ。
「人新生の資本論」にもあったが、ソビエト崩壊でマルクス資本論は過去の遺物になったと捉えるのは誤りとあり、マルクスはもっと先まで見据えた研究を続けて居た事が明らかになり、それが現代の問題解決の鍵になるという趣旨で、資本主義が何故良くないのかを前回よりも更に丁寧に解り易く解説しているので理解が進む。
そしてマルクスは地球環境維持と平等に相関性があると気が付いていたとあり、その慧眼には感服する。要するに、資本主義は格差を生むが、資本家は富を増す為に手段にはお構いなしで、労働者から収奪し、途上国から収奪し、自然からも収奪し、留まる事をしないので、当然自然破壊は進むという訳だ。その流れで今回は土壌の話もあり、資本主義と土壌劣化の関連に触れているが、以前このブログで紹介した「大地の五億年」の内容とも重なるので説得力がある。
一番気になる目指す姿の処は、今回もミュニシパリズムのバルセロナやアムステルダム市、ベルリン州の例が紹介されていたが、世界史で覚えた記憶のある1871年のパリコミューンが、短期間とは言え市民主導の共同体成功例だったという話に少し希望が持てた。
共同体が正しく機能すれば、経済成長の呪縛にとらわれる事なく、自然破壊のストレスは軽くなり、労働時間の短縮で自分の時間という富を増やすインセンティブが効く筈、というシナリオは、資本主義で既得権を得た人をどう納得させて巻き込むのか、という点で難しさも感じ、モヤモヤは完全には消えないものの、期待も込めてそうあって欲しいと思う。とは言え実現は容易ではなく、少なくとも世代交代が必須とも思われ、その場合は温暖化抑止タイムリミットとの競争になりそうで、何とか間に合って欲しいものだ。
先日のNHK番組「1.5度Cの約束」では今年も斎藤幸平氏の見解には触れられなかったが、資本主義否定は現体制批判とも捉えられる内容なので、マスコミもテーマが重すぎて正面から扱うのを躊躇う題材なのかも知れない。
温暖化抑制は待った無しの状況下という認識を持って、マスコミはもっと積極的に取り上げて若い世代を巻き込んで議論を広げるべきと感じた。
いずれにしても、温暖化が気になる方はご一読お勧めの本である。