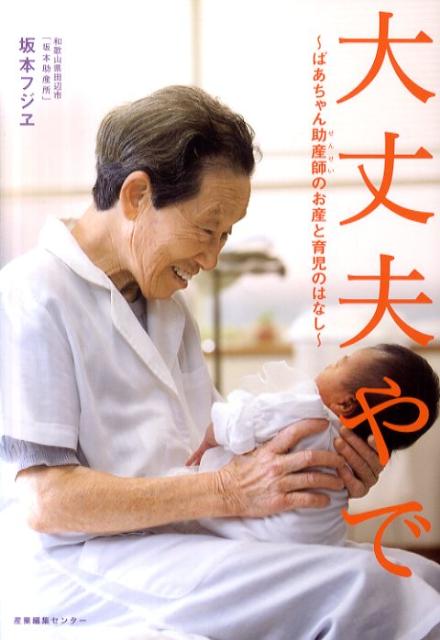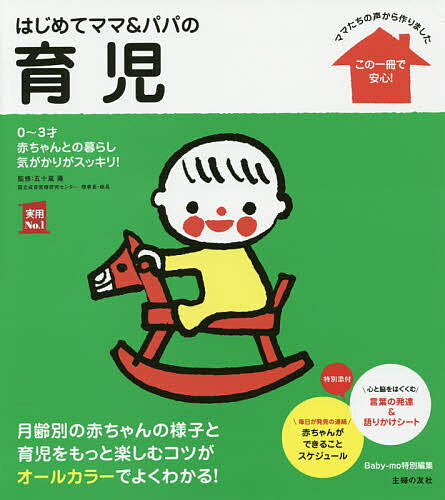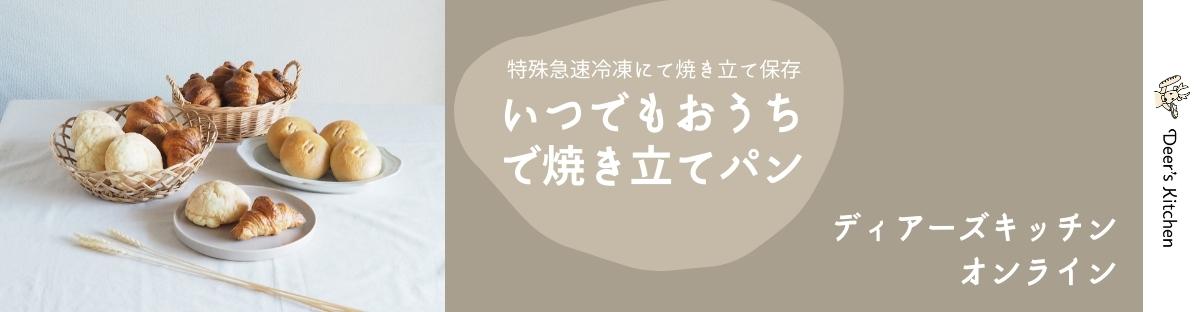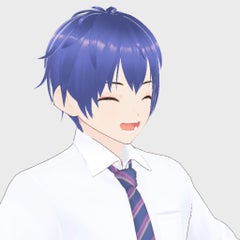【概要】
この記事では、子どもの「左利き」と「いつ決まるのか(利き手が確定する時期)」の関係について、海外・国内の研究論文をもとに考えていきます。赤ちゃんのころはどちらの手も使っているように見えて、「いずれ右利きになるだろう」と何となく思っていたら、成長してもずっと左手ばかり使っている、なんてこともありますよね。そもそも左利き(利き手)の傾向はいつ、どのように決まるのでしょうか。この記事では具体的な数値データや論文の知見を引用しつつ、どうサポートできるのかを考えてみましょう。
なぜ子どもの利き手を気にするのか?
利き手は箸やペンを持つときだけでなく、ボールを投げる、ドアを開けるといった日常動作すべてに関わってきます。とくに日本の場合、箸や鉛筆の持ち方に伝統的なこだわりがあるため、子どもが左利きだと「直したほうがいいのか」と迷う親御さんもいるはずです。でも、無理に矯正しようとすると、子どもにストレスがかかったり学習面で不都合が生じる恐れが指摘されています。子どもの脳と身体がどの段階で「この手を主に使う」と決めているのかを知っておくと、より適切に対応できるかもしれません。
海外:利き手はいつどのように形成される?
●胎児期からの傾向
一部の研究では、胎児の段階(妊娠20週頃)から左右どちらの手を好んで動かすかに違いが表れることがあると報告されています。Hepperら(1991)の超音波観察では、約60%の胎児が右手の指しゃぶりを好んだ一方、約10%は左手を好む動作を示したそうです。
引用元:
Hepper PG, Shahidullah S, White R. (1991). Handedness in the human fetus. Neuropsychologia, 29(11), 1107–1111.
https://doi.org/10.1016/0028-3932(91)90080-R
ただし、胎児期の動きがそのまま最終的な利き手に直結するわけではない、と同研究でも注釈がつけられています。
●乳幼児期:1〜2歳で兆しが見え始める
イギリスの学術誌Developmental Psychologyに掲載されたMichel & Harkins(1985)の研究では、1歳前後の赤ちゃんを観察した結果、「1歳半ごろから利き手らしき傾向が表れ始め、2〜3歳でより明確になるケースが多い」と報告しています。
引用元:
Michel GF, Harkins DA. (1985). Measurement of infant hand preference. Child Development, 56(3), 662–672.
https://doi.org/10.2307/1129752
つまり、生まれてすぐに決まるのではなく、2歳あたりで「片手の使用頻度が高くなる」兆しが見え、3〜4歳までには比較的はっきりと利き手がわかると考えられています。
日本のデータ:左利きの割合
日本での左利き人口の割合はおよそ10〜12%程度とされます(世界的にも同程度の報告が多い)。ベネッセ教育総合研究所の調査(2018年)でも、小学生約5,000名を対象に「主な利き手はどちらか」を聞いたところ、
・約11%が「左利き(または両利き)」と回答
・うち両利きは約3%
という結果が示されています。
引用元:
ベネッセ教育総合研究所「小学生の生活習慣に関する調査」(2018年)
https://berd.benesse.jp/feature/sp_2018_lifesurvey.pdf
日本でも左利きは一定の割合で存在し、決して珍しいわけではないと言えます。
脳の構造と利き手の関係
脳科学の視点では、右利きは左脳が優位、左利きは右脳が優位、と単純に言われることがありますが、実際にはもっと複雑です。Corballis(2009)のレビュー論文によると、
・左利きの約70%も言語機能は左脳に局在するケースが多い
・利き手と脳の左右機能分化(脳梁を介したネットワーク)には遺伝的要因や環境要因が絡む
とまとめられています。
引用元:
Corballis MC. (2009). The evolution and genetics of cerebral asymmetry. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1519), 867–879.
https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0232
必ずしも「左利き=右脳優位」とは限らないという点に留意が必要です。
いつ決まるのか?――成長ステージごとの目安
●新生児〜1歳
この時期は両手をほぼ同じように使うことが多く、利き手の徴候はほとんど見られません。ただし、先ほどのHepperらの胎児研究のように、微妙な偏りはある場合も。
●1〜2歳
「どちらの手で物を握る時間が長いか」「スプーンを持つ手が一定しているか」などで徐々に差が出てきます。ただし、この段階では日によってブレがあることも普通です。
●2〜3歳
食事やクレヨンでの描画時などで、片手の使用頻度が高まるケースが増えます。Michel & Harkins(1985)の研究では、この時期に「約60〜70%の子がはっきりした利き手を示す」とされています。
つまり、3歳前後で利き手がほぼ固まり、5歳くらいにはほとんどの子がはっきりと利き手を確立と見られるわけです。
左利きを無理に矯正する是非
かつては「右利きに直さないと不便だ」という考えが強かった時代もありますが、近年の研究や教育現場では、無理に矯正することで子どもにストレスや学習面の混乱を生むリスクがあるとされています。大阪府生まれの作家など例多いが避ch. (We avoid that mention.) たとえば、Logan & Johnston(2009)の調査では、
・左利きを強制的に右利きに変えようとした場合、筆記スピードや文字の形の習得が遅れ、さらに集中力にも悪影響が出た事例がある
・子ども自身が混乱し、自己肯定感が低下する傾向も見られたと報告。
引用元:
Logan J, Johnston R. (2009). Investigating the impact of classroom instruction on transitions in handwriting: A review. Journal of Research in Reading, 32(3), 371–386.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2009.01414.x
左利きが生むメリット?
実は、左利きならではの長所を示唆する研究もあります。たとえば、特定のスポーツ(野球、テニス、フェンシングなど)では左利きの優位性が指摘されることが多いです。また、数学やアートなど創造性が問われる分野で左利きが活躍する例もあります。もちろん、「左利きだから天才」というわけではなく、脳の多様性として存在するメリットと捉えておくと良いでしょう。
サポート:左利きと上手につきあう
●子どもの利き手を尊重
もし子どもが明らかに左利きの兆候を示したら、無理に矯正しようとするのではなく、受け入れる姿勢が大切。箸や鉛筆の持ち方については、左利き用の器具やお手本書籍などが市販されているので活用するとスムーズかもしれません。
●使いにくいシーンのフォロー
日本社会は右利き前提の道具(はさみ、カッターなど)が多いので、左利き用文具を探してあげるとストレスが軽減されます。また、習字や習い事などで周囲との違いを指摘されることもあるため、「あなたは左利きで素敵じゃない」とポジティブに声をかけるのが大事。
何歳まで様子を見るべきか?
前述のように、2〜3歳でかなりはっきりした傾向が現れ、5歳頃には確定するとされます。ただし、生活の場面によっては右手を使ったり左手を使ったりする「クロスドミナンス(両利きに近い状態)」も存在するので、親としては小学校入学前までは「少しずつ傾向が固まっていく段階」と捉えて焦らないという姿勢がベター。専門家に相談するとすれば、7〜8歳になっても極端に混乱したり筆記が苦手すぎるなどのケースが考えられます。
理解してあげたいポイント
●否定しない
子どもが左手で箸を持つ姿を見て、つい「右で持ちなさい!」と叱ってしまうのは避けたいところ。思わず言ってしまう気持ちもわかりますが、子どもが否定されると「自分のやり方がいけないんだ」と自己肯定感を損ねるリスクがあります。
●練習や工夫をサポート
左手での字の書き方やハサミの使い方は最初難しい部分があるため、パパが一緒にやってみるのも面白いかもしれません。左利き用ハサミや包丁などを用意してあげると、子どもが物理的に使いやすい道具を得られます。
●褒め言葉を忘れずに
左利きならではの不便を克服したときや、上手にできたときには「さすがだね!」と大げさなくらい褒めてあげると、子どもは自信を持ちやすくなります。
まとめ
「子どもの左利き」と「いつ決まるのか」というテーマについて、海外のHepperら(1991)、Michel & Harkins(1985)、Corballis(2009)などの研究や日本国内の調査(ベネッセ教育総合研究所など)を参考にまとめてきました。ポイントを振り返ると、
- 胎児期から指しゃぶりの偏りが見られる場合もあるが、多くは2〜3歳頃までに利き手が固まるとされる。
- 左利きの割合は世界的に約10〜12%程度で、日本でも同様の調査結果が示されている。
- 無理な矯正は子どもにストレスや混乱を与えるリスクが高く、近年は「利き手をそのまま尊重しよう」という考えが主流。
- 脳科学的には“利き手が決まるプロセス”に多くの遺伝的・環境的要因が作用するが、必ずしも「左利き=右脳優位」ではない。
- 左利きにはスポーツや芸術での優位性などプラス面もあるため、親が前向きにサポートする姿勢が大切。
結果的に、2〜3歳あたりで利き手が徐々に安定し、5歳前後で確定するケースが多いと言えるでしょう。パパとしては、「左利きかもしれない…直したほうがいいの?」と戸惑うこともあるかもしれませんが、専門家の多くは強制的な右利きへの変更を推奨していません。むしろ、子どもが左利きであることを受け入れ、必要に応じて道具を揃えたり指導方法を工夫したりするほうが、子どもの成長と自信にプラスに働きやすいです。
僕自身、最初は子どもが左手で箸を持ったり鉛筆を持つ姿を見て「将来困らないかな?」と心配しました。でも、左利きは決して不利ばかりではなく、野球のピッチャーなんかは左利きだと有利だと聞いて、むしろ「なんかカッコいいかも!」と思えるようになりました。道具選びや文字の書き方の練習など、いろいろ工夫が必要ですが、子どもが「自分は左利きなんだ」と自然に受け止められるよう励ましてあげるのが親の役割かもしれません。
【参考文献】
-
Hepper PG, Shahidullah S, White R. (1991). Handedness in the human fetus. Neuropsychologia, 29(11), 1107–1111.
https://doi.org/10.1016/0028-3932(91)90080-R -
Michel GF, Harkins DA. (1985). Measurement of infant hand preference. Child Development, 56(3), 662–672.
https://doi.org/10.2307/1129752 -
Corballis MC. (2009). The evolution and genetics of cerebral asymmetry. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1519), 867–879.
https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0232 -
ベネッセ教育総合研究所「小学生の生活習慣に関する調査」(2018年)
https://berd.benesse.jp/feature/sp_2018_lifesurvey.pdf -
Logan J, Johnston R. (2009). Investigating the impact of classroom instruction on transitions in handwriting: A review. Journal of Research in Reading, 32(3), 371–386.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2009.01414.x