岩辺泰史さんが、この本のことをブログ「岩辺泰吏の午後の歩き方」で紹介していました。
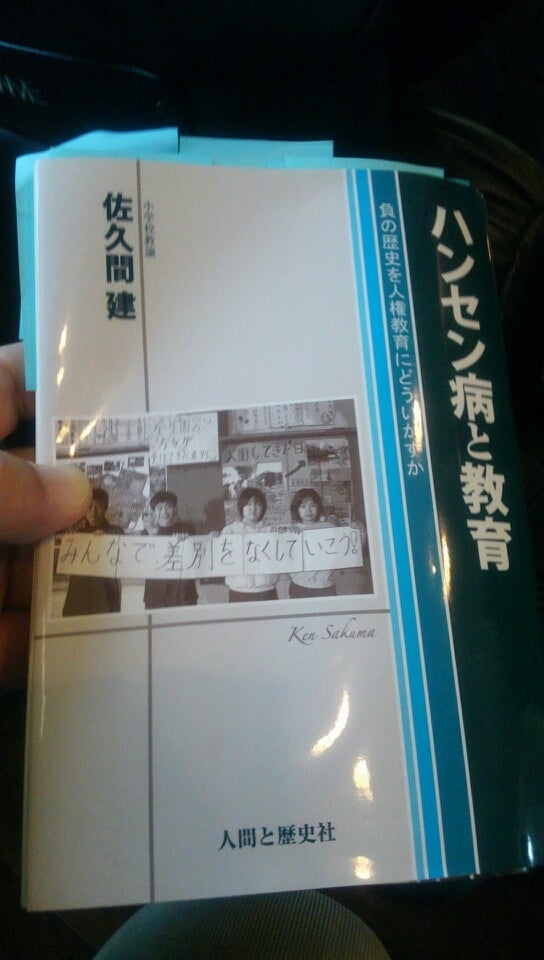
その後、「本は自分の居場所を求めてい
る」と言って、送ってくれました。「あなたのところに渡ればいい」と。
ぼくがハンセン病のことについて、強い関心を持っていることに、心を配ってもらいました。この本を買おうかと思っていたところでしたから、ありがたい限りです。





筆者の佐久間建さんは、東京の小学校の教師。
東京の東村山市青葉小学校に赴任したのをきっかけにハンセン病の問題を追求するようになったと、著者略歴にあります。
全生園に一番近い東村山市の小学校が青葉小です。(ちなみに、全生園は東村山市と清瀬市の境にあり、清瀬で一番近い小学校は、我が子たちが卒業した清瀬六小です)
佐久間さんは現場教師として、子どもたちの学びをつくるために、ハンセン病とその歴史を、実践的に自ら学んでいったことが、この本で十分にわかります。
史料的な研究はもちろんですが、実証的な多くの元患者の聴きとりの中から問題を浮きぼりにするという手法が貫かれています。
証言の一つ一つの重さに、ぼくは、何度も読み続けるのを止めてしまいました。とても読みとばすことなどできません。
この本の中で、教育と教師の責任をとりあげています。
以前、ぼくがブログにも書いた、1954年(昭和29年)に熊本市で起きた「黒髪校問題」一一竜田寮通学拒否事件一一のことでは、再び考えさせられました。
黒髪小学校に入学しようとした「未感染児童」(このことば自体にもう差別性がありました)を、PTAが中心になって入学阻止しようとした事件です。「未感染児童」というのは、
親がハンセン病者であるけれど、子どもは感染していない場合に使われたことばです。
PTAは、その子たちを入学させるなら、同盟休校をさせるとし、入学式当日には「らいびょうのこどもと 一しょにべんきょうをせぬやうに、しばらくがくかうを やすみませう」という貼り紙も校門にされました。
人権というものは、かくもふみにじられたのに、その時教師たちの大部分は沈黙をしました。
当該校だけでなく、「民主教育」を掲げて県の教職員組合も同じでした。
ぼくが以前にブ口グで書き紹介したのは、当時、熊本商科大学の教員をしていて、孤立無援状況でも声を挙げた伯父のことです。
この問題の解決について、佐久間さんは次のように紹介しています。
「この問題は、通学賛成派(少数の伯父たちのこと)が1954年9月に、国会に対して「通学」を認めるよう陳情したことがきっかけとなり、国会でも討議されました。しかし結局、国会でも問題を解決することはできず、1955年に熊本商科大学長が「里親」となって児童を引き取り、そこから通学させるというかたちで決着することとなりました。」
この学長は丸山学さんと言い、伯父の親友ともいうべき方で、伯父を国立徳島大学からこの大学に引っぱった人です。
教育を受ける権利の蹂躙という事態に対し、肝心の教師が声すらあげず、その総括すらされなかったというのは、重大なことでした。
ただ、これは熊本という地域だけのことではなく、日本の教育の持つ民主々義や人権についての希薄な問題意識の故であったとすれば、いまに引きつぐべき課題です。
この本については、あらためてとりあげてみたいと思います。
(No.1227の記事)
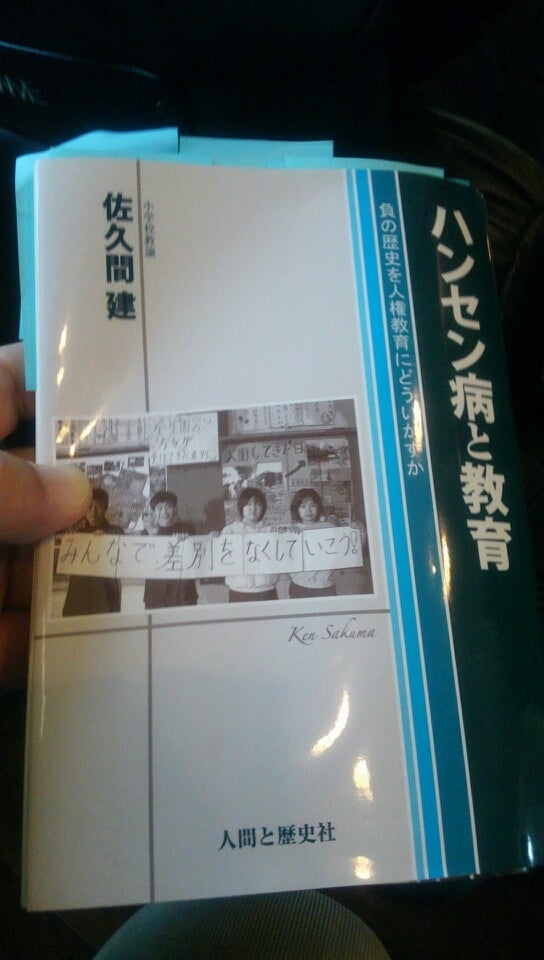
その後、「本は自分の居場所を求めてい
る」と言って、送ってくれました。「あなたのところに渡ればいい」と。
ぼくがハンセン病のことについて、強い関心を持っていることに、心を配ってもらいました。この本を買おうかと思っていたところでしたから、ありがたい限りです。





筆者の佐久間建さんは、東京の小学校の教師。
東京の東村山市青葉小学校に赴任したのをきっかけにハンセン病の問題を追求するようになったと、著者略歴にあります。
全生園に一番近い東村山市の小学校が青葉小です。(ちなみに、全生園は東村山市と清瀬市の境にあり、清瀬で一番近い小学校は、我が子たちが卒業した清瀬六小です)
佐久間さんは現場教師として、子どもたちの学びをつくるために、ハンセン病とその歴史を、実践的に自ら学んでいったことが、この本で十分にわかります。
史料的な研究はもちろんですが、実証的な多くの元患者の聴きとりの中から問題を浮きぼりにするという手法が貫かれています。
証言の一つ一つの重さに、ぼくは、何度も読み続けるのを止めてしまいました。とても読みとばすことなどできません。
この本の中で、教育と教師の責任をとりあげています。
以前、ぼくがブログにも書いた、1954年(昭和29年)に熊本市で起きた「黒髪校問題」一一竜田寮通学拒否事件一一のことでは、再び考えさせられました。
黒髪小学校に入学しようとした「未感染児童」(このことば自体にもう差別性がありました)を、PTAが中心になって入学阻止しようとした事件です。「未感染児童」というのは、
親がハンセン病者であるけれど、子どもは感染していない場合に使われたことばです。
PTAは、その子たちを入学させるなら、同盟休校をさせるとし、入学式当日には「らいびょうのこどもと 一しょにべんきょうをせぬやうに、しばらくがくかうを やすみませう」という貼り紙も校門にされました。
人権というものは、かくもふみにじられたのに、その時教師たちの大部分は沈黙をしました。
当該校だけでなく、「民主教育」を掲げて県の教職員組合も同じでした。
ぼくが以前にブ口グで書き紹介したのは、当時、熊本商科大学の教員をしていて、孤立無援状況でも声を挙げた伯父のことです。
この問題の解決について、佐久間さんは次のように紹介しています。
「この問題は、通学賛成派(少数の伯父たちのこと)が1954年9月に、国会に対して「通学」を認めるよう陳情したことがきっかけとなり、国会でも討議されました。しかし結局、国会でも問題を解決することはできず、1955年に熊本商科大学長が「里親」となって児童を引き取り、そこから通学させるというかたちで決着することとなりました。」
この学長は丸山学さんと言い、伯父の親友ともいうべき方で、伯父を国立徳島大学からこの大学に引っぱった人です。
教育を受ける権利の蹂躙という事態に対し、肝心の教師が声すらあげず、その総括すらされなかったというのは、重大なことでした。
ただ、これは熊本という地域だけのことではなく、日本の教育の持つ民主々義や人権についての希薄な問題意識の故であったとすれば、いまに引きつぐべき課題です。
この本については、あらためてとりあげてみたいと思います。
(No.1227の記事)