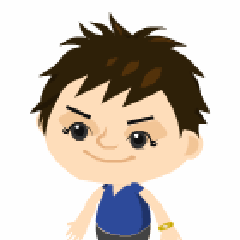前回は、「不適切指導」は実例をあげてしないように通知がなされているが、適切な指導例は示されていない。
「懲戒権はあっても実質行使できていない」ということをお話ししました。
そんな中で子どもを安全、安心にすごさせることを保障することは難しく、悲しい事案が繰り返されているひとつの要因と考えられます。
文科省の通知を見てみると、「問題行動を起こす生徒に対する指導について」等を見てみると、まず、個人でなく、チームで対応すること、出席停止も一つの手段として指導すること。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、保護司、警察、などとの連携を図り、対策会議等で検討すること等があげられえています。
たしかに、その通りなんですが、「出席停止」を命じるのは実質かなり高ハードルがあります。
それは、問題行動1回で出席停止にはなりません。繰り返し繰り返し、指導しても指導しても改善せず、あらゆる指導の手段を取った後でないとできません。もちろん、「はい、明日から出席停止ね」とは当然行かず、仮に出席停止にしたとしても、
義務教育中ですので「その子が学校に来ない間の教育計画をつくり、自宅へ学習を教えにいく」ということを同時にしなくてはなりません。現場の先生にとってとてもではない負担です。
通常の指示や言うことを全く聞かないのですから、家にいて勉強しますよと言ってもするわけありません。
このような子には愛をもって別の方法で支援することを考えるべきです。この子も大切な学校の生徒なのですから。
「高圧的な指導はだめ」「怖がらせたらだめ」「大声を出したらだめ」ということでしたら、本当にどう秩序を維持し、指導していいか現状手はありません。
「そんなことはしてはいけません!」「きまりは守ります!」と言って聞くならいいですが、聞かない子はどうしたらいいのでしょうか。いろいろ文科省の通知を見ても、具体的にこんな方法で指導せよ。とは示されていません。
生徒指導のバイブルである「生徒指導提要」にも残念ながら示されていないのです。
前に聞いたことがあるのですが、「子どもひとりひとりがちがうので一概には言えない」と回答された方がいました。
全くその通りですが、論点がずれています。
指示を聞かない、指導に従わない子をどうするか。その手立てすら教員は持っていないに等しいのです。
では、現場の先生方はどうやってやっているのか?
それは、物を投げたり、椅子をけったりすることはもちろんありませんが、それなりに厳しく、子どもと向き合います。
「絶対にひるまない、あきらめない、関わり続ける」という信念で厳しく言う先生、それをフォローする先生と役割を分けたりして子どもの心に訴えかけ、できるかぎりのことをします。そうしてわかる子もいるけど、わかるまで時間がかかる子もいます。
しかし、結果がどうであろうと、毎日、毎日、注意をし、反抗されても、暴言を吐かれても、向き合い、関わり続けるのです。
ネットで「生徒指導のコツ」などを見てみると「生徒の暴言は心を無にしよう」と書かれていました。
一度スルーすると、「この先生は許した」と子どもは判断するので、スルーするのは経験上よい結果を生みません。
暴言がひどくなり、言う生徒の数が増え、注意すると暴れたり、向かってきたりします。
スルーしてそれで済めばいいですが、目の前でスマホを見たり、いじめをしていたり、タバコをすったりしてもスルーするのでしょうか。そうはいきません。そうはいかないことが必ずでてきます。
「荒れに立ち向かい、まじめに頑張りたい子を守るため」にはそれなりの方法があります。
荒れた学校というけれど、「荒れっぱなしで好き勝手な学校」と「荒れているけど授業はちゃんと行われ、教師が荒れていること関わっている学校」では雲泥の差です。
私も学校でも行政でも生徒指導一筋できたので、生徒指導に関する知識と経験は豊富だと思います。
このような方法は代々、先輩から教えてもらっていたのですが、今は、たてのつながりや飲み会なども少なくなり、教えてもらう機会は激減しています。
この点はすごく危機感を感じています。
先生方のきつさや大変さは、長時間労働や部活動があげられますが間違いなくNO1は生徒指導と保護者対応だと思います。
そのような意味で「生徒指導力」を身につけられる機会と経験が私は必要だと思います。