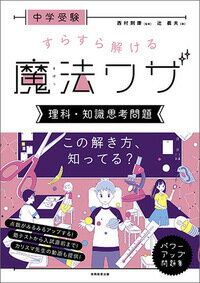ご訪問くださり、お読みいただきありがとうございます。
今日のテーマは日能研のTMクラスについて。
とはいっても、娘は通室していませんし認定を頂いているだけです。
心惹かれるTMクラス
確認ですが、TMクラスというのは日能研関東が現在は首都圏7校舎で開講している、資格制のクラスです。
Top of Mの略で、日能研関東では通常クラスを上位コースはMクラス、基本コースはAクラス、と呼び名を分けており、そのMコースのてっぺん、という意味になります。
パンフレットによると、2025の受験生が第9期生ということになりますので、今年の6年生が10期生でしょうか。
TMクラスの人数も実績をあげてきたことで増やしているようで、2025の第9期生が94名(男子61名、女子33名校舎数は当時6)その中で開成12名、合格率80%、麻布24名合格率88.8%、桜蔭9名合格率64.2%、女子学院15名合格率93.7%、豊島岡18名合格率81.8%、洗足13名合格率100%、筑駒7名、灘11名・・・・などなど驚異といっていい実績です。筑駒
たしか昨年度は90名なんていなかったと思うので、TMクラスの人数自体を増やしているんだなと思います。
開講校舎は東京3校、神奈川2校、埼玉2校ですので、けっこう限られており、遠くて通えないという子もいると思われます。
認定を頂くと、毎回立派なパンフレットが郵送されてきます。
これを読むとまあ、心惹かれる。。。。![]()
早稲アカのNNを小3からやるようなものです。
もちろん違いはその学校1校を目指すNNとは違って御三家全般レベルを目指すための授業ですが、3,4年生だとまだ余裕もあるせいか、宿題も「探究」的なものも含まれるようです。
「深い学び」ができそうだなーと感じます。
意外と多い?TM認定
前回までのTM認定では総合で1桁だったり2桁前半だったりしたので「TMはそりゃ固いだろう」と思っていました。が、今回300番台だったことで「今回はTMはないな」と思っていたのに基準点より6点上というギリギリで認定を頂いたことで、300番台前半なら可能性があることがわかりました。
割合でいうと今回は上位約3パーセントでしたね。
ただ、今回は新4年に向けて多めに出しているのではないかなと思っています。
この認定の締め切りが11月11日で締め切られるので、そこで何名入ったかによってまた次からの認定が変わってくるのかもしれません。
我が家が迷う理由
TMはサピやグノより断然魅力的であり、きっと力がつくと思っています。
ありがたいことに我が家からは「とても近い」とは言えませんが充分通うことができる範囲に校舎もあります。
しかし踏み切れないのは通塾日数の多さです。
日能研自体、けっこう通塾日数が多い塾です。
我が家は上の子のときから、基本的に自宅で勉強していたので平日の通塾に実は私自身も慣れていません(笑)
自分は日能研に通塾していて、最後は週6とか通塾しておりなんとも思っていませんでしたが、我が子を通わせるとなると平日の夜潰れるのって大変だなと思ったり(笑)
うちの場合は私が基本的には教えることができるので、本人のわかっている単元や得意な単元まで塾に行って座っていなければならないのがとても無駄に思えてしまい、もう少し効率よくできるかなとつい思ってしまいます。家で個別をやってる、みたいな感じですね。
まあうちの例は特殊なので参考にあまりなりませんが、通わせるとしたら日数以外は惹かれています。
娘はまだ時間のかかる習い事(ピアノその他)を複数しており、4年生のうちはとくにまだそちらも頑張りたい、できるなら6年生まで頑張りたいと本人が言っているのでそうなると削るのは通塾となります。。。。
通塾していると練習時間がなくなるので。
現在も、実は勉強時間よりピアノを弾いている時間のほうが多いです。。。これをいつまでできるか、にかかっています。
志望校もまだ決まっていないのですが、来年からは今まで見た学校を含めて娘が6年間楽しく、力を発揮できるような学校をしっかりみつけていきたいです。
近々、TMの説明会に行ってみようかなと思っています。
また、今回同時にいただいた「新4年生選抜 目指せ難関校!特訓講座Ⅰ」も惹かれる。月に一度で、きっと後期は後期でTM資格があれば参加できるのでしょう。
4年生になると日能研の無料のテストは、中学受験勉強をすでに始めている子には意味をなさないので、公開模試をお金を払って受ける必要があります。
または、浜学園Webにするか。。。。
志望校どころか塾すら迷っている我が家ですが、娘のキャパに合わせながら進もうと思っています。
↓計算の工夫を家で学ぶならこちら。以前の私のおすすめは廃版になってしまっため、いろいろ総合すると今のところコレがベストかなと思います。親が計算の工夫を知らない場合にこれで一緒に学びましょう。