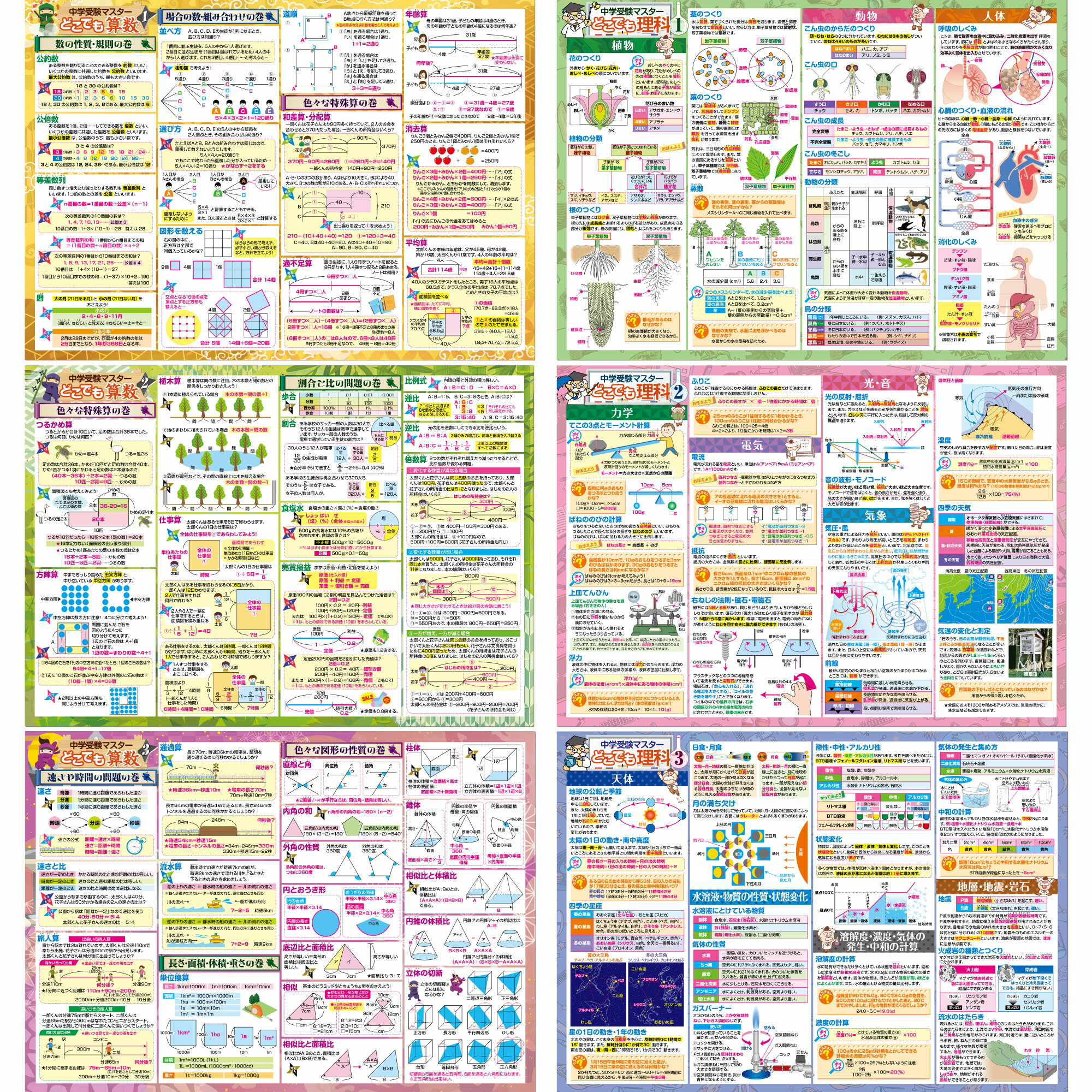ご訪問くださり、お読みいただきありがとうございます。
ご質問をいただいたので、私なりに考えていることを答えしたいと思います。
学校見学は大切です
どうやら、中学受験のブログなど界隈ではプロの方でも「学校見学なんて行く必要がない」とおっしゃっている方がいるようです。![]() 衝撃です。
衝撃です。
私が考える学校見学に行く必要がない方は、そうですねえ。基本的にはいないのですが例えば何の模試を受けても偏差値が振り切っている、常に1位、とかでその子に合う学校ってもう筑駒しかないな、みたいな子とか??
いやそれでも行ったほうがいいと思うけど。。。。
何年生から行くべき?
とにかく学校見学や説明会は出来る限り都合をつけて、低学年のうちから行ったほうがいいです。
理由はいくつもありますが、時間的に余裕があるのは低学年のうちだけです。
5年生で行けばいい、なんていう塾は最近は少ないですが(あったらそこの情報は疑ったほうがいいですね)、学校行事って、重なるんですよ??
行きたい学校の文化祭、説明会、そして現在の小学校の行事。こういうものは思っているよりずっと重なります。本当に重なるので、いまぼんやりといいな、と思う学校がある場合、ちゃんと全部文化祭日程をカレンダーに書き出してみてください。そんなことができるのは低学年だけです。
文化祭というのは例年どの学校も前年と同じサイクルで開催しますので、一度調べておけば「そっか、こことここは毎年重なるのか。じゃあ3年でこっち、4年でこっち」というように計画しておくことが可能です。
5年生になると模試も増え、最後6年で無理やりまだ見学していないからと見学する場合は、模試のあととか前に子どもを追い立てながら「とりあえず行った」ということになりがちです。
高学年の保護者からすると、低学年保護者や低学年児童が物見遊山気分で文化祭に来ていると、イラつく方もいるようです。「こんな小さいうちからきて。バカじゃないの?」という言葉に近い言葉を並んでいるときに実は私も見知らぬ人に投げかけられたことがあります。でもそこ、知人のお子さんがいて招待されただけなんですけどね。。。
私の場合ですが、自宅から通える範囲の学校の説明会は偏差値に関係なくすべて行く、すべて文化祭をまわる、くらいの勢いでいました。ですのでなんと、息子が小1からいろいろと回っていました。
当時は文化祭は年齢制限がないところが多く、予約も要らずフリーパスだったりしたので「お出かけ」「行楽」の1つというような感じでしたね。
親がまずファーストコンタクトを
かたっぱしから計画して足を運んでいましたが、ファーストコンタクトは基本的に私が一人でします。
説明会はもちろん私だけで行きます。
子どもというのは、連れていかれるとどこも気に入るし、子どもが気に入ったけれど親はイマイチということもあったりします。もしそうなったら、親子ともに傷つくことにもなるので無駄な争いを避けるためにもファーストコンタクトは親だけで、というのが鉄則だと思っています。
それは説明会でも、合同説明会でも、塾主催でもなんでもいいんです。できればその学校に足を運んだほうがいいですが、無理なら合同説明会でのその先生のお話。
それを聞いて、見て、「あ、ここはないな」と親が思ったらそこはもうナシでいいわけです。子どもにそれを見せる必要はないと思っています。
もちろん我が家だって、ファーストコンタクトが親子同時だったことはあります。しかし事前に一次情報をいろいろと仕入れたうえでまあ見てもいいかなという学校に連れて行きました。息子が気に入っても大丈夫な学校という意味です。
そういう、「あ、ここはないな」なんて、のんびりと観察できるのが、低学年のときなんです。
まだ心にも時間にも余裕があるので、大きな気持ちで見ることができます。
近所の学校は絶対に行くべし
よく、偏差値で切って〇〇以下の学校は絶対に行かせないからみにいかない、という方がいます。
しかし私はそれは反対です。偏差値は大切ですが、それは学校の価値とは違うからです。偏差値は操作でいくらでも上げることもできますし。ですが近所の〇〇は偏差値が低いからそんな学校行かせるなら公立で、とおっしゃる方もけっこう多いです。
近所の学校というのは、それが別学、共学の希望と違っていても見に行くべきです。
私ももちろん近いところ(自宅から30分程度)はすべてまわりました。
以前ブログにしていますが、滑り止め、として有効なのは「近い学校」なんです。
実際にそこに通うことになった場合。いろいろ不満はあった、あるけれどでも近いだけで生活にゆとりが出るし、満足が生まれやすいです。
家から近い。それだけで学校生活有利です。(うちが今遠いから尚更そう実感)
ですのでいろいろあって落ち続けてしまった場合に滑り止めになりそうな、近所の学校があったらそれはもう「我が家はついている」と喜ぶべきです。
しかし、偏差値が低いとか、近所だから印象が悪いとかで見学されないご家庭が本当に多い。。。。
なんででしょうね、行ってみて、嫌ならやめればいいのにと思います。まあ「嫌だなー」と思って見に行くと粗ばっかり見えてしまうでしょうけど。
コロナの教訓
うちの息子は5年生の春からコロナ禍となったので、5年、6年とくに5年の1年間はすべての学校が行事中止、説明会はオンライン、そういう時代でした。
6年生になると一部の学校で「6年生だけ対象で、抽選で文化祭に招待」という学校もありましたが、容赦なく抽選に外れるくらい狭き門でした。
お友達の中には、第一志望なんだけど決めたのは5年だから試験日まで一度も学校へ行ってない、なんて子もいましたし、それが第三、第四と下がるにつれてぶっつけ本番という子がけっこういました。
模試の会場などになっていればラッキーなので、そういう人気校は申込みも争奪でしたね。
うちは塾に在籍しておらずフリーだったため、合不合をネットで自分で申込みしていたのですが、10分前から待機していたのに1分前に電話が来て2分遅れてしまったら人気校は満席、、、、なんてこともありました。人気校の会場はプラチナチケット並でしたね。
そんな感じでかなり周囲のお友達が困っていたのですが、我が家は小1から回っていたので小4までで結局実際受けた学校はすべてまわりきり、小4ですでに2回目とか3回目の学校もあったりしました。なので小5ですべて見学ができなくなっても、まったく焦りませんでした。
あのときほど、「ただの前のめりなイタイ低学年の親」という目線を浴びながらでも文化祭などに連れて行ってよかったと思ったことはありません。
子どもはたいして覚えていない
こうまで書いても、実は低学年で子どもを連れまわしても、文化祭、たいして覚えてなかったりします。でも親子で一度足を運んだことがある、という経験が大切だと思っています。
もし何か楽しい思い出が残ればもうけもの。
子どもは二の次でもいいので、親は一生懸命普段の生徒の様子を見てみてください。
絶対に受験校選びの良い資料となるはずです。
ここ、見に行ったことがある。そういう学校の数は安心材料の数になると思います。
余裕のある低学年のうちに、丸一日かけて文化祭で遊んで、そして実際5年6年で受験校や我が子の実力が決まってきたら、最後もう一度その受験校と決めた学校だけ、確認でまわったり、説明会を聞けばいいのです。
夢を見たいなら低学年のうちに
筑駒、開成、などなど男子の有名校の文化祭は面白いです。うちなんてまったく、と思っても低学年ならそれは「お祭り」として行けばいいと思います。おりがみとか、レゴ部とか面白いですし。
高嶺の花の学校は低学年で一度行き、本当に受けられそうなら6年か5年で行けばOKです。
夢を見られるのは低学年なので。
現実も見る
現実もしっかり見ます。それができるのも低学年。とにかく、「こんな偏差値が低い学校」とか思っている学校もしっかり見ます。5年になって急に不安になって併願校を探して見に行くのは本当に大変です。
そういうときに一度低学年で見ていたり説明会に行ったことがあると、心の余裕が生まれます。
ここ、受けることになるかもなー、じゃあ入試問題解説のイベントだけ行こうかな、とか。
比較することでの発見
これも当たり前のことですが、比較材料がないと比べられないですよね。なので私も別学も共学もかなり見学しています。学校によってのカラーもよくわかりますし、同じ大学附属といっても勉強のさせ方はかなり違いますし。校風も比較することで見えてきて、同時に我が子に合うかどうか、やっていけそうか、考えることができます。
私はいつも、「うちのバカ息子がこの中にいることが想像できるか?」という視点で見ていました。
いやー無理だなーという学校もありましたし、「なんかいそう」と感じる学校もありました。
先生についても、学校の空気感についても行ってみないとわからないものがあります。
在校生の保護者もたくさんいます。思ったより部活の応援とかすごいだな(親もTシャツ作ってそろえてるとか)、とか、PTA楽しそうだな、とかそういう空気感を感じることで「自分も」この場でやっていけそうか、見ることができます。
どんどん行きましょう
低学年が一番余裕がありますので、とにかくどんどん行けるものは調べていきましょう。
9月はうちもあと2校はご新規でまわってみるつもりです。
ただし、低学年は切羽詰まっている高学年の邪魔はしないよう、おとなしくまわったほうがいいと思っています。
学校によってはとくに女子校などは人数や年齢に制限があったりしますので、そのあたりも加味しながら低学年のうちから優先順位をつけて、今年はここ、というように計画することをおすすめします。
習い事とか、予定とかあると思いますが、5年以上になったらもっと余裕がないです。
物見遊山気分、大事です。
子どものモチベーションアップについてもよく言われますが、まあそれは副産物くらいの気持ちで。
文化祭で火が付く子もいますが、つかない子もたくさん、たくさんいますので気になさらず。あくまで保護者が見学する、選びに行く、つもりで。
子どもにとっても、いざ受験するとなったときに「行ったことがある」は大きいですのでそれだけでもいいんです。やる気にならなくても大丈夫。みんなそんなもんです。(もちろんやる気になってくれたらもうけもの。)
いつ、何が起こるかわからない世の中です。
あとで慌てないように、いろいろ見て回ってください。偏差値で区切ることなく、まわってみることをおすすめします。
ご質問の答えとしましたが、今後も見学の重要性などは折に触れて書いてみたいと思います。
どなたかのご参考になれば幸いです。