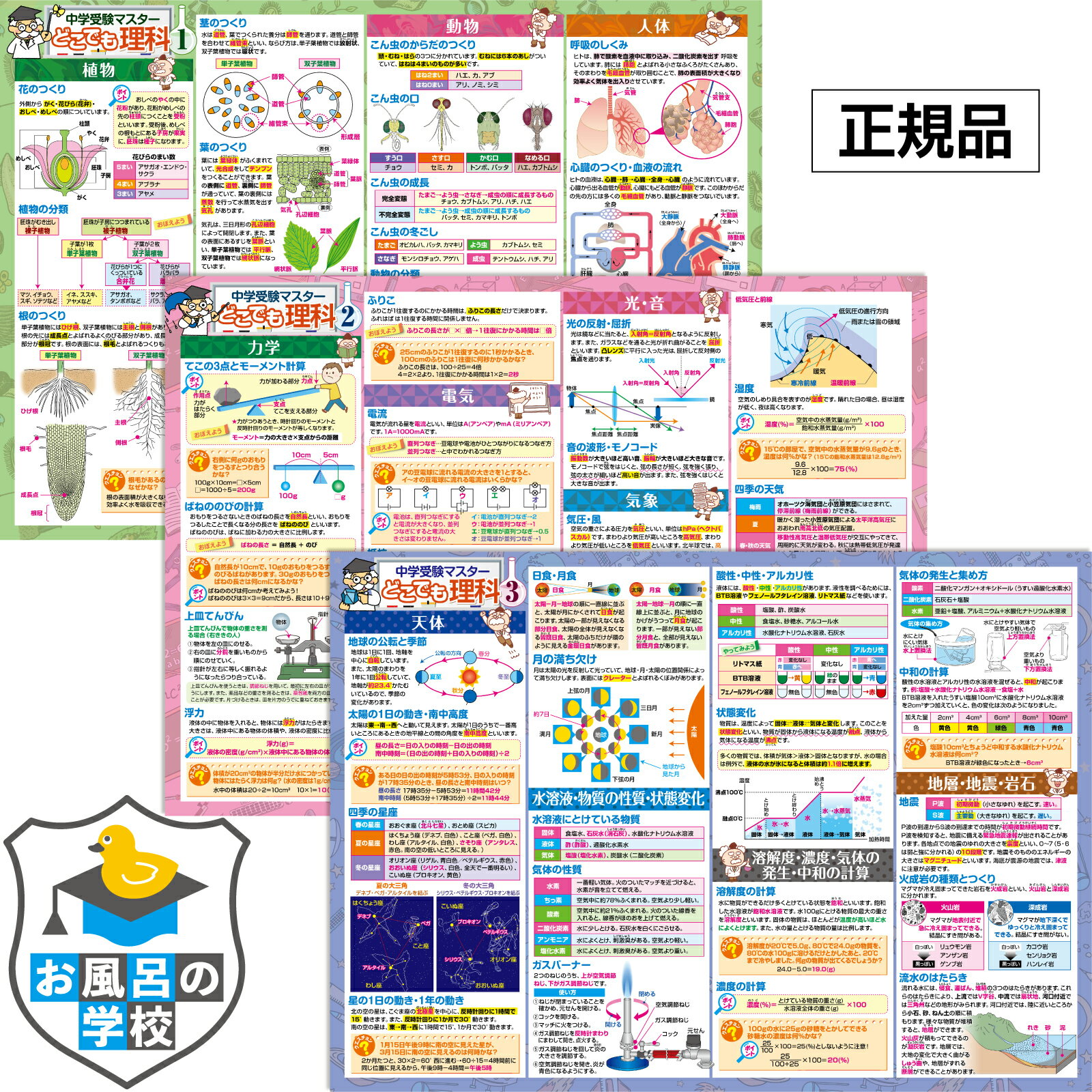ご訪問くださり、いつもお読みくださりありがとうございます。
今日は国語の対策について、いろいろとご質問をいただくことも多いので書いてみたいと思います。
今回は6年生から。いよいよ夏期講習の申し込みや日程も発表されて受験学年になったんだと実感していると思います。(主に親が![]() )
)
6年生の現在で国語が苦手な子はこれから何をしたらいいか。
苦手のレベルによりますが、四谷で偏差値55あれば、偏差値60くらいまでの学校になら届く可能性が高いです。55からならば、過去問をしっかりやりこむことによってあと5は偏差値を上げられます。これ、算数だとなかなかそうはいきません。算数偏差値55の子が60の学校に受かる、というのは大きな58の壁を超えないといけないので難しいことになります。偏差値58を超えるとどの学校も算数が一段階難しくなるので今から夏の終わりまでにしっかり苦手分野を潰していくことが必須です。
話を国語に戻しますが、国語で偏差値55取れていれば、そこまで外れた読解をしているわけではないはずです。ですので演習問題をたくさんやることであと5くらいは国語を伸ばせる可能性があります。
難しいのが現在55以下の場合。
45から55までくらいの幅がボリュームゾーンの子たちといえると思いますが、このあたりの子は概して
1.語彙力が足りない
2.読むスピードが遅い
ことで点数が伸びません。
そのため結果として
3.文の要旨を掴めていない
ということになります。
物語文と論説文では掴めていないポイントも違うのですが、それはまた次回別立てにしたいと思います。
1の語彙力。
これはワークだけで伸ばすことは不可能だと最近さらに感じています。言葉は生きているものなので、やはり実感を伴っていないと覚えられないんだと思います。子どもや若い子は造語は一瞬で作って覚えますよね?あれは「実感して」「実際に使って」という言葉の覚え方そのもののお手本のようなプロセスを踏襲しているからなんでしょうね。流行っている言葉なんかもあっという間に広がってさまざまな場面で試すように使っていますもんね。
うちのバカ息子も何にでも「ガチで」をつけたり。「ガチで?」と聞いてくるときは「それは本気で言ってるんですか?」という意味だし![]() 「ガチでこけた」は「本気で走ってたのに、転んでしまった」ですし。。。。
「ガチでこけた」は「本気で走ってたのに、転んでしまった」ですし。。。。![]()
使いながらどんどん増えている「受験に使えない言葉たち」![]()
生徒さんも似たような感じです。添削してあげて点数が振るわなかったとき。「マジかーうわー。萎えるわ~」という子。いやいや、あなたの点数ですから(笑)萎えてる場合じゃないよ!とツッコミます。萎えるってちゃんとした意味を聞くと曖昧なんですよね。
流行り言葉くらい染みついてほしいなと語彙のワークをやらせながらよく思います。
どうすればいいのか、というと6年生の今となるとワークは朝の計算の感覚でさっと続け、あとは塾や過去問で出てきた文章の言葉を本当に理解しているのか、いちいち突っ込んであげることです。解答を間違えているとき、たいてい「キーワード」となる言葉の意味を正しくとらえていません。
でもその言葉はワークでは出ているはずなんです。ワークを1人でやるだけでは苦手な子ほど定着しません。必ず指導者か、保護者が〇をつけながら会話してください。本当にわかっているか、はもちろん、それに付随する言葉、エピソード、たくさん話してあげることが大切です。これは低学年だったらなおさらです。時間はまだあるのですから、何冊語彙のワークをやったか、ではなくて1冊をしっかり読み込む。それを土台にすれば次のワークへも進めます。スピード重視でどんどんやっても定着が薄いと意味が半減します。
地道で親もめんどくさいし、「なんだそんな当たり前のこと?」と思われるかもしれませんが、「会話」から学ぶ。これが一番早いです。(低学年だとアニメとかもですね。以前サザエさんやちびまる子ちゃんを例に出して記事を書いています。)
題材としては6年生になったらもう読書をしている暇もないので(もちろんあればしてほしいです)塾の課題で出ている文章を流さずにしっかり読んで解く。これがいろいろと手っ取り早いです。
できれば、しっかり添削してもらって実戦演習で鍛えていくことが大切です。間違えているときは必ず重要な言葉の意味を正確にわかっていません。でも本人も親御さんもそれには気づきにくいので、指導者に指摘してもらって指導してもらえるといいですね。
親御さんでもできるのが、その文章を題材に会話をする。話を広げることです。そうすると出てきた言葉が定着してきます。
今日はこのへんで。明日、読むスピードが遅いというご相談について私なりの対策を書いてみたいと思います。
私のおすすめの本
中学受験に取り上げられても良さそうな本ですが、純粋に面白いです。キリン学者の女性のお話です。
ご出身は国学院久我山だそうです。そちらから東大へ進学され、学者になられました。なぜキリンをテーマにしたのかなども語られていて、動物学者に興味がある子などにはとてもいいと思います。