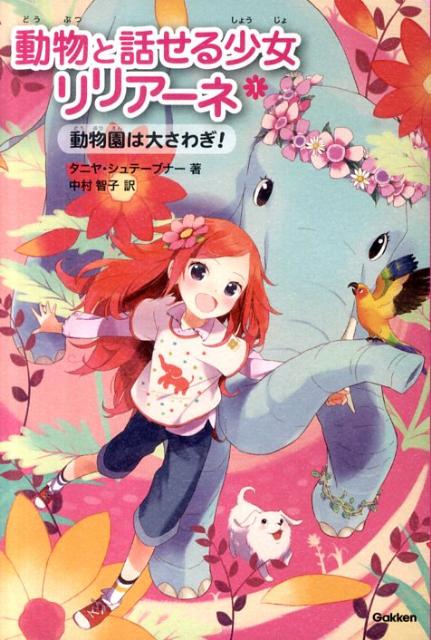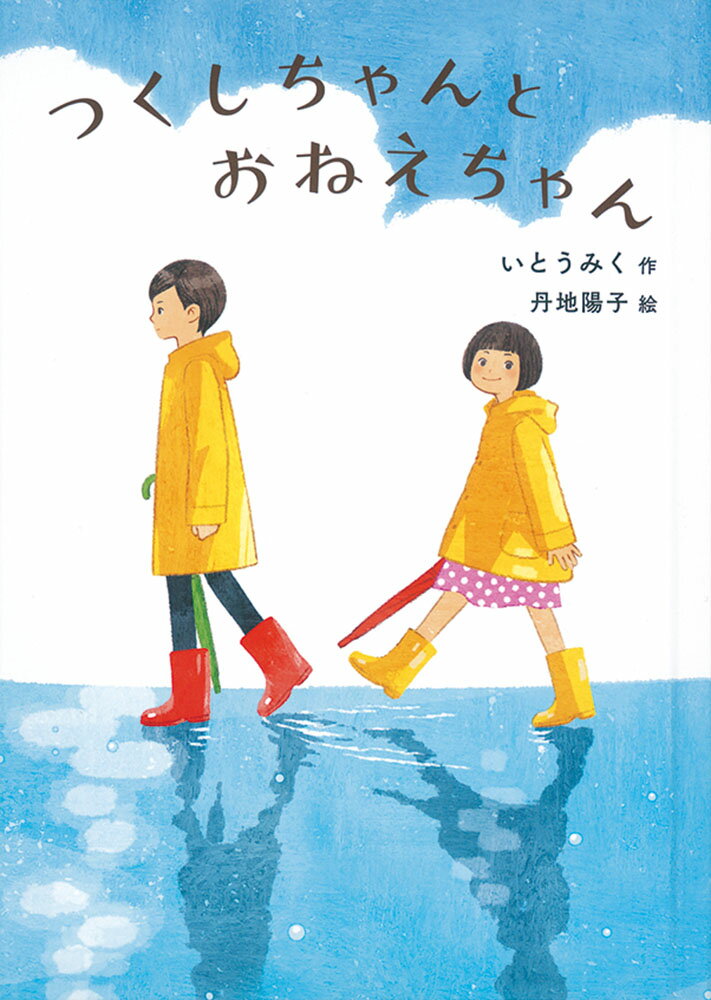ご訪問、そしてお読みくださりありがとうございます。
今回は、中学受験においての模試の意味と、使い方の注意について書いてみたいと思います。
とくに四谷の合不合や組分け、カリキュラムテストなどは準拠塾がこぞって授業で過去問をやらせて対策しているところがあります。
組み分けもカリキュラムテストも範囲が決まっているので、対策は効果的です。
私自身も、以前は決まっている単元の範囲をきちんと確認するためにも、過去問を解いて出来なかったところを復習し、「本番」のテストに臨むということは「良いこと」だと考えていました。
組み分けの過去問で算数が100点しか取れなかった子が、対策したことで130点になったりなど。
合不合も過去問がいろいろ出ていますので、ある程度理社などはどこが出そうか、予測もできてしまいます。もちろん毎年変えてありますが、作成側としても「重要だ」「確認させたい」という問題はそうそう変わらないので、似てしまうんだと思います。
ちなみに国語は(文法以外)同じ問題は出ませんので、過去問をやるのは普通に「勉強として」効果的です。四谷の模試の国語は難しいことが多いので、「鍛える」ためにはいいでしょう。
しかし算・理・社において、この3年ほどで、そうやって出していた組分けの偏差値、ひいてはクラス分けにつながる偏差値、が実力より上振れしてしまっていたのでは?という子に当たっています。
もしかして、瞬間的に偏差値を実力以上に押し上げてしまっていたのか?という疑問が入試結果を見るとわくのです。
具体的にいうと、「持ち偏差値」の学校に全然受からない。
持ち偏差値より5下の学校くらいでなんとかひっかかる感じです。
とくに、メンタルが弱い子に多い傾向です。
ここからは完全な偏見と予測になりますが、メンタルが弱いため、「初見」に弱い。「慣れていない環境」にも弱い。「不安感」が強い子が多く、少しでも形式が違うと動揺する。逆に「ホーム」では強い。
こんなタイプの子が増えているように思います。
こういう子に、模試の過去問をやらせて慣れさせるのは点数と偏差値を上げるのに有効です。
しかし、理社はとくにですが、ちょっと聞き方が違うと自分が知っている知識を聞かれているんだ、ということに気づけないのがこのタイプです。同じパターンのものばかりをあまり思考せずに学習しているので、すぐ「知らない問題が出た」と思い込んでしまう。
会場も、机が違った、時計が違った、そのようなことに敏感だとすぐ動揺してしまう。
もちろん、小学生ですからある程度は当たり前だし、みんなもそうです。また
本番だって「過去問」があるわけですから、それをやりこんでいくわけですから「準備万端」なはず。
でもなぜ、本番で力を発揮できないのか??
アウェイに慣れていなさすぎるのではないかと思うのです。
四谷の合不合 組分け(書き間違えました。)の形式って実は独特で、算数の傾斜配点がありすぎだし、問題のめくり方もああいうタイプの学校は、ほぼないですよね?
とはいえ、その分しっかり過去問もやったはずなのにな~という子が増えていて。
私の力不足を痛感するわけです。
だけどそういう子が増えてみると、パターンがあることに気づいて、それが上に書いたような「模試の過去問やりすぎた?」という子たち。
真面目で熱心がご家庭に多く、きっちり問題パターンまで保護者が分析している家庭もありました。
あとはご家庭がというよりも、四谷準拠塾が鬼のように合不合や組分けの過去問をやらせているパターン。。。
そして全員共通で、初見に弱く、メンタルが弱い。
四谷の問題なら取れるけど、サピックスオープンだと解けない。。。
そもそも、ほとんどの子が私がいくら進めても、サピックスオープンや日能研公開模試を受けに行かない。
メンタルが弱い子ほど、失敗してもいいアウェイに挑戦してみることは大切だと思います。
塾の先生は、「うちの塾の模試だけで充分です」というと思うのですが、本当に充分な子と、ちょっと理由があって鍛えたほうが、経験したほうがいい子といるのだと思います。
また、以前よりもメンタルが弱い子が増えていると思うのでそのあたりも影響しているかもしれません。
別立てで書きたいことですが、「うちの子には絶対に、「落ちる」という経験を人生で一度もさせたくないんです。傷つきますから。だから絶対に受かる学校を受けさせます」という保護者も増えています。![]()
これを話すと「うそでしょ~」と知人は笑うのですが、そんなにレアでもないです。
まあ、無謀な教育虐待より全然いいのですけど、でも開成や渋幕じゃなくて海城を受ける理由が「校風が気に入ったから」ではなくて、「確実に受かるから」みたいな理由って。。。ねえ。。。
まあ、その海城も合格ラインには十分いる子だったのですが、「合格ラインにはいるんですから、絶対に絶対に落とさないでくださいね!!」と念押しされるこちらのプレッシャーったら。
まあこの話は横道でした。戻ります。
入試本番はどんなに過去問をやっても何が起きるかわかりません。
ナイーブな子ほど、外部模試で失敗しておいたほうがいいと思います。
もちろん、サピや四谷系、浜、希、グノ、日能研のトップクラスの子は別です。そういう子は何があっても受かるくらい実力がすでにあるので。
偏差値60超えるか超えないか、から偏差値40台までの子はお子さんの性格によって外部模試とかで鍛えてみる。または過去問で対策しまくった模試の結果は少し控えめに評価する、などの心づもりが親側に必要なのかな、と思います。
とくに、そういう子は1月受験で不本意な結果だったり、または2月1日に落ちてしまうと雪崩のように崩れてしまうことが多いです。
やっぱり小学生、ということで精神的なケアや少しずつメンタルを鍛えるような対応も必要かなと思う日々です。
お読みくださりありがとうございました。
今日のおまけ
逆算が苦手な子の相談がまたあったので、再掲します。
ちょっと最初はまどろっこしいかもしれませんが「手順を踏む」ということが理解できます。逆算だけに特化しています。
計算全体を学びたいなら、ふくしま式や山本ドリルのほうがいいと思います。
サイパーはとにかくテーマ別に細分化されていて、苦手なものだけ出来るのでピンポイントで復習や予習できます。問題集が薄いのも良い!
おまけ2
娘がここ数日で一気に借りてきて読み漁っているのが
『動物と話せる少女リリアーネ』シリーズ。
欲を言えば中学受験対策になるような本ばかり読んでほしいけれど(笑)自分で選んできた本ですし楽しいなら口出しできません。
おまけだけど、これはぜひ国語に悩む低学年の保護者に
こちらは中学受験では定番の作家さん「いとうみく」さんの本
2022年の読書感想文の課題図書だったようで、図書館で見つけたそうです。これも自分で選んできました。
いとうみくさんの本でも低学年向けのものがあったのですね!!勉強不足でした。
娘に助けられました(笑)
つくしちゃんシリーズ、中学受験対策としても低学年にぴったりの童話作品なのでかなりお勧めです。読書が嫌いな子は読みたがらないかもしれませんが、一緒に読んでみたらいいと思います。おお、やはり「いとうみく」だな、という作品です。国語を伸ばしたい低学年の保護者はぜひ購入するか、または図書館で探してみて、お子さんと読んでみてください。
長々と本日もありがとうございました。