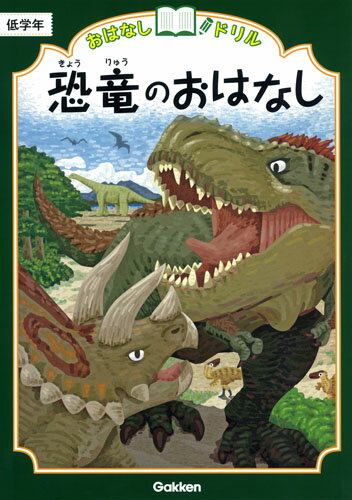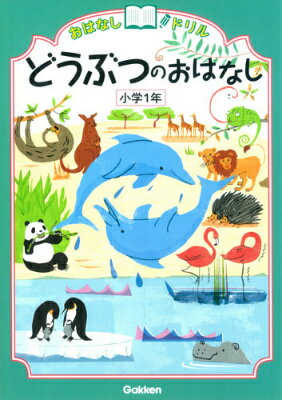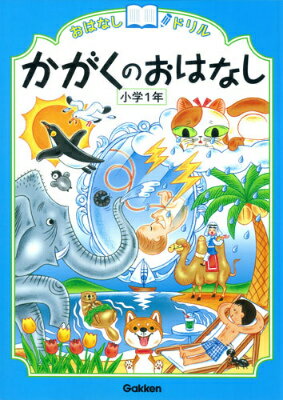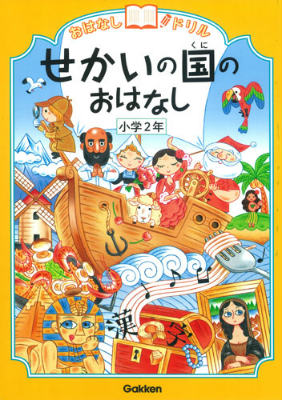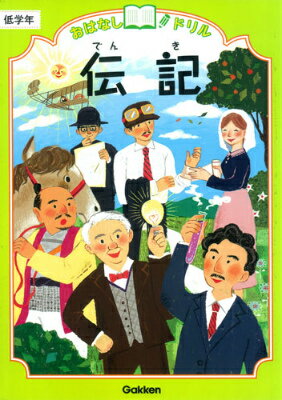ご訪問くださり、ありがとうございます。
そしていつも読んでくださる皆さま、ありがとうございます。
今日のテーマも、そうですね、私の中でも昔と比べていろいろと考察するなかで、最近考える話なのですが、
今日投げかけたいのは、
「中学受験の準備として、とにかく算数だけ進めておけばいい」という「正解」が実は過去のものなんじゃないか?今は少し違ってきているんじゃないか?という問いかけです。
うちの息子(2022組)が低学年のころと、現在の娘(2029組、現小2,新小3)の状況も、かなり違っていますし、息子のころに通用した「セオリー」「正解」が結果として実はそんなに「正解」でもないんじゃないの?と思うことが多いのです。
いろいろありますが、まずは息子の頃は定番の考え方だった、「とりあえず、算数だけ先取りし、算数だけどんどん鍛えておけば最難関に最も近い」みたいな定説は、今は通用しないんじゃないか、と思っています。
毎度のことで、エビデンスがあるわけではないのですが、通用しなくなったというのは別に「算数先取りが意味がない」とか言っているのではありません。ここはお間違えないように。
現在でも、そしてたぶんこれからも中学受験において一番、合格者平均点と、受験者平均点の差が開くのは「算数」です。次が国語、次が理科、次が社会(理社は傾斜配点の学校が多いからというのもありますが)。
算数なんて10点以上差がついてしまう学校もあります。つまり、今も昔も「一番大事」なのは算数なんですね。
それはそうなんです、そう思います、私も。私の好きな社会なんてて算数のトップ講師からしたら「ゴミみたいな扱い」なんです![]() 社会なんて、丸暗記すりゃいいだろ、という。(今はそうもいかないんですけどね、でもまだそういう先生も本当にいます(笑))
社会なんて、丸暗記すりゃいいだろ、という。(今はそうもいかないんですけどね、でもまだそういう先生も本当にいます(笑))
という昔からの定説で、
算数が大事。算数はたくさんやってきたなんだな、という子がたくさん。
でもなんか違和感を感じる子が多い。小4の途中から小5くらいで、「算数のほうが得意で・・・でも国語が苦手みたいで」という話でお預かりするお子さんが増えており、私もそうなんだな、と思って始めるのですが、なんか、おかしい。
本当にこの子、算数得意なのかな?と思うのです。で、国語が思ったよりも出来ない。
過去の偏差値を見ると、たしかに算数はサピなら55以上、四谷なら60くらいは取れている。国語は50いくかいかないか。場合によっては40くらい。
まあ算数のほうが好きなのかな、なんて思って進めるのですが、算数も好きじゃなさそう。国語もワーク類はやってるはずなのに、定着してない。読むスピードが遅く、読解も的からだいぶズレている。。。![]()
算数も小5の比が出て、図形も複雑になると、なんだか以前より得意科目でもなくなって、国語がもともと出来ていないので、2科目一緒に下がってしまって立ち位置が下がってしまう。![]()
なんでこうなってるんだろう、出来ないはずじゃないのに。と思う子が増えていてここ数年ずっと首をかしげていたんです。
そんな中で考えたのが、「算数を無理やり先取りさせて、見せかけで成績を上げた子が増えているのか?」ということです。
確信はないですが、いわゆる「算数ブースト」とでもいいましょうか。
念のため書きますが、もちろん、
「算数の先取り」これは意味は、あります!すごくあると思います。
ただ詳細に書くとそれだけで何ページも書けちゃいそうですので今日はざっくりいうと、「内容」と「やり方」は重要でして、
私が「意味がある」「役立つ」なんなら難関校合格に低学年に「必須」と思うのは、以下の3点です。
・公文等での四則混合計算、とくに小数、分数計算の先取りと、完成。(新4年になるまでに)
・絵や図を描いて考える癖。
・サイコロや立体などに触れながら考えたり、立体自体を作成する体験。
このような「先取り」は効果的です。できるならやらせたほうがいい、と思います。
この3つがあったうえでの、フォトンとか、きらめき算数とか、算オリとか、予シリ先取りとかは、効果的だと思います。ただし、最初の小数・分数までの四則混合計算を完璧に。これってかなり根気も時間もかかります。「普通の子」にはそう甘くはありません。
しかし、現在はこの3つをしっかり固めるというご家庭よりもさきに、
・とにかく『きらめき算数』や『理系脳を育てる』などで「思考問題」に触れさせ、繰り返して覚えさせてしまう。
・サイコロや立体も、点図形で描けるようになる前に、6面あるとか、重ねている面の数え方とか、見えないサイコロの数え方とか、特訓する。
・低学年模試の過去問を手に入れ、対策に対策を重ねて模試を受けさせる。
このような対策で、とにかく低学年模試で「そこそこ」の「算数の」成績を取らせて満足している保護者が多いと感じます。
このときに、ほとんどの保護者が「算数」しか勉強させていません。読書や言葉を知ること(ワークじゃなくてね)、言葉と体験と物がリンクするような経験をさせること、そういうことよりもとにかく、算数、算数、となっている。
厳しい言い方を偉そうにさせてもらうと、着実、正確な計算力の前に、小手先の思考問題ばかりやっている感じです。
失礼を承知で書くと、共通しているのは以下のことです。
全員にすべて当てはまるわけではないけれど、5つのうち3つ以上は当てはまります。
・両親どちらかが熱心で(なぜかお父さまがすごくきっちり計算して、計画している方のほうが多い![]() )、とにかく市販の思考系などの問題集をたくさん与えている。
)、とにかく市販の思考系などの問題集をたくさん与えている。
・お子さんの「算数」の力ばかりを「鍛えている」が、算数も低学年模試で飛びぬけてトップクラスの出来、というわけではない。でも偏差値60はちょくちょくオーバーするくらいは取れる。なので、低学年の選ばれた子の模試だし、うちは出来るんだな、うちの子は理系なのかな~、算数は得意なんだな~と思っている方が多い。
・国語の模試の結果が算数に比べて偏差値20くらい低い。
・親主導で勉強はしているが、自分から勉強が楽しい、とかいい点を取りたいな、とか意欲があるわけではなく、モチベーションは低め。本音は勉強したくない。勉強に対してネガティブな感情を持っている。
・読書が嫌いではないけど、好きではない。
このようなパターンの低学年時代を過ごしてきた子の5年からの失速が目に余るな、というのが最近の私の実感なのです。。。![]()
低学年模試はそれで乗り切れてしまうし、たくさん勉強して、先に算数をいろいろやっていた子のほうが上位にいきます。
しかし、そこでしっかり「国語」のほうも鍛えておかないと、算数の力も失速するように感じます。読めないと、解けない。難関校ほどそうなっていますし、理社もまずリード文が正確に早く読めていない子は総じて「低学年のとき家庭で算数だけやってきた」という子です。
まず、言葉。語彙の問題集やマンガはもちろんおすすめ、すごくいいのですが、でもそれを与えっぱなしではダメで、どうして算数はつきっきりで見ているのに、わが子の国語の力を心配しないのかな~と思ってしまいます。問題集やマンガを子どもが読んだら、一緒に会話してあげれば、ぐっと定着率が上がります。
簡単な国語の問題集を解かせてみれば、わが子の語彙レベルが何年生なのかわかります。読解方法より何より、語彙。言葉を知っていて、使えるか。楽しそうなお話で薄い(これ大事!)問題集がたくさんあります。
「国語はあとから精神年齢が追いついたら自然にできるから」
これは今もよく言われることなのですが、昔はそうだよね~と思っていた私ですが最近は「ほんとにそうか!?」楽観的すぎないか?と思うのです。
それくらい、ちょっとどうしよう、どこから手をつけよう、と思う小4のお子さんなどが増えています。
小3以下でも同じです。
長くなりすぎているので、続きはまた明日書きます。
低学年模試で、本当に読めてないな、興味を持てていないな、という子は以前も紹介しましたが、学研のこちらの中からその子の興味を持ったものを選んであげてください。けっして、本を読まないような子に、最初から「トップクラス」とか、「はなまるリトル」を与えないように。それは、国語が得意な子が「読解方法」を学ぶために使う問題集です。
まず、言葉を知っているか、知らないなら興味を持って新しい言葉を覚えてもらうために、題材をこちらが本人に寄せてあげることが大切だと思います。
この学研シリーズ。どんな子でも、1冊くらいは好きな分野が見つかると思います。
文章も短い!ですが、苦手な子はこれすら、パーフェクトには解けないはずです。