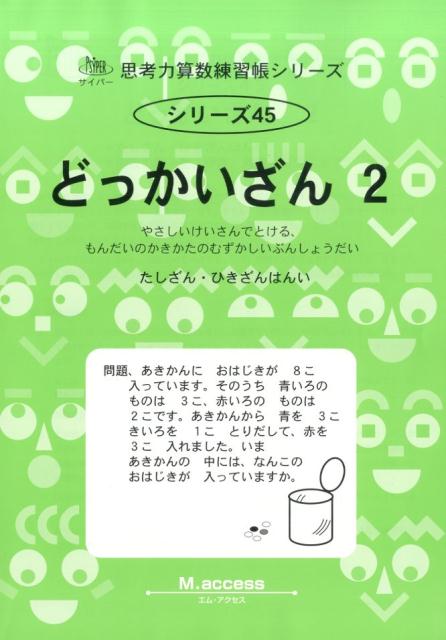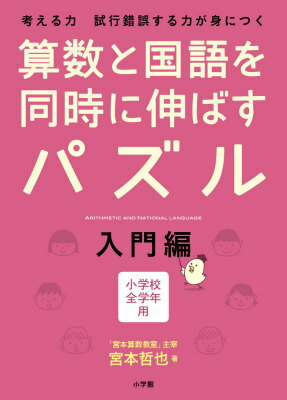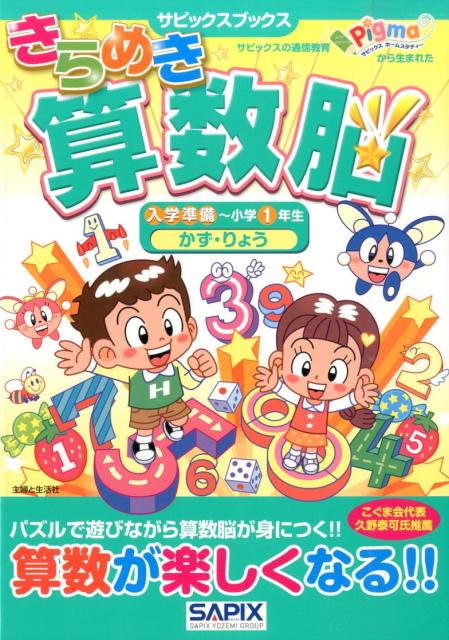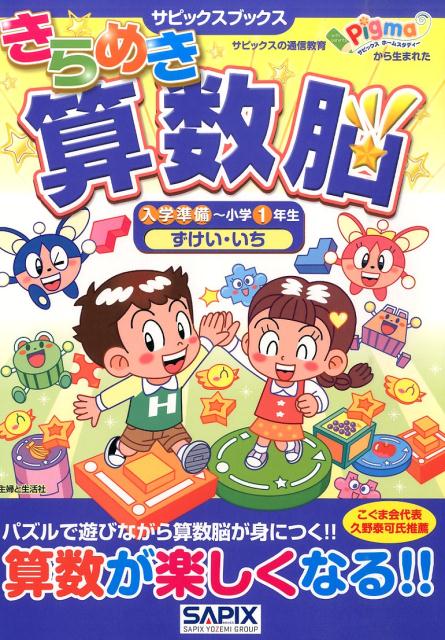いつもお読みくださりありがとうございます。
体調を崩しそうになっており、冷や冷やしながら生活しておりました。今でも万全ではないのですが、なんとか持ちこたえています。同僚が次々とインフルエンザで倒れており、代講、代講、また代講、代われる限りは代わってあげております。![]()
代講というのも、引き継ぐことで他の講師の教え方について学ぶ勉強になりますし、インフルエンザやコロナなどは「明日は我が身」ですので私でお役に立つなら、と思っています。
さて、以下のようなご質問をいただきましたので、改めて公文の高進度と文章題や読解力との関係について書いてみたいと思います。
ご質問↓
「最近フォローを始めさせていただきました。小学生低学年の算数問題でも、文章問題は国語力が必要だと思いますが、いかがでしょうか?うちの子供は年長でくもんFまで来ていますが、文章問題をやらせると聞かれていることが理解出来ず苦労しています。どのような対策をしていますか?
あとスマイルゼミなどのタブレット教材はどのような評価でしょうか?」
まず、こちらのブログでは繰り返し書いておりますが、中学受験においてもそれ以外の受験においても、なんなら人生においても、「読解力」「国語力」は必須、ありすぎて困ることはないです。
ですのでお答えとしては一択、「おしゃる通り、国語力は必要です」ということになります。
そのうえで、年長さんで公文のF(小6のレベルとされているところですね。小数・分数を含めた四則混合計算まで終わっている、逆算も少し出てくる、というレベルです。)まで終わっているとのこと。
充分、高進度だと思います。
現在文章題に苦戦することがあるようですが、年長さんですのでどのレベルの文章題に取り組んでいるのかにもよりますが、たとえば公文でFまで進んでいるのに『きらめき算数』の入学準備編あたりに苦戦しているようですと、ちょっとその高進度にも疑問が残ってしまいます。
数の本質、計算の意味、を理解して進んでいれば、Fまで到達していれば年齢相応の文章題(入学準備編と言われるもののうち、塾教材レベル)には苦戦しないはずであり、そうあってほしいです。もちろん、公文がFレベルだから小6の文章題が解けるなどということはないので、「小6の問題が解けなくて・・・」という話ではないはずですが、読解力があまりないようだとすると、高進度の計算もやらなくなるとすぐ忘れてしまう可能性もありますし、小学生になったときに学校の算数レベルでも計算以外でつまづく、ということもありますので現状がわかりませんが、慎重に見てあげたほうがいいと思います。
公文がFやGまで到達しているのに、低学年の中学受験塾の模試で惨敗する子や新小4のスタートを意気揚々と切ろうとして、惨敗する子はとても多いです。
なのでよくある話なのです。
ご質問者のお子さんがそうかはわかりませんのであくまで例えば、ですが、計算を数字でただ追っているだけ、暗記して公文で作業として進んでしまうと、とくに1年生くらいまでに多いのが、分数が終わったあとに三桁×三桁の掛け算とか、三桁÷2桁の割り算をやろうとしたら筆算すら忘れてしまっている、、、などの事態がおこります。
数を量として捉える、ということを意識していくことが公文では厳しいので保護者のサポートが必要です。111という数字のひとつひとつの違いを実感させたほうがいいです。(この点、モンテッソーリ教育では幼児期に数を量として体感させるので、1000の大きさ、100との違い、を理解しやすくなっています。)
以前の記事でも書きましたが、公文は計算力を鍛えるツールであって、文章題を解くための訓練には基本的になりません。目的が違うのでそれは公文が悪いわけではないのです。創始者の公文公さんは、「わが子が高校数学を楽々と解くために」というところをゴールに逆算でメソッドを編み出したので、中学受験の文章題とは目指すところが違うのです。
ただ、目的が高校数学なので、やっておくと中高一貫校に入ったあと、(ちゃんと思い出すor2月以降再入会して続けるなら)公文のG以降はとても役に立ちます。
中学受験をする小学生からみても、私個人の意見ではありますがGの正負の数の概念が理解できていると、式の移行が出来るので中学受験で問題を解くときに「考え方」として使えるときがあります。決して、方程式を使うということではなくて左辺と右辺がイコールになる、という概念、意識がついているほうが数の問題などにおいて思考がスムーズな気がする、というだけです。(Hの因数分解も余裕があれば。。。。)
方程式は中学受験の問題においては「悪手」となるので使わせません。何が悪手かって、あんなものをつるかめ算だ、食塩水だ、速さだ、に使っていたら遅くて遅くて話にならないからです。私は高校受験予定の公立の中学生の数学を担当することも稀にあるのですが、中受の勉強を全くしていない中学生の方程式って、本当に信じられないくらい回り道です。(まあ立式することに中学生は意味があるのですが、つい、見ただけで同じ問題を解いてしまう小学生も知っているので、その差に歴然とすることがあるのです。![]() )偏差値60以上の学校においてはとくに、方程式で立式なんてしていたら時間がなくなる問題ばかりだし、難しいものは不定方程式になるものもわざと入っているので、方程式は使いません。
)偏差値60以上の学校においてはとくに、方程式で立式なんてしていたら時間がなくなる問題ばかりだし、難しいものは不定方程式になるものもわざと入っているので、方程式は使いません。
6年生になって算数の偏差値が60以上ある子は、簡単なつるかめなどは「見ただけ」で答えを出してしまうので![]() 、方程式は意味がないのです。
、方程式は意味がないのです。
が、先ほどあげた理由で私は「やっておく」ことは余裕があればお勧めしています。
一応、娘もGかHくらいまでは続けようかなと思っています。(現在Fが終わりそう)
公文の国語をやっていらっしゃるかはわかりませんが、何かしらの国語の対策をしたほうがいいと思います。
または、算数の文章読解力を上げたいならその名の通りの
サイパーのどっかい算がおすすめです。
最初の2つが小1レベル。最後のが四則混合が出来る子向けなので公文でFまで進んでいたら、最後の問題集も取り組んでみていいと思います。もしこれが難しそうでしたら、戻ってたしざんひきざん範囲のほうからやってみる。という感じがいいでしょう。
他には変わり種としては宮本算数シリーズも読解力を鍛えられるものがあります。
この辺を与えてみて、どれくらい自力で理解できるかを見ると、低学年や幼児さんの場合の力が見えてくると思います。
『きらめき算数』の入学準備編も目安になります。
公文でFまで進んているなら、この辺がなるべく1人で理解できるように力を揃えてあげたいところです。
以上が目安ですが、あくまで中学受験を見据えるならば、計算だけに偏らず算数ではこんな力も同時につけていけるといいですね、という話です。
国語力の鍛え方は、読書は王道ですし、読解力が無いなと思うお子さんほど市販の優しいワークから始めたほうがいいです。ただいきなり難しいものは避けたほうがいいです。このあたりの記事も参考にしてほしいのですが、以下では比較的先取りしたい方向けなので
もっと、基礎からやり直させたい!という方や始めたいという方には、国語もサイパーがいいんですよ。
このあたりがおすすめです。公文の国語をやるより、だいぶ安く、ピンポイントでできます。
公文の高進度と算数の文章題について、対策を書いてみました。
タブレット学習については、次回以降とさせてください。
お読みくださりありがとうございました。