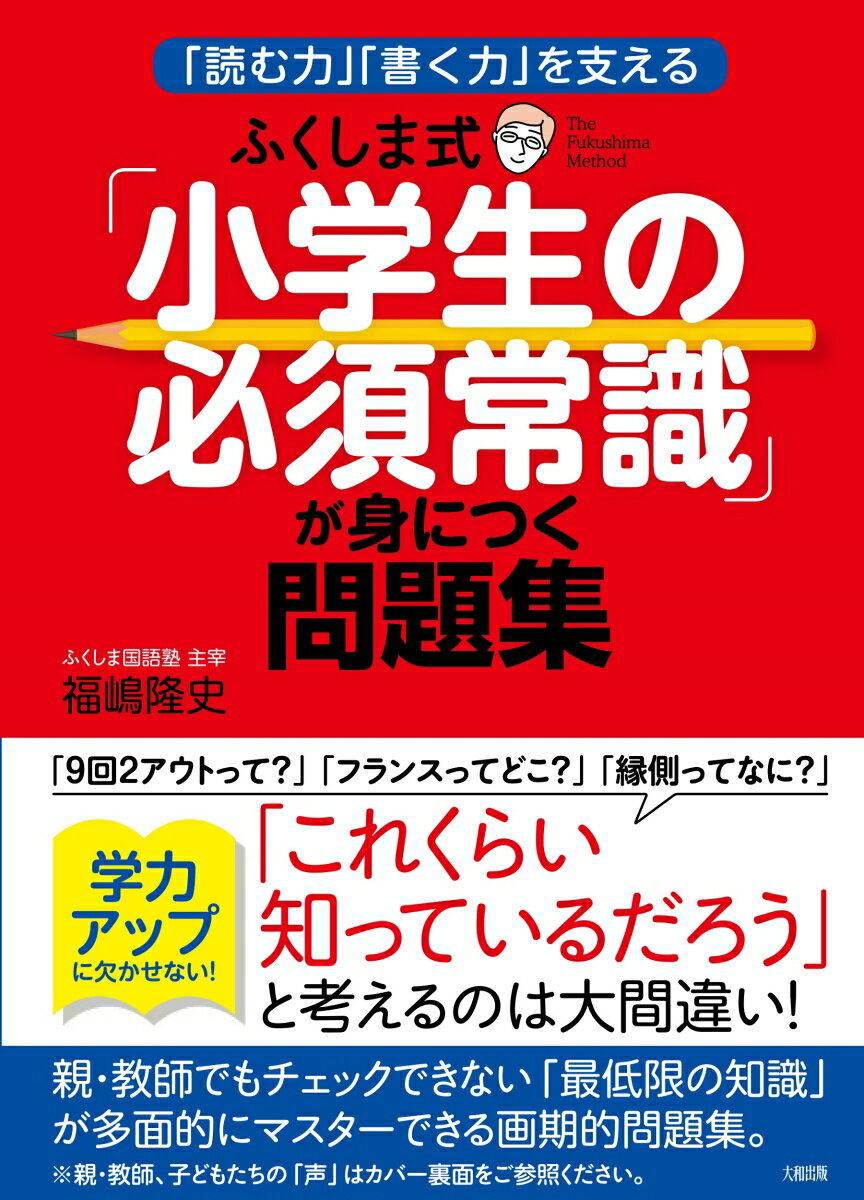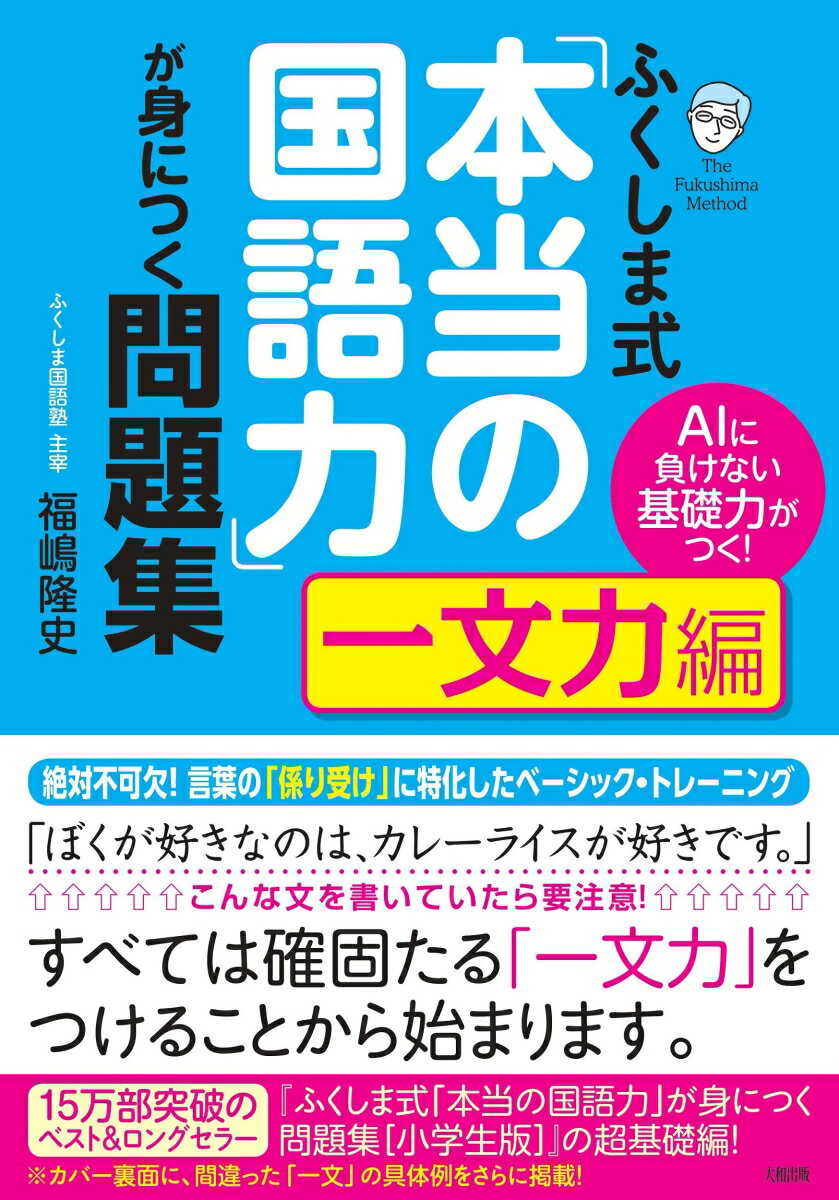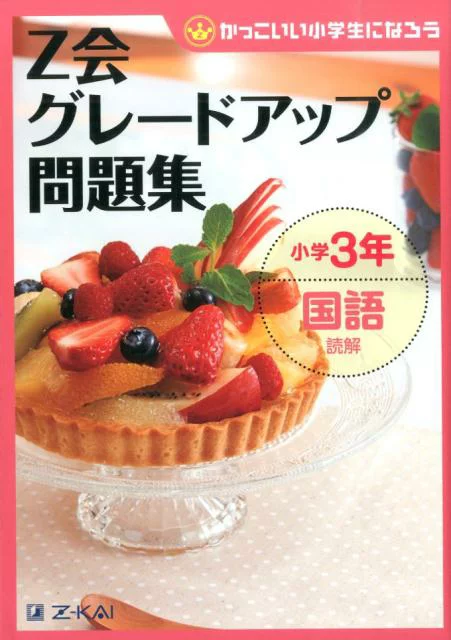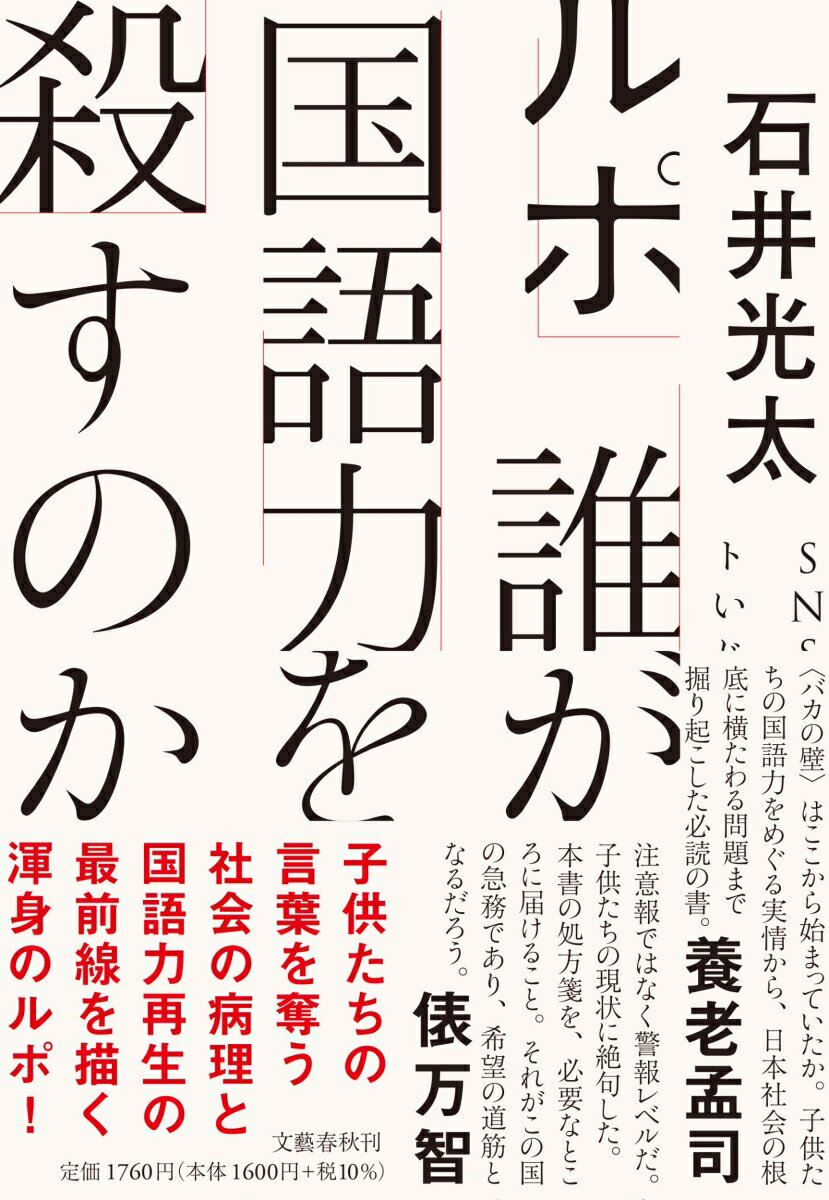いつもお読みくださりありがとうございます。
先日、コメントを頂きましたので、その返信も兼ねてこのようなテーマで書いていきたいと思います。
頂いたコメントです↓勝手に使用してしまって、すみません。
はじめまして。いつも拝読させていただいております。
小3の娘の記述力について伺いたいです。
6月の日能研全国テスト・国語の記述問題で、
・あなたがチャレンジしたいことと、その理由
・チャレンジする上で、どのような難しさや邪魔するものがあるか
・難しさや邪魔するものをどのように解決するか
という問題が出ました。
それに対する娘の解答が「難しさや邪魔されたら、一回れいせいになってもう一どやってみたり「できない!」となってしまったら、つぎの日にもう一どやってみたりして、「できない!」と思っても「やってみたらできるかも!」と思いながらやればいいと思います。」というものでした💦
そもそも提示された3つのポイントについて書くべきところを、このうちの1つを選んで書けばいいと思っ
ていた時点でアウトなのですが、句点がなく長文な上、内容も何が言いたいのか分かりづらく、親としてはがっかりな解答でした。
公立中高一貫を目指しているため、記述力は絶対必要だと思うのですが、おすすめのドリル等ご教示いただけましたら幸いです。
(通塾はしておらず自宅学習のみです)
加えて、読み聞かせはずっとされているとのことでした。
まずは、この日能研の全国テストですが、記述が低学年からきっちりあります。それも、早稲アカのような「読解問題」ではなくて、「自分の考えや意見」を書かせるものとなっています。配点も31点とか![]() あるので、ここを空欄にしたら好成績は狙えません。また、まだ受験基礎を勉強していないお子さんでも、逆に作文のセンスがあると簡単にここで満点の31点取れてしまいます。
あるので、ここを空欄にしたら好成績は狙えません。また、まだ受験基礎を勉強していないお子さんでも、逆に作文のセンスがあると簡単にここで満点の31点取れてしまいます。
さて、もし私がこのお子さんのこのテストの解説指導をするとしたら、と想定して記述の問題点をまず挙げてみますね。
親御さんでも十分できるはずですので、とにかく親は冷静に、自分が塾講師になったと思って(笑)目の前の子は他人だと思って(笑)、一行ずつ、たどっていきましょう。
3年生ですから、主語、述語という概念は入っていますよね?
大前提として、「日本語で文章を書くときは、基本的に主語と述語を入れます。」と説明し、例外もあることもサラっと付け加えておきます。強調するのはあくまで、主語と述語が大事ということ。
そして本人に自分の記述を音読させます。まずは止めずに読ませる。次にもう一度。スタートの「難しさや邪魔されたら」と本人が読んだところで、「誰が?」と聞いて答えさせます。そして、「主語、入ってなかったね。これじゃ読んだ人は誰のことかわからないよ」と教える。
次は「誰に邪魔されるって?」とまた答えさせる。「で、何を邪魔されたときの話をしてるの?」と聞く。まずはそこまでで、一行話を組み立てさせ、書かせます。
これを繰り返していくことで要素の入った記述を完成させて、本人に読ませ、最初のものとどう違うか考える。この工程は実は6年生の添削でも同じですが、3年生にだってできます。内容は易しいので、親が「え?何を書きたいのこの子![]() 」と思う気持ちをぐっと抑えて「通じる話」に組み立て直してあげるのです。
」と思う気持ちをぐっと抑えて「通じる話」に組み立て直してあげるのです。
もちろん、時間も忍耐も必要です。ただ、これを繰り返すことでしか正直「書く力」は伸びて行かないと思います。
回数、必要です。テストの記述というのはよくできた問題なので、良いチャンスだと思って必ず直しをします。(親子でこの過程がだんだん辛くなるので、外注ということになる場合もあります。)
また、3年生以上ならば「要素」についても解説してあげるといいと思います。
この問題ならば、「書かないといけないことって何個あるの?」という問いかけですね。
その問いかけだけで、自分の間違いにハッと気づくこともあれば、そういわれても一体何のことやら、という子もいると思いますが、わかっていなければ嚙み砕いて説明するのみです。
次に、「自分」のことを聞かれているんだよ?ということを自覚させる。
この「私」にテーマを引き入れて、自分のテリトリーに引き込んで書いていく。これは大学受験の小論文まで使える「方法」だと思います。抽象的な概念だったりしても、それを本当に理解できていれば身近な自分の話に例えたり、経験と照らし合わせての感想が言えたりするわけです。これができる小学生は、作文力が高いですし、これからも国語は得意になっていくと思います。「自分に引き込む」これ、超重要なポイントです。とくに公立中高一貫で作文があるのなら、この力は必須でしょう。
そして、もし、「そんなチャレンジしたいことなんてないよー」という返答だった場合。
「ないわけないでしょ!」と言いたくなる気持ちをぐっと抑えて(笑)、「えー、この間の〇〇とか、頑張ってたんじゃないの?」とか子どもがまずは「あ!そうだね」とすぐ納得しそうなものの例を挙げる。それで文章を書かせます。次に、子どもが絶対思いつかなさそうな、親目線からしたら頑張っていたチャレンジを教えてあげます。子どもって自分のこともすぐ忘れたりしますし、大人とは物の捉え方が違うので、大人側が「これもテーマに合うじゃん!」って思うようなことも、気づかなかったりします。
例えば、チャレンジとして誰でもわかりやすいのは「スイミングで頑張った」とか「ピアノのコンクールの話」とか。一方で子どもがふと言った、「今度ぼくは○○係になりたいんだよねー」とか「今度私は応援団になりたいんだー」「リレーの選手になてみたいなー」とか。本人も忘れているような、大人から見たらテーマと合っていそうなことを挙げて思い出させてあげるのです。それが一番できるのって、塾講師でもなくて間近で見ている保護者だと思います。
私の場合は自分の子にはもちろんそうしていますし、(ただし、冷静に、は出来ていません。![]() 怒り口調
怒り口調![]() も多々。。。)他のお子さんに指導するときも、自分の子の経験を頭の中でフル回転させて、何かヒントになることを提示します。
も多々。。。)他のお子さんに指導するときも、自分の子の経験を頭の中でフル回転させて、何かヒントになることを提示します。
地道ですが、そうやっていくと「なんだ、記述のネタってそういうことでもいいんだ」と子どもはわかっていきます。
で、じゃあそれをどうやって鍛えていくのか、ですよね。
私は低学年ならば、なんなら幼児期からやってほしいことが、「日記を書く」です。
しかも、できるだけ「毎日」書く。幼児は絵日記でいいです。
短くてもいいので、書かせていくとネタを見つけるのもうまくなります。
ただし、うちの息子の場合は本当に「ねー次、なんて書く?」「ママ考えて~」![]() という調子でしたので、私もキレてました(笑)で、毎日キレてたら大変なので、うちの息子のように書きたくない子には「長期休みのときだけは義務として毎日書く!!」という課題にしていました。それと週末も書かせていましたね。まあ、息子の作文力は全然なのですが、それでも書いていなかったらもっと酷かったとは思います。
という調子でしたので、私もキレてました(笑)で、毎日キレてたら大変なので、うちの息子のように書きたくない子には「長期休みのときだけは義務として毎日書く!!」という課題にしていました。それと週末も書かせていましたね。まあ、息子の作文力は全然なのですが、それでも書いていなかったらもっと酷かったとは思います。
日記というのは本来人に見せるためのものではないのですが、この場合は学校や親へ提出するという前提で書いてもらいます。小学校の担任の先生が協力的ならば、毎日書いて提出してもいいか、感想を書いてもらえるか、聞いてみてください。先生に読んでもらえると思うと頑張って書けるお子さんもいますし、「先生が読むんだ」という意識で書くと、めちゃくちゃな文章ではおかしいということにだんだん気づくと思います。良い先生だと、丁寧に添削もしてくれるはずです。
提出するとはいえ、「子どもらしさ」は消さないであげてください。子どもが話してくる今日あったこんなこと、あんなこと、をそのままの表現で書かせます。なんなら面白ワードは親がメモしてあげておくといいくらいです。子ども自身は忘れてしまったりするので。
そのうち、最低限の構文力は身についてきます。
娘は幼児のころから「書きたい!」子だったので、絵日記から始まって、基本的に毎日日記を書いています。
日記の効用や詳細については、別にまた記事にしたいと思います。
4年生、早ければ3年生くらいからは様々な問題集で鍛えることもできます。
そのときでも必須は「語彙力」です。文章って読むのも書くのも語彙力無しにはできないので、語彙の勉強だけはあの手この手でしていったほうがいいです。
まんがでもいいですし、私は
ふくしま式の必須常識もぜひやっておいてほしい問題集です。
2年生以下には途中から難しくなるのでお勧めではないのですが、3年生以上なら休み休みでもいいので、これが「書く力」を直接鍛える問題集としては今一番の推し。こちら↓一日1Pでいいです。
↑「ぼくが好きなのは、カレーライスが好きです。」この文章、めちゃくちゃ刺さりました(笑)。本当に多いです。こういう文章を書く子。息子もコッチ系。。。![]() それで中3の現在もふくしま式の要約力をつける問題集などをやらせてますし、テストなどではなんとかなっています。読書感想文とかはやる気もないし、酷いですけど。
それで中3の現在もふくしま式の要約力をつける問題集などをやらせてますし、テストなどではなんとかなっています。読書感想文とかはやる気もないし、酷いですけど。
あとは3年生なら、王道としてZ会の国語問題集と、四谷のはなまるリトルもいいですよ。
読解も記述もバランスよく、少し難易度高めの問題で鍛えることができます。
記述がいまいちだな、と思う場合、「読解力」も足りていない可能性があります。なぜなら「書く」ためには相手の、つまり設問の「意図」が「読解」できないと、的を射た解答が書けないからです。
今回のお子さんの場合も、記述力を鍛えつつも、自宅学習なら読解力も上げていくようなバランスのよい取り組みが効果的かなと思います。
偏差値が高い場合、よくできる場合の問題集って、いくらでもあるのですが、大多数の子には難しすぎることもあるので、自宅学習の場合はとくに、わが子にちょうどいい、少し難しいとするレベルの問題集を与えていくことが成績アップの鍵かなと思います。
今回のご家庭では小さいころから現在まで読み聞かせをされているとのこと、効果、絶対にあると思います!!少なくとも読み聞かせの嫌いな子っていませんし、読んでもらった本は絶対に子どもの糧になっています。読書への移行もしやすいです。見た目とキャラ的に、一切本なんて読まなさそうな息子が本を読むのが好きなのは、私の読み聞かせのおかげ、とひそかに思っています(笑)。国語力にも絶対にプラスになりますよ!
読み聞かせについての記事も書きたいなと思いました。
番外編として
ちょっとテーマからズレてしまいますが、国語力についての面白いと思った本をご紹介します。
中受に向かっていると、どうしても点数化された国語力が気になりますが、なんで国語力って必要なんだっけ、という原点に帰れる本です。
有名中学校の取り組みなども出てきますので、よかったら読んでみてください。面白いので一気に読めると思います。
今回ご質問くださった方へ、いろいろと話が飛んでしまってわかりにくかったかもしれません。
参考にしていただける部分が少しだけでもあればと思います。
今日もお読みくださりありがとうございました。