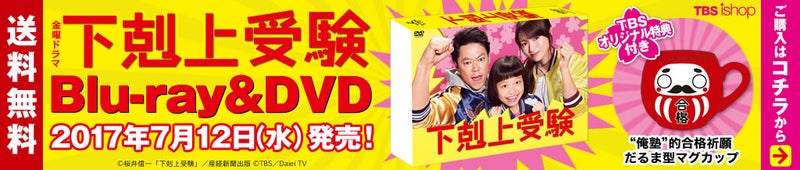【お知らせ】
ハウスクエア横浜で講演会をいたします。ご興味のある方は下記のバナーをご覧ください。
お名前:M,K
件名:低学年の対策
本文:小学校1年生の娘を持つ、M,Kと申します。
ブロク、本、ドラマとすべて見させていただいております。
桜井さんの経験談はとても参考になり、将来来るであろう受験にと思いと対策を考えております。
そこで、少々先の早い話ですが、入塾である3年生2月含めそれ以降の受験勉強において、親としては良いスタートを切るとともに、できることは先にやっておいて、少しでも有利に運びたいという思いがあります。
桜井さんから見まして、小学校の入塾前にやっておくほうが良いことはありますでしょうか。
以前のブログで、6年生の漢字をやっておくと良いかも。という内容を拝見した記憶はありますが、それ以外でも、仮に上げるとすると、これをやっておくと良いということがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
M,K様、はじめまして。
低学年のお子さんをお持ちの方々から同様のご相談をたくさん頂戴しております。
なかには就学前という方までいて、その意気込みにびっくりです。
真剣に相談しているのにふざけるなと言われそうですが、まずは「祈願」だと思います。
小学校1年生の学力なんて、余程どちらかでない限り判断しづらいと思うからです。
親はなかなか客観的に見れないでしょう。
ちょっとした仕草にまで「おっ、この子は違う」と思ってしまうのは私なんかでも同じでした。
最近は塾も低学年からありますね。少子化に伴う青田買いというやつでしょうか。
そんな塾の先生でも、余程どちらか寄りの子でない限り、低学年の子の能力はなかなか判断できないと思うのです。判断できたとしてもそんなのアテにならない。
結局は勝負の学年までわが子の行方がわからない。
もうこれは祈願しかないという私の回答が、あながち冗談とも言えないとは思いませんか。
出版記念イベントで、同様のご質問が会場からあがったのです。
私もまだ受験勉強から1年半か2年しか経っていなかったものですから、一番「これ苦労したなあ」と思ったものを答えたのです。
それが漢字でした。
漢字って侮れないのです。5問ほど出題される学校が多いですが、2問落とすと結構痛いのです。
ところがその対策となると、飛び込み訪問するセールスマンが町をさまようようなもので、やってもやっても結果につながらないのです。確率が悪すぎるのです。
難関中学というのは、どういうわけか難しい漢字はあまり出題されません。
難関を狙うなら小学校の漢字ドリルで十分。
小学校のドリルをよく見ると、新出漢字の下か横かに、その漢字を使った熟語が4つほど出ていると思います。
その熟語の意味、「わからないのはど~れ?」と蛍光ペンで塗らせてみると、「なんだよ!ほとんどわかんないまま覚えていたのかよ!」とびっくりというか焦ったというか。
うちの子は、学校の漢字テストはまあまあ良かったのです。
4年生頃になると、母親と頑張ってテスト対策していましたから、まあ出来ないこともなかったのです。
まさか意味がわかってないなんて考えもしませんでした。
その悩みを解決してくれるのが漢検。
漢検をやると中学受験範囲の熟語や意味は網羅できるのではないでしょうか。
漢字5問の得点と文章を読む上での語彙を想像する能力の2つが同時に解決しそうです。
もう一度受験する機会があるなら漢検は必ずやりますね。私も一緒に頑張ると思います。
私の知っている範囲を見渡しますと、順当に難関中学に辿り着いているお子さんは、やはり新小4スタートが多いようです。
そして、意外なのはそれまで準備らしきことはやっていないという点です。
幼児教育的なことや、難しい問題集を自宅でやっていたというお子さんは私の知る範囲ではいないのです。
そりゃ範囲を広げればいるでしょう。
しかし少数派のような気がします。
だからといって低学年は放置しているということではないようなのです。
学び方の違いですね。
私も一緒に勉強して痛感しましたが、小学校で同じことを習っていても、深め方というか視点が違うんだと思います。
例えば、足し算。
2+9=11
4+8=12
ひたすら計算ドリルをやることが中学受験にとって重要な能力ではなく、合わせる力が大切で、わが家は勉強のスタート時にかなり練習をしました。
例を挙げます。
「8!」と私が言うと、子どもが「2!」と答える。
「88!」と私が言うと「12!」と答える。
これ、22と答えたりするんです。
数秒考えたら意味がないのです。即答できるかがポイント。
「878!」と言うと、もうモゴモゴでした。
計算練習する前にこれを徹底してやったのです。
これが後になって利いてきたと私は思っています。
大人は買い物をするので、合わせる力は子どもより長けている。
そんな大人の当たり前を放置しない親から優秀な子が育っているんだと思います。
先取りせずにその学年で学ぶべきことをじっくり深める。
何が必要かをちゃんと考えているんだと思います。そこがすごい。
だから兄弟姉妹を次々に涼しい顔して難関に入れてくる。
そして本格的なスタートのときまでに、勉強嫌いになってしまわないように注意する。
優秀な子はテストで競うことをゲーム感覚でやっていますから、勉強を苦行と思っていないところが共通点だと思います。それは入学後でも大事なことで、苦行ならさらに6年間は続きませんよね。
それと、静かに暮らしている家が多いみたいですね。
うちはテンション高めなので、お友達の家に行くと戸惑うみたいです。
これは学力とは関係なく育ちの違いかもしれませんが。
「あっ、それはうちもやってたあ」というのが1つだけあります。
夏休みの自由研究は本気でやっていましたね。
これは共通点というほどではないですが、親子の共同作業に慣れている子がいるということでしょう。
他にも色々あるのでしょうけれど、パッと思いつくのはそんなところでしょうか。
周りを見ていて、うまく育てるなあとつくづく思います。
子どもの頭を良くする系の本って、割と逆のことを書いていることが多いんですよね。
もしかすると、子どもを難関中学にラクに入れてくるお母さんたちは、そういう系の本とは無縁かもしれませんよ。
今日もどこかで涼しい顔して「楽勝~」なんて言っているかもしれません。
ぐぐぐ、ぐやじい……。
2017.5.23
桜井信一