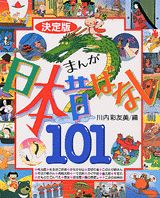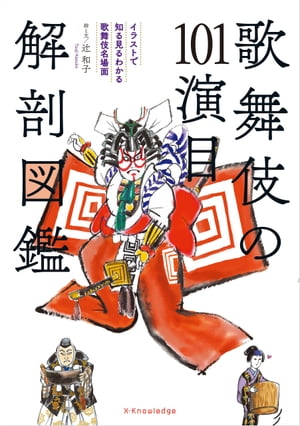豊竹咲寿太夫
オフィシャルサイト
club.cotobuki
HOME
団子売
文楽の演目は
時代物
世話物
景事
の三つに大きく分けることができます。
団子売はこの内の景事で、お芝居というよりは舞踊の要素が大きい演目です。
なので、ストーリーがある演目ではなく、テーマに沿った踊りを楽しむ演目です。
団子売は清元の「玉兎」という演目のリメイク作品です。
玉兎は「かちかち山」を取り扱っていて、劇中で「景勝団子」が掛け言葉のような形で使われます。
景勝団子とは、上杉景勝の生家の鉾先と形が似ていることからそう呼ばれている団子です。
玉兎をリメイクした団子売では、団子を売り歩いている夫婦が臼と杵で景勝団子を作ります。
奥さんがお臼さん、旦那さんが杵造さん。
分かりやすいネーミングです。
幕が開くと、軽快な様子でお臼と杵造が餅つきセットを持って登場します。
あちこちで目の前で餅を作りながら団子を売る夫婦の団子売りで、客席に向かってその様子を踊りで表現します。
「団子売」は露店で団子を売り歩く夫婦の歌詞と踊りで子孫繁栄を祝いながら演じます。
臼と杵でつくという、少し色っぽい表現から子孫繁栄というテーマに繋がります。
本文と解説
今度、今度仕出しじゃなけんけれど、雪か花かの上白米を、痴話と手管でさらせて挽いて、情けで捏ねてしっぽりと。
この度、新しい試みという訳ではありませんが、雪か花かという上等な白米を色っぽいお話と色っぽい技術をもってさらせて挽いて、情で捏ねてしっぽりと団子をつくります。
「さあさあ、これはこの度大評判」
「ご贔屓高い飛び団子」
「そんならお臼」
「杵造さん」
「さらばこれから、始まり始まり」
「飛び団子」
「さあさあ、これはこの度大評判」
「人気の飛び団子」
「そんならお臼」
「杵造さん」
「それではこれから始まり始まり」
「飛び団子の始まり」
やれもさうややれやれさてな。
臼と杵とは夫婦でござる。
やれもさうややれやれさてな。
夜がな夜ひと夜、おゝやれやれな。
父んが上から月夜はそこだよ。
やれこりゃよい子の団子ができたぞ。
おゝやれ、やれさ。
あれはさて、これはさて、どっこいさてな。
よいと、よいと、よいと、よいと、よいとなとな。
これはいさのよい夫婦。臼と杵との仲も良や。
やれもさうややれやれさてな。
臼と杵は夫婦だよ。
やれもさうややれやれさてな。
夜、夜、ひと夜。
旦那さんが上からつく月夜はそこだよ。
これはよい子ができた。団子ができたよ。
おおやれやれさ。
あれはさて、これはさて、どっこいさてな。
よいと、よいと、よいと、よいと、よいとなとな。
これは仲の良い夫婦だ。臼と杵の仲は良い。
『お月様さえ、嫁入りをなさる。やっときなさろせ』
とこせ、とこせ
『年はおいくつえ。十三、七つえ』
『ほんにえ、お若いあの子を産んで、やっときなさろせ』
とこせ、とこせ
『誰に抱かせましょうぞえ。おまんに抱かそゞえ』
見ても美味そな品物め
『お月様さえ嫁入りをなさる。やっときなさろせ』
とこせ、とこせ
『年はおいくつだい。十三、七つえ』
(十三夜の七つ時、4時頃、に出たばかりの月を意味するという説があります)
『ほんに、お若いあの子を産んで。やっときなさろせ』
とこせ、とこせ
『誰に抱かせましょう。お万に抱かせよう』
見るから美味しそうな品物だ。
そうだよ、高砂尾上の爺様と婆様が箒を手に持ち、熊手を担いで目籠を背負いそろ、小松の枯葉をさらりと集めて、戻ろとしたれば上の枝には鶴の巣籠り。
下の小池にゃ女亀と男亀が空を眺めて、このや松はな、めでたい松にて高砂文句もここらで止めましょ。
尾上。
かくては尽きじと夫婦連れ。
かしこを指して。
「高砂尾上の松」に登場する老夫婦が箒を手に持って、熊手を担いで、目籠を背負い、小松の枯葉をさらりと集めて、戻ろうとしたところ、上の枝には鶴が巣篭もりをして卵をあたためていたそうだ。
下の小池では女亀と男亀が空を眺めていた。
この松はめでたい松だ、と高砂尾上のおめでたい歌もこのあたりでお仕舞いにさせていただいて、また別のところへ参ります。
そうして団子売りの夫婦は連れ立って次の所へと向かっていったのでした。

「飛び団子」というのは、団子を一口サイズに丸めて、お客の口へ飛ばして放り込むという曲芸のような曲売りのことで、実際にそうした売り方が流行ったのだそう。
曲調は非常に楽しげな明るいものになっていて、清元の玉兎から義太夫にリメイクした、軽やかな演目になっています。
![]()

とよたけ・さきじゅだゆう:人形浄瑠璃文楽
太夫
国立文楽劇場・国立劇場での隔月2週間から3週間の文楽
公演に主に出演。
その他、公演・イラスト(書籍掲載)・筆文字(書籍タイトルなど)・雑誌ゲスト・エッセイ連載など
オリジナルLINEスタンプ販売中
豊竹咲寿太夫
オフィシャルサイト
club.cotobuki
HOME