

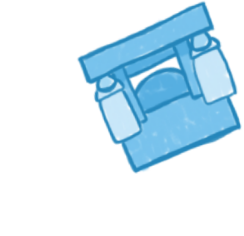 長門太夫という師。
長門太夫という師。人形浄瑠璃
文楽、つまり人形浄瑠璃の太夫には各時代時代にもちろん名人と呼ばれる師匠方がいらっしゃって、逸話が数多く残されています。
今日は三代目竹本
明治の師で、当時はお寺の境内で芝居をしたり、道頓堀で芝居をしたり、と「文楽」になりつつある時代でありました。
長門太夫師はとても腹の強い師で、たとえば道頓堀の芝居小屋で語ると、川向こうの宗右衛門町一帯にまでその声が響き渡るという方でした。
明治ともなると文明も発達してきているので、おそらく義太夫師の時代よりは街中の騒音が増しているだろうと思いますが、そのような話がのこっているくらいなので、よほど腹の強い方だったのだと思います。
そんな腹の強さを物語るエピソードが残っています。
菅原伝授手習鑑「車曳きの段」
https://amzn.to/2ZFjCgF ストーリーで楽しむ文楽・歌舞伎 菅原伝授手習鑑 金原瑞人・佐竹美穂 | ||||
この段ではなんといっても時平の大笑いがひとつの見せ場でございます。
現在では「ヤア命冥加な蛆虫めら」で大笑いになります。
しかし、古い型では時平が登場するシーン「現われ出でたる時平の大臣」で大笑いになったそうです。
長門太夫師のこの大笑いになると、その笑いがとてつもなく長く続いたそうで、それが評判になったそうです。
博労町稲荷境内での稲荷座で上演した時も評判となり、この大笑いの時になると自然と人が集まるようになったのだとか。
そして、いつからとなく、長門師の大笑いになると、子供達をはじめ集まった人たちが大笑いに合わせて神社の廊下をぐるぐると走り始めたのだそうです。
30周、35周、はては37周廻る日もあったのだとか。
この逸話は決して大げさな誇張ではないそうで、実際にそれほど腹が強く、ただただ長いだけの大笑いではなかったという逸話だそうです。
この逸話は、上演中の音が漏れ聞こえていたからこそ成り立った逸話で、現代のように完璧な防音の劇場ではありえないことです。
こうしてみると、戦前は自然と義太夫を始め三味線音楽が耳にはいる環境だったのだなということがよく分かります。
現代は静寂に敏感すぎるのかもしれません。
咲寿太夫でございました。
https://www.ntj.jac.go.jp/sp/
日本芸術文化振興会サイト
国立劇場・国立文楽劇場
文楽公演はこちら!
https://www.bunraku.or.jp/index.html
500で文楽を観られるワンコイン文楽や
文楽地方公演など。





