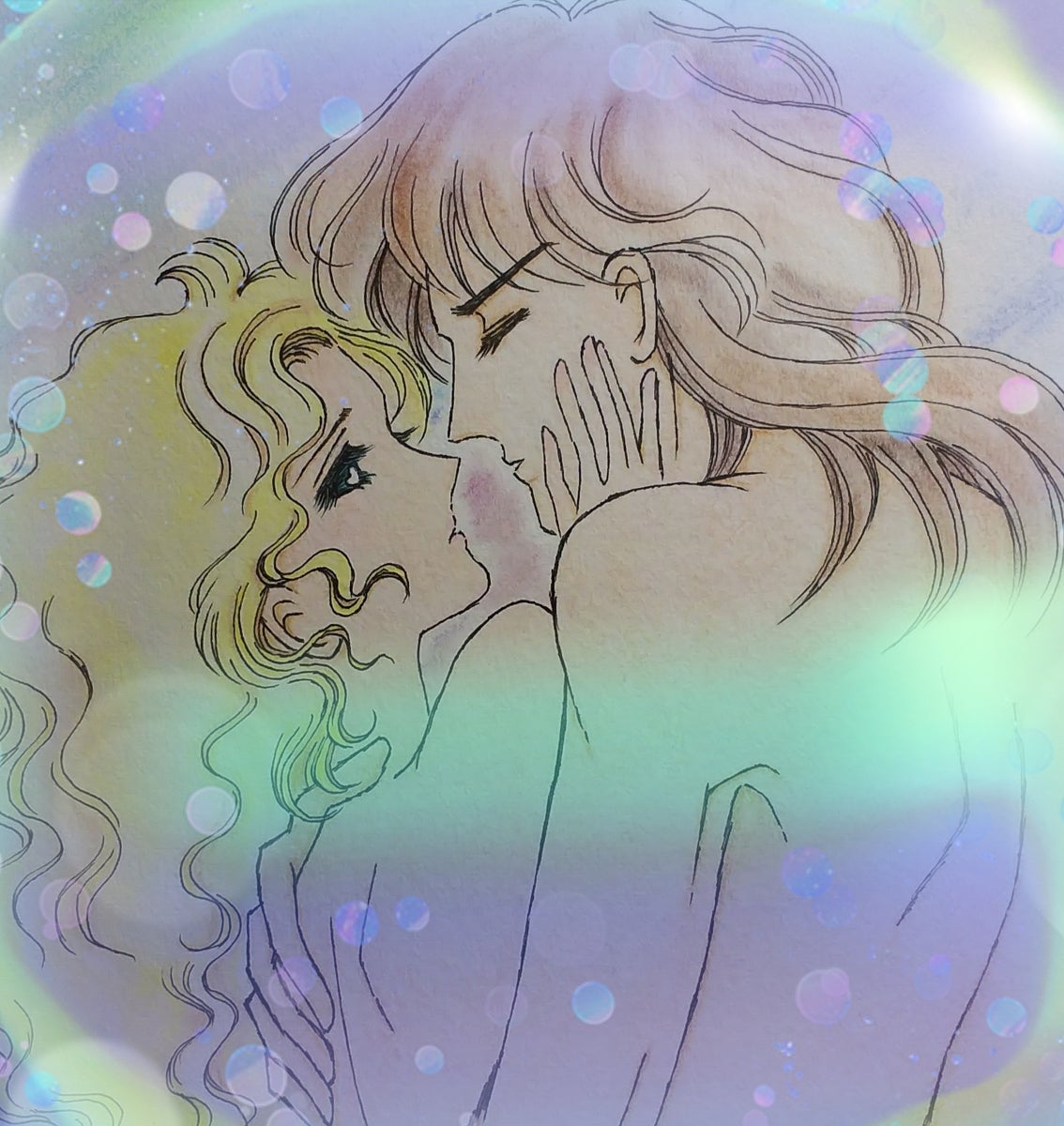![]() アメンバー限定話がちょいちょい挟まっておりますが、ギリOKだろう(多分)。
アメンバー限定話がちょいちょい挟まっておりますが、ギリOKだろう(多分)。
Schmetterling(蝶)
愛の挨拶ーLiebesgrussー
上弦の月が、西の彼方に沈む───
七月の聖ゼバスチアンの寮は、殆ど人はいなかった。
夏休みに入り、生徒は自宅に帰っていく。残っているのは数人だけだろう。
ひとつの部屋の扉が開いて、また直ぐに閉められた。
僅かに開いた窓の隙間が、カーテンを揺らしている。
夜更けにはまだ早い。薄ぼんやりとしたグレィの空に白い星が瞬いている。
荷出しの済んだクラウスの部屋は、ソファやベッドなどの家具以外はすっきりと片付いていた。
「もう、何も無いんだね」
部屋の中を見渡して、ユリウスはぽつりと呟く。
「ああ、後は、身ひとつで出るだけだ」
クラウスも懐かしげに、少し汚れた壁やベッドの傷に目をやった。
「そう……」
造り付けのクローゼットに掛かっているハンガーが、寂しげに揺れている。
ユリウスは、窓に近づいて、空を見上げ、星を数えた。
ひとつ、ふたつ……みっつ……
クラウスは、窓辺に佇む恋人の姿に見惚れ、無言で立ち竦んでいた。
星明かりに微かに光る金糸の髪が、そのまま天に昇っていくようで、一緒に彼女も連れて行ってしまうのではないか、と怖れた。
行くな……と手を伸ばしかけた刹那、ユリウスがこちらを向いた。
そろそろと彼女が歩み寄る。腕の中へ吸い込まれるように……。
クラウスは、ユリウスの細い手を取ると、そのままベッドに座らせる。
白いワンピースが、ふわりとシーツに広がった。
「その服で、この部屋に来た日のこと憶えてるか?」
彼女の隣に腰を下ろしながら、クラウスは訊いた。
「え? もちろん……」
「二人して池に落ちて、びしょ濡れになって──」
「ふふっ……、大変だったよね」
「それが、ぴったりと張り付いて──」
長い指が白いワンピースの襟元をつまむ。
「え……?」
「お前の躰のラインが露わになって……」
何を言いだすのかと、ユリウスは仰天し、
「そっ、そんなこと思い出さなくていいっ!」
と思わず身を乗りだす。クラウスは、まあまあまあと押し止めた。
「じゃあさ、クリスマスの夜のことは?」
一人思い出し笑うクラウス。
「今度は……何?」
「お前、一人で酔っ払ってさ、大変だったよなぁ」
何だか暴露反省会みたいになってきて、ユリウスは、みるみる身の置き所が無くなってくる。
「もぉっ! どうして今頃になって、そんな意地悪言うの?」
「俺さ、この部屋でどれだけ、お前に振り回されたと思う?」
「い……今更そんなこと言われても……」
「でも、それも今夜で帳消しだ」
急に真面目な顔になって、クラウスはユリウスを見つめた。
「え?」
彼は、ゆっくりとユリウスに顔を近付ける。そして、桃色に艶めく頬にキスを落とす。
「ぁ……」
次に瞼、額、髪に頬擦りしながら耳朶に、再び頬へと唇を滑らせる。
烟るような睫毛が震えながら上を向くと、彼の愛してやまない碧玉の瞳が浮遊する。
もう千回は超えたであろう口づけを、それでもまだ足りないと、翹望するように交わす二人に、止めるものは何もない。
窓よ──
幾百、幾千もの恋人たちを、久遠の空から見下ろし続けてきた
窓よ……
限りない邂逅と別離の道程に、
一条の閃光のごとく重なり合った
若い二人の前途に、
その扉を開けよ……
汝の想い焦がれたエウリディケは……
エウリディケは───
彼の躰が彼女の躰に、溶け入るように合わさった。
漆黒の空に光を放つ七つの星が、零れ落ちる彼女の涙を幾度となく掬い取る。
「ユリウス、愛して…る……」
「嬉しい……。クラウ…ス……」
枕の会話
「ほら、水」
「ありがと……」
半ばぼうっとしながら、ユリウスはグラスに手を伸ばす。
「あっ」
案の定、手が滑った。
「あぶねっ!」
すんでのところで、クラウスがグラスを摑んだ。
「ご、ごめん……。なんか力が入らなくて……」
「しょーがねえなぁ」
ケットから肩だけ出した状態の恋人の隣に、クラウスが潜り込んだ。
「お前は持たなくていいから。ほれ飲め」
彼女の唇にグラスを当てて、少しだけ傾ける。
「ん……」
こくんと、水を飲み込んだ。ふう……、と息をつく。
「もういいのか?」
「うん、……ありがと」
何故だか、躰も心もふわふわしている状態のユリウスだった。
クラウスは、グラスをテーブルランプの傍に置き、彼女の肩を抱き寄せた。
まだほんのりと温かい。
ユリウスは、何となく顔を背けてしまう。
「……びっくりしたか?」
「え!?」
振り返り、クラウスと目が合った瞬間に、ユリウスは上気した。
ほんの数分前、息つく間もなく自分の身に起きた想像を絶する出来事を思い浮かべ、頭から湯気が出そうなほど熱くなり、パニックに陥り、頭の中がぐるぐるぐるぐる思考回路はショート寸前……etc.etc.
──ああぁ……あんなこと……、誰も教えてくれなかった。リ、リーナだって……(当たり前だ)。
「後悔しているのか?」
「え? ま、まさか! してない! してないからねっ」
どうしてこんなに必死になるのか自分でも分からない。
クラウスは「そうか」と呟くと、彼女の躰を強く抱き、
「じゃあ、またしような」
半分戯けて囁いた。
「え? い、今から?」
「ばーか。そうしたいのは山々だけど、次はパリだな。楽しみにしてるよ。ん?」
「な……もぉう!」
摑み掛かろうとした瞬間、ケットがずり落ち、ユリウスは慌てて握り締める。
「こらこら、今夜はもう大人しくしとけ。大事にしなきゃ駄目だ」
「う、うん……。詳しいんだね? クラウス」
「え!? い、いやまあ……、常識だよ(何が?)」
「ふうん……、そうなの?(解ってない)」
「初めてなことばっかで大変だったろ? ゆっくり休めなきゃな」
「ん……」(頭が回らない上に、突っ込む知識も無いので従順)
クラウスがシーツを掛け直し、今度は優しく抱き寄せた。
髪の毛を指に絡ませ弄ぶ。
そして、まだ少し湿った毛先に口づけた。
──気持ちいい……。
彼に躰を預けながら、とろんとしてくるユリウスなのだった。
「俺……、天罰が下るかな?」
「どうして?」
「天使を抱いちまった」
「……ボクは、天使じゃないよ」
「知らないのか? ゼバスの連中は、みんな、お前のことを金髪の天使って呼んでいたんだぜ」
「そんなの、揶揄っていただけだよ」
「俺も口には出さなかっただけで、心の中では思っていたよ。この髪が光に透けて見える度に、背中に羽が生えているんじゃないかと錯覚したもんだ。今日だって、ドナウで今にも飛んでいきそうだった」
「それは……、クラウスにだけ見えたんじゃない?」
「随分と、限定公開の神の使いだな?」
「神の使いはね、そんな簡単に正体は見せないの。特別な人にしか見えないんだよ」
「特別……?」
「心を許した人にだけ見えるの」
「天使に?」
「天使が」
そう言って、彼女は彼を見た。
「ふうん……、だから俺にだけ見えたのか」
「そう。これからも、ずうっと君にだけ見えるの」
「そっか……」
「そうだよ」
ユリウスは、クラウスの胸に顔を埋め、瞳を閉じると、心の中でもう一度呟く。
──そうだよ……。
クラウスもまた彼女の柔らかな髪を撫でながら、心の中で呟いた。
──そうか……。
翌朝/神様の蹴りの後
※『愛の挨拶♡おまけ集』の「ほんっとうにどうでもいいおまけ」の直後の出来事。
「躰……、何ともないか?」
「え……? 大丈夫だけど……」
無意識に答えた後、ユリウスは昨夜のことをありありと思い出した。忽ち、脳内が沸騰した。
「だっ……だいじょぶ。ほんとに……」
クラウスの首に腕を巻きつけた状態で、ユリウスはどうしていいか分からなくなった。
「なら良かった」
クラウスは内側の感情を押し隠し、平静を装った。
だが。
──どうしてこんなに甘い匂いがするのだろう……。
「……ユリウス」
「え?」
ユリウスが顔を上げた。耳まで赤いのが分かる。
可愛くて堪らない……。
吸い込まれるように唇を奪った。
「ん……」
啄むだけのつもりが、瞬く間にのめり込む。
唇を合わせたまま組み敷いて、柔らかな舌を搦め取る。
「んん……」
夕べと同じだ。躰が痺れる熱っぽいキス。
理性が吸い取られていくような……。
熱く火照った唇が頬を滑り、耳朶を甘噛みし、首筋へ下りていく。
左手がシャツごと背中を擦り上げ、右手が膨らみを探り出す。
互いの息が荒くなる。
縋るようにシーツを摑む。
桜色に匂い立つ肌。薔薇色に上気する頬。睫毛の隙間に見え隠れする潤んだ碧の瞳。
その碧海に溺れる前に、クラウスは動きを止めた。
深くついた溜息で、ユリウスの髪が揺れる。
「ク…ラウス……?」
「うん……」
背中を抱いて、ユリウスの躰を起こす。
「そろそろ、行こうか」
ベッドから立ち上がる。欲望も一緒に引き剥がして。
「クラウス、ボク……」
クラウスは、ユリウスの手を取った。
「続きは、お前がパリに来るときまでとっておくよ」
出発の日───
クラウスは、ユリウスに大きめの封筒を差し出した。
「何、これ?」
「コンセルヴァトワールの願書」
「え? ……どういうこと?」
「あのな、お前が俺とどれだけ離れているつもりか知らねぇが、俺は、そんな気はさらさら無いからな」
「あの……クラウス?」
初めは、状況が飲み込めないユリウス。
「いいか、来年絶対に来い。お前のレッスンは、ヴィルクリヒに頼んでおいたから」
「なっ! なんで、ヴィルクリヒ先生に!?」
更に、意味が分からなくなるユリウス。
「他に誰がいるんだよ? 最適任者だろうが。レッスンは週一で、早速来週からだ」
「そ、そんなの、ボク聞いてないッ」
「お前なら絶対受かる。ゼバスに編入できたんだからな。楽勝だ」
「クラウス、あのねボクは……」
ますます理解に苦しみ出すユリウス。
「いいか、これは命令だ。希望じゃない、願望でもない。命令、だ」
「ちょっと! そんなの横暴だってば! ボクの意志は無視なの?」
「これが最初で最後だ。あとは一生、お前の言うことは幾らでも聞いてやる」
「そういう問題じゃないよ! あぁもう信じられない、勝手過ぎるよっ!」
だんだん腹の虫が、治まらなくなってくるユリウス。
「うるせー! 俺はお前以外のパートナーは考えてないからな。お前が来るまで誰ともペアを組む気はない。だから、死んでもストレートで受かれよ」
「そんな無茶なっ!!」
もはや、傍若無人としか思えないユリウス。
「俺の部屋の隣が今、空いているんだ。流石に一年間確保しておくことは無理だが、まぁいざとなったら一緒に住めばいい。ベッドは一つだけど別に問題ないよな?」
「ク、クラウス!?」
急に話がすり替わり、ついていけなくなるユリウス。
「だいたいお前、俺にいつまで侘しい独り寝をさせとくつもりだ? ん?」
「え? え……!?」
「お前が、俺に火をつけたんだからな」
「そんなっ……、今になってそんなの……狡い」
まるで弱みを握られたように、足の爪先が浮いてくる。
それでも、なんだかどうにも釈然としないユリウス。
「覚えとけ。音楽も人生も、俺のパートナーはお前だけだ」
心臓を──射抜かれた。
意識が徐々に遠退いていくのをユリウスは自覚する。
このバリトンに揺さぶられるのは、これでもう何度目だろう。
そうなる度に考える。
そうなるごとに、解らなくなる。
そんなことはどうでもいいことなのだと、ユリウスは、この時やっと理解した。
恋人たちのペイヴメント
クリスマス休暇を利用して、ユリウスはパリに来ていた。
ーくしゅん!
と可愛いくしゃみに、クラウスは恋人の顔を覗き込む。
「おい、大丈夫か?」
「だ、だいじょぶ……」
「こんなにひっついてても寒いのかぁ?まったく」
「そんなっ、一回くしゃみしただけじゃない」
躰の半身と半身が両面テープで貼られたように隙間なく密着し、互いの腰に互いの腕が巻きついて、歩きにくいことこの上ない。
分かっているのに、どちらも離れようとはしなかった。
「おっ、ちょっと待ってろ」
不意に大きな躰が離れ、途端に片側が寒くなる。
「えっ?」
クラウスは少し離れた屋台に走っていくと、直ぐに何かを持って戻ってきた。
「ほら、手、出しな」
ユリウスの手のひらが、ほんわりと熱くなる。
「わぁ……あったかい」
「焼き栗だ。これで少しは温まるだろ?」
クラウスは、その中の一個を取り出し、殻を割った。
「ほれ、口、開けろ」
「んん……甘い」
「美味いか? んじゃ、もう一個……」
「そんな一気に無理……。クラウスも食べて」
「俺はいい。そんなに好きじゃないし」
「えっ? じゃあ買わなくても良かったのに」
「いいんだよ。お前に食べさせたかったんだから」
「ふうん……そうなの?」
ユリウスが、小首を傾げてクラウスを見上げる。
その愛らしい表情に、彼は一瞬で捕まった。
「やっぱ、貰おうかな……」
「そう? じゃあ今度はボクが割ってあげるね」
「それじゃない」
え……と言う間もなく、キスが落ちてきた。唇を啄まれ、ぬるりと舌が絡みつく。
「ん……。クラ……」
「こら。こんなときに喋ンな」
熱い囁きが、彼女の口を噤ませて、亜麻色の髪が両頬を隠した。
ユリウスは、焼き栗の袋を咄嗟に握る。
けれども既に、意識が半分飛んでいた。
コロン。
焼き栗が零れ落ちた。
ミャ~……。
「あ。……猫」
「え?」
石畳に転がった焼き栗に、白い猫がふすふすと鼻を寄せている。
ユリウスがしゃがみ込んだ。つられてクラウスも座り込む。
「お前さぁ、邪魔すんなよな」
猫に向かって、クラウスがぼやく。
「もう……何言ってるの? ごめんね、きみは悪くないよねぇ」
ユリウスが顎を撫でると、ゴロゴロと喉が鳴った。
「あの時の仔猫も、これくらいでかくなったかな」
「え……憶えているの? クラウス」
ユリウスは驚いた。今、自分も同じことを考えていたからだ。
「そりゃあ、初めてお前の泣き顔を見ちまったからな。セットで残ってるみたいだ」
あの頃は知らなかった。
彼女が泣いていた本当の理由、姉との喧嘩、決してそれだけではないということを。
脳天気に揶揄った、あの日の自分を蹴り飛ばしたかった。
そして出来るなら……、あの時に戻って彼女を抱き締めてやりたかった。
「やだ……。そんなこと……恥ずかしいから早く忘れてよ」
──ま、こいつは戻りたくもないだろうがな。
「忘れられるかよ。お前、子猫と同じくらいに震えててさ」
「それは……、寒かったからだよ。ほら、コートも着てなかったし」
「ばーか。この期に及んで、俺の前で強がるのか?」
「もうっ、直ぐにばかって言うの、ぜっんぜん直らないよね?」
「お前のその小生意気な態度もな」
また雲行きが怪しくなってきた。
白い猫は、呆れた顔……をしたかどうかは分からないが、ふいっと小走りで行ってしまった。
ユリウスが、すっくと立ち上がる。
「帰る!」
「どこに?」
「え…? あ、えーと‥‥」
「よし! 帰ろう」
ユリウスの手をぎゅっと握り、クラウスも立ち上がった。
「ど、どこに?」
「俺の部屋」
「え…うそっ!? だって、今日はパリの街を案内してくれるって」
「それは明日に変更だ」
「でも、まだこんな明るいのに帰るの勿体ない!」
「俺の計画が間違ってた。ほぼ半年振りにお前に逢うのに、順番が違うだろうが。浮かれてどうかしてたんだな」
ユリウスの腕を引っ張りながら、クラウスは脇目も振らず歩いていく。
「ねえ、何ぶつぶつ言ってるの?ほんとに帰るの?」
「お前が、帰るって言ったんだぞ」
「だって、それは……」
クラウスは途中から一言も喋らなくなり、ユリウスは完全無視された。
繋いだ手の力強さとじんわりと汗ばむほどの熱に、片手にある焼き栗の熱はとっくに冷めたというのに、ユリウスは視界が霞んでいくようだった。
部屋に入った途端、抱き上げられた。
「わっ! ク……クラウス!?」
そのまま寝室に連れて行かれ、ベッドに下ろされた。
クラウスはコートを脱いでソファに投げ、続けてユリウスのコートも、するりと脱がした。
「あの……、クラウス……?」
ベッドカバーが勢いよく剥がされ、床に落ちる。
ユリウスは、そのまま仰向けにされ、あっという間に組み敷かれた。
「ちょ……え!?」
彼女は、そこでやっと気付いた(遅過ぎる)。たちまち顔が火照りだす。
淡い水色のモヘアのセーターを捲り上げられ、袖から脱がしにかかろうとするクラウスに、ユリウスは仔猫のようにじたばた暴れた。
「ま、待って! ボク、朝からずっと移動で、埃っぽいなかドイツから来て、だから……」
「何言ってんだ? お前」
漸く、クラウスが口を開いたので、ユリウスはホッとする。
けれども、彼の手は止まらなかった。
あれよあれよという間に、セーターは剥ぎ取られ、ぽーんとソファに投げられる。
ユリウスは、心臓のメーターが今にも振り切れそうだった。
「クラウス、待ってってば! ねえっ!」
「……何だよ?」
ブラウスのボタンを三つ外したところで手が止まった。
「お願い……、シャワー浴びたい……」
真っ赤っかのユリウス。
「シャワー?」
「お願い、お願いー! それ以外はちゃんと言うこと聞くからっ」
ユリウスの頭に、友人からの忠告が蘇る。
『いーい? 逆らっちゃだめよ……』
変なところを真に受ける。
「しょうがねえなぁ……」
クラウスは立ち上がると、ユリウスを抱き起こした。ユリウスは、安堵の息をつく。
クラウスは促すように恋人の肩を抱き、バスルームのドアを開けた。
「使い方、分かるか?」
「だ、大丈夫!」
ボタン三つ分開いた胸もとを隠すように握り締め、もう片方の手でクラウスを外に追いやり、ユリウスはドアを閉めた。
「もう……」
──どうしてこんなことになっちゃうの?
まだ心臓がバクバクしている。
溜息をつきながら服を脱いだ。
シャワーを出して、手で温度を調整する。
少しずつ冷静になっていく。
熱いお湯のせいだろうか、とユリウスは思った。
埃っぽいと言ったのは、嘘ではない。
それを流すように頭からお湯を浴びる。
初めての時は夏だった。
──あのときは、どうしたっけ……あれ? 憶えてない。それどころじゃなかったし……。
何もかも目まぐるしくて、記憶が半分くらい飛んでいて。
えと……、あの時と同じことするんだよね、今から……今か…ら……。
だ、大丈夫、もう子供じゃないんだから……。
どうしよう……またドキドキしてきちゃった。
考えない考えない……考えな……
ーバタン。
シャワーの音の向こう側で、ドアの音が聞こえたような気がした。
──え……?
振り返る間もなく、後ろから抱き竦められた。
「きゃあぁっ!!!」
「お前、遅い」
「クラウス!? 嘘っ! やだ、なんで!?」
「タイムオーバーだ」
「そんなっ! 時間なんて聞いてない!」
当然の如く、男は聞く耳を持たず、濡れた金色の髪を、長い指で梳くように前に寄せていく。
「は、離して……」
「だ、め、だ。さっき、言うことを聞くって言ったろ?」
「え…ええっ……?」
クラウスの広い胸に、すっぽりと後ろ抱きにされ、ユリウスは身動きが取れない。
唇が、うなじに落とされ白い背中を這っていく。
「やっ……」
精一杯の抵抗は、掠れた声と一緒にシャワーの音に掻き消された。
痺れるように背中が熱い……。
これはお湯のせい? それとも彼のキスのせい?
クラウスが蛇口をひねり、お湯を止めた。
前を向かされ、口づけられる。
角度を変えて何度も。
水滴と一緒に舌が忍び込んでくる。奥まで……。
息ができない。
気が……遠くなっていく。
……熱い。
体温よりも。
「ク、クラウス……、はだ、か?」
湯気が立ち込めた中で、ぼんやりと彼の全身が見える。
「当たり前だろ? 風呂に服着て入るかよ?」
きつく抱き締められた。生身の躰が……重なった。
「あ」
首筋に、キスの雨。あの夜のように。
続いて鎖骨に、そして、二つの膨らみに……。
「だめ……、立ってられない……」
ユリウスが小刻みに揺れ始める。
「そうだな。このままだと寒いか……」
抱え込まれるように、脱衣所へ。されるがままに、躰をバスタオルでくるまれた。
濡れた髪も、彼の手で優しく拭われる。
「前も、お前の髪、こうやって拭いたっけな‥‥」
「う、ん……」
──もう……、余裕なんだから。
ユリウスは俯きながら、バスタオルの角を躰に押し込めるだけ押し込んだ。
顎に手を添えられ、キスをされた。それだけで蕩けそうになる。
タオルごと、抱き上げられた。必死に首にしがみ付く。
部屋は、ちょうど良く暖まっていた。
ベッドに下ろされるや否や、腕は簡単に振り解かれ、口づけの嵐。
タオルも、あっけなく取り去られてしまった。
シーツの海に、真っ白な裸体が曝け出される。
寝室の窓は小さいけれど、カーテンをしていても昼の光が漏れてくる。
少しでも躰を隠したくて、背中を丸めても横を向こうとしても、直ぐに元に戻されてしまうので、ユリウスは泣きたくなった。
「クラウス、明るいよ。恥ずかしい……」
「大丈夫。見てるのは俺だけだ」
──それが恥ずかしいのに……。
「綺麗だ……ユリウス。恥ずかしがることなんて、ひとつもない」
躰中が、彼の熱で融かされそう。
彼の視線が辿るところ、手が、唇が触れるところすべて……。
あの日も、こんな風に冷えた躰を包み込まれた。
家を飛び出した時、躰だけでなく心まで凍えそうで、いっそ凍ってしまえればと──。
それが見る見る溶かされた。
大きくて暖かいコートの中で、片側だけ、彼と密着したところだけが熱かった。
その熱は、夜になってベッドに入っても、じんわりと残っていて、
窓から差した月明かりは、何故だか不思議なほど温かく穏やかで、ボクにしては珍しく深い眠りに落ちていった。
夢の中で──月に浮かんだ彼の姿に全身が覆われて、ゆらゆらと漂っているようだった。
「クラウス……あったかい」
「ん……、そうか」
躰だけじゃなく心まで……、
あの時は、言いたくても言えなかった。
その言葉が、今は零れるように口に出る。
そんな自分が──嬉しかった。
パリの朝
鳥の囀りが聴こえてくる。
薄目を開けると、うららかな冬の光が窓から差し込んでいる。ふと、森の中かと錯覚する。
波打つ金色の髪がメデューサのように俺の肩や腕に絡みついている……(そんな言葉を聞かせたら、両眉を吊り上げて怒るだろう)。
規則正しい寝息。
陽射しが映す天使の寝顔。
いつもながら、よく眠っている。寝付きも良いし、寝たら起きない。
これでも昔はなかなか眠れなかったらしい。
こいつの生い立ちを考えれば当然かもしれないが……。
そんな翳りは今はすっかり取り払われた。
無垢な寝顔を眺めながら、そのしなやかな髪を指で梳く。
稀に、俺の腕の中で、ぞくっとするような艶やかな面貌を見せるのに。
昨日は、長距離移動で疲れただろう(移動だけが原因か?)。
ゆっくり眠らせてあげたい……と思う一方で早く起こしたい気にもなる。
そんな心が通じたのか、長い睫毛の奥から、碧色の光が降り注ぐ。
「……おはよ」
一瞬で俺を虜にする、甘いソプラノ。
ああ──もう堪らない。
返事の代わりに柔らかな唇を奪い、そのまま戸惑い逃げる舌も絡め取る。
「ん……っ」
身に纏っているのは俺のシャツだ(今やこいつのパジャマと化した)。ボタンを外すことなど造作もない。
俺の手にちょうど良い膨らみを形どるように指でなぞる。
「……ぁ」
掠れた吐息。
その僅かな空気の揺らぎが、どれほど俺を掻き立てるかお前は知らない。
すかさず薄桃色の頂に口づける。びくん、と細い躰が跳ねた。
そうすると、こいつの右手が宙に浮き、俺の左手を探し当て、指を絡ませてくる。
ジン…と熱い熱が伝わる。
「クラウス……やめて、朝だよ?」
そんなのが理由になるとでも思ってるのか?
「良いだろ? 朝の挨拶」
「なんか、そんな曲なかったっけ?」
「『愛の挨拶』──か?」
「そう、エルガーの。んん……っ、だからやめてってば……」
「ちょうどいいじゃんか。今の俺たちにぴったりだ」
「全然違うもん。や……ン……」
「お前そりゃないぜ。そんな声、聴かせといて」
「だって……、クラウスが……」
「その曲、後で聴かせてくれ」
「え? 良いけど」
「ピアノも、お前の繊細な指で弾かれたら悦ぶよ。いつも俺に叩かれているからな」
「ええ?」
ユリウスが吹き出した。
「俺の指は、お前の肌を弾いてる方が性に合ってる」
俺は五本の指で、シャツの内側のラインを撫で上げる。
「あっ……、何言ってるの! い、や……」
まどろっこしい。
息と息は、こんなに間近で絡み合ってる。言葉なんか無意味なほど。
なのに、こいつときたら……。
触れるそばから逃げようとする、往生際の悪い躰を捕らえ、火照った耳朶に囁いた。
「お前さぁ、たまには素直に抱かせてくれ。無駄な抵抗ばっかしてないで」
「え…え?」
「俺に向かって『抱いて…』って言ってくれた、あの時のお前はどこ行っちまったんだぁ? うん?」
「あ! あ、あれは……、もう意地悪っ!」
「可愛かったなぁ、あの時のお前」
「……」
泳ぎ過ぎて寄りそうな瞳を、わざと、じっと見詰める。
「昨日だって、あんなにじたばたされて。久し振りだったのによぅ」
「な…ッ! 当たり前じゃない! あんなのいくら何でも唐突過ぎるよっ!」
「はいはい、俺が悪かったよ」
「もぉう、ちっとも悪いって思ってない!」
「あーもう、うるせー。いい加減に黙れ」
「いつもいつも黙れって言えば済むと、んんん……っ」
ったく……、また初めからやり直しだ。
ひばりのようにぴいぴい鳴き喚く口を塞ぎ、大人しくなったところで──俺は、愛情たっぷりの朝の挨拶を奏でだす。
月の雫
※そして、コンセルヴァトワールに無事に受かったユリウス。勿論、合格祝いは……。
「お前の髪、シチューの匂いがする」
シャツのボタンを外しながら、クラウスが呟いた。エプロンは既にソファの上だ。
「え?」
「頑張ったんだな」
「だから、すぐに食べて欲しかったのに」
「シチューはいつでも食べられる。でも今のお前は、今だけだ」
その言葉で、何度言い包めてきただろう。気づかれないのが不思議なくらいだ。
クラウスは少女の躰からシャツを滑らせて取り払い、ソファに投げる。
この瞬間がユリウスはいつも恥ずかしくて堪らない。
普段は優しい二つの瞳が煽情的な色を帯び、躰の裏側まで見透かされているようだった。
そのことはクラウスも疾うに気づいていた。忽ち、彼女の頬が紅色に染まるからだ。
「なんか……屁理屈」
「そうか? それにまだ合格祝いもしてないし」
それを誤魔化そうとするが故に、彼女が饒舌になるのもいつものことだ。
「な……なんでボクの合格祝いでこうなるわけ?」
「俺には?」
「……え?」
「サポートして、応援したろ? 一ヶ月」
「そうだけど……それは感謝してるけれど。話が擦り替わってない?」
そして、それに暫く付き合って適当なところで切り上げる……のも、今やお決まりのパターンで。
「ま、どうでもいいか」
「んん……」
意識が遠退くほどの口づけを交わした後、広い胸がユリウスの柔肌に重なった。
金糸の髪を横に流すと、見る度に陶然となる滑らかな項が現れる。
光を当てたら、透過しそうな白い肌。
触れたら欠けてしまいそうで、一瞬、指が彷徨った。
肩と鎖骨のラインに沿って、そっとサインを残していく。壊してしまわないように。
膨らみが優しく包まれて、柔らかな蕾を指が掠める。
ユリウスは震える口を固く閉じて声を堪えた。
「ユリウス、我慢するなって言っただろ?」
「だ……だって、恥ずか……」
「お前の声が聴きたいんだ」
再び、唇と舌がそれに触れ、反射的に背中が反る。
水に落ちた小石の輪が広がるように、止め処なく襲ってくる火照りと痺れ。
躰の芯を、マグマが流れていくみたい。
もう何度、彼の躰に抱かれただろう?
ボクよりも、ボクのすべてを知っている大きな手と長い指、温かい唇と柔らかい舌……。
解ってる。こんな抵抗なんて無意味だと。
口に手を当てても外される。
顔を背けても戻される。
優しいのに意地悪だ。
意地悪だけど優しい……、ボクを操る鳶色の瞳。
──匂艶の……音色が零れ出す。
初めて彼女を抱いた時、真珠の涙を何度も掬った。
俺の躰にしがみつく細い腕、絡まる指先、星に輝く金色の髪。
月が泣いているようだ。そう思いながら抱きしめた。
群れからはぐれ岩礁に打ち上げられた人魚のように、性を偽り、虚勢を張って……、
そんな孤独の中で幾度となく見た哀しい涙が、悦びに変わった瞬間だった。
「ユリウス、俺の勝手な願いを聞いて、ここまで来てくれてありがとな」
「ふふ。初めはびっくりしたな。でも嬉しかった。だって本当は、ボクも追いかけて行きたかったから」
「そうなのか?」
「ついて行っていいんだ……、って思った」
「当たり前だ。お前のことは、もう離さないって言っただろ?」
「クラウスは、ボクの太陽みたい」
「は……、大袈裟だな。俺はそんな大層なもんじゃないよ」
「そんなことない。クラウスがボクの影を照らしてくれて、ボクの本当の声と心を取り戻してくれたんだもの。今のボクがあるのは、君のお陰だよ」
そうして、愛しくて柔らかくて儚げな肢体が、少し冷めた躰に絡みついてきた。
次の瞬間、躰が熱を帯びてくる。
首筋に纏わり付く靭やかな指と甘い吐息に、俺のほうが溶かされそうだ。
「おい、シチューはいいのか? また遅くなっちまうぞ?」
「え? ボクはシチューよりあなたが食べたいのに……」
「おま……」
「なーんてウソ。食べようか。きゃっ!」
「そんな軽はずみなこと言って、それで済まされると思ってんのか? ん?」
「え、冗談だってば。離してよっ……んっ!」
「もう遅い、火が付いた」
「や、やだっ! シチューを食べるの。あっ……ん」
「シチューよりお前が食べたい」
「それ、さっきも言ったじゃない!」
「さっきはさっき。今は今」
「だめっ! 一人一回まで!」
「そんなルール、いつ決めたんだよ?」
「今だよ! や、やめて……」
「お前も成長したな。俺を誘ってくるとはな」
「だから違うって……、や……ん」
「愛しているよ、ユリウス」
「なっ! ついでみたいに言わないで!」
「ほんとだって」
「嘘つきっ!」
「嘘じゃない」
「うそ……」
「本当だ。ユリウス」
「……」
「愛している」
「も……ぉ……」
愛している……
どんなに伝えても伝え切れないほど
言葉では言い尽くせないほど
天つ空から降りてきた
俺の、エウリディケ……