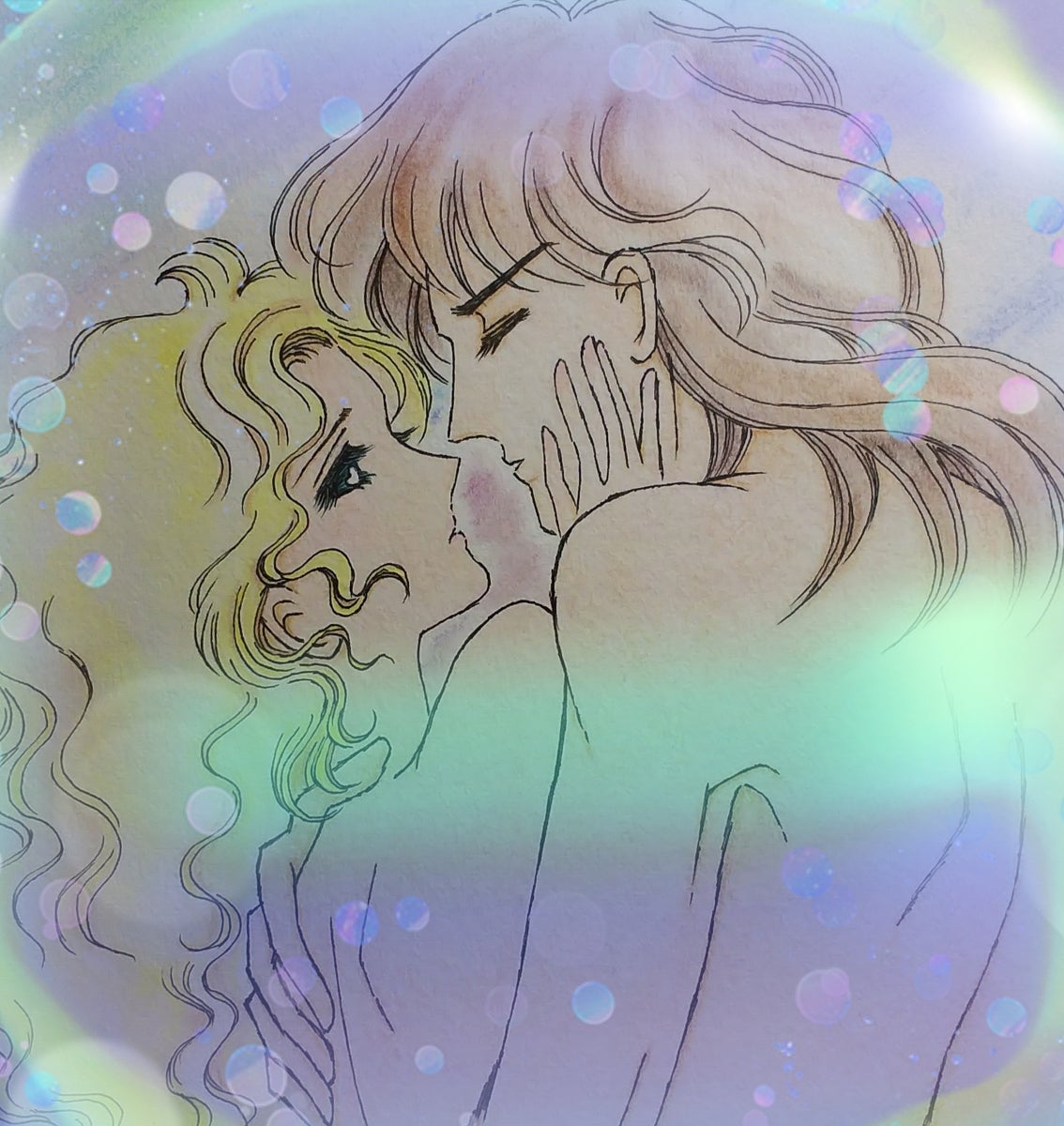──或る日、天使を抱き止めた。
此処が俺とお前の出発点。
手を繋ぎ、確かめ合い、
階段を上るように、
一段ずつ、愛を育んでゆく二人の軌跡(ときどき暴走)。
![]()
![]()
![]()
pixiv三年目突入記念で調子こいて上げた総集編です(この頃は元気だったなぁ)。
二人の出逢いからプロポーズまでの道程を、主に二人の関係が変化していく場面をピックアップして纏めました。切り取り方は様々、年代順に並べ替えた話もあります。なるべく簡潔に、と頑張りましたが、長いです。なんと総文字数約77000文字(ほぼコピペ![]() )。
)。
アメブロではどーやって上げようか。当然、一気に上げるには無理がある(アメブロの制限文字数は、日本語入力でおよそ30000文字)。
単なる過去作の羅列なら、載せなければいい話なのですが、過去作の間に新エピソードを挟んでいるため、それは皆さんに読んでほしい📖
悩んだ末、各章又はきりの良いエピソードごとに区切って投稿することにしました。
加筆修正しながら、少しずつ進めていきます。何話に分けるかも未定です。読み難い点もあるかもしれませんが、宜しくお願い致します![]()
プロローグ
幻ばかり追いかけていた①
幻ばかり追いかけていた──
お前に出逢うまでは……。
音楽は好きだった。
ストラディヴァリを構えると、ピンと張り詰める空気。
音色とともに揺れ始める空気。
強弱に乗って風になる空気。
でも現実は平坦で、微風すら吹かない毎日が続く。
前奏曲
その頃、俺は、事あるごとに、親父と将来のことで衝突していた。
音楽の道へ進みたい俺と、自分の仕事を継がせたい親父。
親父にしてみれば、勉強の合間の気分転換のために買い与えたヴァイオリンに、俺がここまで夢中になるとは夢にも思わなかったようだ。
いつまでも子供が親の言うことを大人しく聞くとでも思ったら大間違いだ。
![]()
![]()
![]()
同じ時期、俺自身に、それとは別の波が起きた。
陳腐な言葉で表すなら、男の儀式を済ませた。若しくは、大人への関門を通過した。とでもいうのだろうか。
事実、そういう年頃だった。
同じクラスの、「幼馴染みのお姉さんに誘われて」などとひけらかすやつを取り囲み、
羨ましげに囃し立てる者。遠巻きに眺めるだけの者。
自分はどちらにも属さなかった。
別に、完璧無比を気取っていたわけではない。
どちらかと言えば、苦い経験だった。
いや……、単に自分が青かっただけだろう。
晩夏から冬。季節風のように吹き抜けて、サクラとともに散った記憶。
![]()
![]()
![]()
三月に入って最初の日曜日、親父がいきなり封筒を寄越した。
「何だよ? これ」
「お前の新しい学校だ」
「は!? いくら学校を変えたからって、俺の気持ちは……」
「無駄な台詞を吐く前に、中を見ろ」
こういう言い方が気に食わない。俺は、がさがさと封筒を開ける。
「聖……ゼバスチアン? 音楽学校……?」
「場所はレーゲンスブルクだ。行く気があるなら、試験は二週間後だそうだ」
青天の霹靂だった。
一体全体、どういう心境の変化なのか。
にわかには信じ難かったが、下手なことを言うと元の木阿弥になりかねない。藪は突かないことにした。
「……ありがとう」
親父の目が丸くなる。
ふん……、俺だって素直になる時くらいあるさ。
とにかく、奇跡だ。
逸る気持ちを抑えられず、外に飛び出すと、街中が喧騒に包まれていた。
そうだ、今日はカーニバルだった。すっかり忘れていた。
仮面を付け、仮装した人々が至るところに溢れ、歩きながら陽気な歌を歌いだす。
ドイツの三大カーニバルの一つ、断食の前夜祭と呼ばれるマインツのカーニバル。
見上げれば、風船と紙ふぶきが宙を舞う。歓声とビールの泡と、子供たちの笑い声。
「母さん! 母さん、ねえ似合う?」
一際高く響く声に、俺は思わず振り返った。
まるで花びらが舞うように白いワンピースを翻し、くるくる回る小さな姿が通り過ぎた。紙ふぶきをくっつけた金色の髪が弾むように揺れている。
「ねえ母さん、次から『ハンガリー狂詩曲』をやってみようって先生に言われたんだよ。すごい?」
人波に飲まれていった後ろ姿を、俺はいつまでもぼんやりと眺めていた。
いつまでも………
理由は、分からない。
前奏曲/後日談
試験は無事に合格した。
親父にも結果を報告した。返事は、「お前なら受かると思っていた」と一言だけ。
おめでとうくらい言えないのか。まったく、親父らしくて笑えてくる。
書斎から出ていこうとすると、
「ちょっと待て」
と呼び止められた。
親父は椅子から立ち上がり、デスクの後ろにある両扉キャビネットの鍵を開けた。合格祝いでもくれる気か?
ところが、信じられないことに、親父が抱えてきたのは、革製のヴァイオリンケースだった。
蓋を開けて、更に驚く。
「これ……、ストラディヴァリウス……じゃないか」
「ほう。大したものだ。お前でも識別できるのか」
嫌味さえ耳の横を擦り抜けた。それほど信じ難いものを見せられたのだ。
「どうしてこんなものがここに……。本物だよな?」
「お前のために手に入れたわけじゃない。これは、私の楽器だ」
「は?」
「昔、フランクフルトのオーケストラで、コンサートマスターをやっていた。まだ結婚する前のことだ」
親父がオーケストラで、ヴァイオリンを演奏していた? それもコンマスだって?
寝耳に水とはこのことだ。
「そんなこと初めて聞くぞッ!」
「当然だ。お前に話した覚えはない」
──何だとお!?
「だいたい、どうやって手に入れたんだ? オーケストラってそんなに羽振りがいいのかよ?」
「まさか。とてもじゃないが、一介の楽団員が所有できるような代物ではない。楽器ディーラーの話では、フランスの富豪の遺品だそうだ」
そう言って、親父は鑑定書を見せてくれた。
製作者名「アントニオ・ストラディヴァリ」。確かに、正真正銘のストラディヴァリウスだった。
その鑑定書によると、ロシアの貴族のもとを経て、フランスの富豪へ渡ったのが最後らしい。
「まず、その気品ある姿に魅せられた。次に、類い稀なる妙なる音色に。瞬く間に、その不思議な魔力の虜になった。しかし、私には、絶対に入手不可能だった。かといって親には頼めない。私の父は、私が音楽を続けることに反対だったからな」
それを聞いて、俺は呆れた。
「蛙の子は蛙だな。親子二代で、子供の将来に口出ししたのかよ」
「買ってくれたのは私の母だ。音楽好きだった母は、よく私のコンサートを聴きに来てくれた。楽屋まで訪ねてくることもあった。私は知らなかったが、そのときに、誰かから、ストラディヴァリウスの一件を聞いたのではないかと思う」
祖母は資産家の一人娘だったらしい。ストラディヴァリウスの一挺くらい造作もないことだったのだろう。
そうして、家族に内緒で、祖母はそれを手に入れた。ただ、息子を喜ばせたい、この楽器を演奏する息子の姿が見てみたい、という一心で。
いきなり目の前に差し出されたストラディヴァリウスを見て、親父は困惑し、初めは固辞したそうだ。
自分には一生かけても返せない、と。
すると、祖母は親父に告げた。
『良いわ。では約束しましょう。これからずっと、母さんに、その美しくて清らかな音色を聴かせてちょうだい。一生かけてね』
「一生かけて──母が満足するまで奏で続けよう。嬉しそうに微笑む母の目を見て、私は誓った」
親父はストラディヴァリの縁線を愛でるように指で撫でている。
「それなのに、それから一年も経たずに、母は逝った。まだ、この弦の響きの、10分の1も伝えきらないうちに……」
生まれてこのかた親父のそんな表情は見たことがない。幼い頃は、仕事一筋のアンドロイドじゃないかと思っていたから。
祖母の急逝により、祖父は再び、親父の音楽に難色を示し始めたらしい。
「逆らえば良かったじゃないか。俺みたいに」
「もちろん何度も説得を試みた。だが、父親の態度は硬化する一方だった。結局、最後は押し切られる形になり、私は会社を継ぐ決意を固めた。そうと決めたからには、半端な気持ちは切り捨てた。オーケストラは退団し、音楽とも縁を切った。だが、どうしても、これだけは手放せなくてな」
今や、合格の喜びさえ、何処かへ吹き飛んでしまっていた。
「未練は、なかったのか?」
「最初は辛かった。最後のコンサートが終了して、この蓋を閉じるとき、手足を捥がれる痛みが走った。しかし、そのうち忙しさにかまけて忘れてしまった。何十年も思い出しもしなかった。お前のヴァイオリンに対する訴えを、毎日のように聞かされていてもだ。いつだったか、お前と大喧嘩になったことがあったろう」
どの大喧嘩だ? と考える。それくらい日常茶飯事だったのだ。
「『勘当だ! この馬鹿息子!』と怒鳴ったときだ」
思い出したぞ、こんちくしょう。
「ああ……、俺が『死んじまえ! くそ親父!』と罵声を浴びせて、ここから飛び出していったときか」
お互いに、立ったまま睨み合う。親父は僅かに顔を逸らした。
「その後、鏡を見て愕然とした」
「鏡?」
「そこには、私にヴァイオリンとの決別を宣告した父親の顔が映っていたんだ。二度と思い出したくもない嫌な顔。そのとき、初めて、自分のしていることの愚かさに気がついた。……母さんにも叱られたよ。自分の息子にまで不本意な道を歩ませるつもりなの、とな」
「そんなことを……母さんが……」
「母さんは、私のヴァイオリンが好きだった。客演で、何度か、チェンバロを弾きにきていてな」
な──何だって?
「ちょっと待て! ていうことは、母さんはピアニストだったのか?」
「聞いていないのか?」
「聞いてないっ!」
何ということだろう……。
これ以上、驚かされることはないと思っていたのに。
ヴァイオリンを習い始めたときから、ときどき母さんは伴奏をしてくれた。
初めて聴いたとき、素人とは思えない滑らかな演奏に、子供ながらにびっくりしたことを覚えている。
「どうしてそんなに上手なの?」
と聞く俺に、
「小さい頃から習っていたから。それだけよ」
と、母さんは、はにかんだ表情で答えるだけだった。
家にピアノがあるのも単なる趣味だと思っていたのだ。
どうりでプロ並みに上手いわけだ。本物のプロだったのだから。
それにしても、なんて親だ!
二人して、秘密主義にもほどがある。
親父はヴァイオリンケースの蓋を閉じると、大事そうに両手で抱え、俺に向かって差し出した。
なんだか、躊躇する。本当に受け取って良いのだろうか。俺には、分不相応じゃないのか。
「これ……、俺に持つ資格はあるのかな?」
「良い楽器を持つことは、良い師に出会うことと同等の価値があると言われている。けれど、それが証明されるのは、お前がゼバスに入ってからだろう」
「蛙の子は蛙って言わないのかよ」
「随分と目標が低いじゃないか。せめて、鳶が鷹を生んだと言われるくらいにはなってほしいものだ」
──ちぇっ、くそ親父め……。
ドアを開ける前、ふと合格通知に目をやった。封筒に印刷された【聖ゼバスチアン】の文字を。
俺は振り返った。
「なあ。この音楽学校って、もしかして……」
親父は、気づいたかというように、にやりと笑う。親父の笑った顔なんていつ以来だろう。この上なく、不気味だった。
「私の母校だ」
六月──、俺は、小振りの旅行鞄とヴァイオリンケースを手にして列車に乗った。
窓際の席に腰を下ろすと、ほどなく発車のベルが鳴る。
直行便にしたのは、乗り換えが面倒なのもあるが、ストラディヴァリを抱えて、なるべく動き回りたくなかったからだ。それでも、4時間の長旅である。
途中、でかい鉄橋を渡る。この川を下れば、新しい目的地まで繋がっているのだろうか。バイエルンに位置する歴史と音楽の街。
そういえば、あの音楽学校にも古寂れた塔があった。それから、そこだけ時間が止まったみたいな窓が一つ。何て言ったか、聞いたような気もするが、忘れてしまった。そもそも、試験直前に、耳に入れるほどの情報か?
能天気な教師の名前は……、ほら覚えていない。
ほぼ予定通りの時刻に、学校へ到着した。
直ぐに寮へ案内される。造りは古いが小綺麗な部屋だった。あまり期待していなかったので嬉しかった。何もなければ(問題を起こさなければ)、5年間ここで生活するのだ。
「何か質問は?」
部屋を見回しながら寮監が訊いた。
「特にありません」
そう答えると、寮監は頷いて部屋から出ていった。
先に送った荷物は既に届いていた。窓を開けると、枝振りの良い樹が迫っている。手を伸ばせば届きそうだった。緊急時にはここから逃げられるだろう。緊急時って何だ? と一瞬考える。火事とか?
馬鹿なことを。思わず口もとが緩む。やはり少し浮かれているのかもしれない。
白い鳥が一羽だけ飛び立つのが見えた。
「それは、ストラディヴァリ?」
突然、背後から話しかけられた。
ヴァイオリンケースから、ストラディヴァリを取り出した時だった。
ドア際に、男が立っている。おい、ノックの音を聞いてないぞ。
「良く分かったな」
「ニスの塗り方に特徴があるだろう。僕も、一応ヴァイオリンを嗜む身なのでね」
初対面なのに馴れ馴れしいな。上級生だろうか?
シスターリボンをしているから……、8年生よりは下のはずだ。偉く大人びて見えるけれど。
「ヴァイオリン科なのか?」
「そう。来年度から6年だ」
やっぱり。一つ年上か。
男は近づき、熱っぽい目で、ストラディヴァリを見つめている。
「素晴らしい。この美しい艶とライン。なんだか、成熟した女性を思わせないか」
……気持ち悪いやつだな。
そんな心の声を読み取ったかのように、男は話題を変えた。
「編入生だろう? 珍しいな、夏休み前に来るなんて」
「休み中に、レッスンを受けるから」
「へえ。将来有望なんだな」
単に遅れを取っているからだと思うが、面倒なので黙っていた。
「部屋は……、おお偶然にも隣じゃないか。なんだか、お前とは仲良くなれそうな予感がするよ」
なんだこいつ?
馴れ馴れしい上に、かなり調子のいいこの男。名前は──、
「ダーヴィト・ラッセンだ。よろしく相棒」
![]() 『前奏曲』は後日談を加筆。クラウスのルーツをもう少し深掘りしました。
『前奏曲』は後日談を加筆。クラウスのルーツをもう少し深掘りしました。
当時はまだ不鮮明だったクラウスの父、再登場です(父と息子の会話って難しい)。流れついでに、悪友との出会いも足しました。
参考文献*「千住家にストラディヴァリウスが来た日」千住文子著
Puppe(蛹)
幻ばかり追いかけていた②
そんなとき、川面に石を投げられた。
小さいけれど重く、夜空に光る星よりも眩く瞬く。
幾度となく、ぶつかり合った。
![]()
![]()
![]()
「なあ、今度、編入生が来るらしい。それも二人」
生き生きとした声で、悪友が言った。
「こんな時期にか? 学期のど真ん中だぞ」
「編入生っていうのはそういうもんだろう。さっき、一人だけ、ちらっと見かけたんだ。それが見事な金髪でさ」
「金髪なんて、どこにでもいるだろうが」
「いや、その辺にいる金髪とは違っていたね。後ろ姿だけだけれど、躰の線も細くて、なんだか儚げでさ。あぁ顔を見たかったなぁ。絶対に綺麗なやつだよ」
男相手に、いったいどこを見てんだよ? と呆れ返る。
「はっ! いくら儚げで綺麗だって、男じゃしょうがないだろうよ」
「美しいものに男も女も関係ないさ。そりゃあ女性だったら言うことなしだけどね」
お前の美意識なんてどうでもいい。
「あぁあ、なんでこんな学校に入っちまったのかなあ。見渡せど見渡せど、周りは男ばかりなり。初めは親父に感謝したけど、今は恨むぜ」
「は? どうして親父さんが出てくるんだ?」
「べ、別に。何でもねえよ」
儚げで綺麗で、天使みたいな女が空から降ってこないかな……とちょっと思う。
思っただけである。
オルフェウスの窓
※実は書いていなかった「窓での出逢い」。新エピソードです。
見上げると、一昨日の喧嘩の相手、風邪の原因、端的に言うなら、気に食わないやつが視界に入った。予期せぬことに。
「よう、聖者の相棒。風邪はどうだ? お前、アーレンスマイヤ家の御嫡男だって? 跡取りたる者、もうちっと沈着冷静でいないと、お前の代で身上を潰し兼ねないぞ」
最後の台詞にむかついて、無言で立ち去る。大きなお世話だ。
何がオルフェウスの窓だ。こんな半分崩れかけた窓に運命の相手を決められて堪るものか。
背後から「おい、待てよ!」という声がした。無視をした。
![]()
![]()
![]()
金色の髪が逃げていく。小生意気な編入生。慌てて階段を駆け下りたら、ダーヴィトのやつにぶつかりそうになった。
「クラウスか! 危ないなあ」
「あいつ、何処に行った?」
「誰のことだ?」
「えーと、何だっけ? 聖者の相棒、金髪の」
「ああ、ユリウスか。彼なら礼拝堂じゃないか」
「礼拝堂? このくそ寒いのにか」
「お前のせいだろうが。いたいけな子羊相手に取っ組み合いなんかして」
「いたいけぇ? 何処がだよ?」
「ヴィルクリヒの罰だよ。聖書暗唱。可哀想に。また風邪が、ぶり返さないといいけどなぁ」
なんだか、当てつけのように聞こえたのは気のせいか。
その後、俺は、厳粛な礼拝堂に降り立った天使を目の当たりにしたのである。
紅いくちびる~春の兆し~
光が、あれほどまでに眩しいものだとは、俺は知らなかった。
あいつに出逢うまでは・・・
『触るなっ!!』
『ユリウス!?』
『ボクはいいんだ、触るな!』
ちょっとした小競り合いの最中に、忌々しい音楽教師に頭から水をかけられて、びしょ濡れのまま逃げるように走り去っていったあいつは、翌日になっても姿を見せなかった。俺は、一緒に濡れ鼠になったもう一人の編入生を呼び止めた。
『おい、お前の変な相棒はどうした?』
『ああ……、今日は欠席らしいです。風邪を引いたみたいで……』
『ふん、言わんこっちゃない。この寒空に飛び出していったりするからだ。せっかくの俺の厚意を無下にしやがって』
『はあ……』
その翌日。
礼拝堂にいるあいつを見つけたのは、オルフェウスの窓で出くわした直後のことだった。
陽光の届かない寒々しい空間に、折り重なるように波うつ淡い金髪。目を奪われる。
『我を恤れめ……、神の手我を撃てり……』
掠れた声。
まるで片翼をもがれた天使だった。
言葉が途切れる。あいつは身動ぎもせず、ただ一点を見据えている。
そのまま凍りついてしまうのではないか、と俺は思った。
パキッ、という張りつめた空気の割れる音。その拍子に、顔を上げたあいつと目が合った。
その時やっと、頬を伝う涙に気がつく。泣いていたのだ。
ある意味、窓から眺めた時よりも神聖で運命的な何かを感じたのは、礼拝堂という場所だからか、或いは俺を見据えて揺らぐ碧海のせいなのか。
その時はまだ、あいつが女だなんて、これっぽっちも思っていなかったというのに……。
あいつはすぐに歩きだし、俺の横を擦り抜ける。咄嗟に摑んだ細い手首は想像以上に冷たかった。
『は……離せ!』
『何言ってんだ! 氷みたいな手をして。病み上がりのくせに肺炎になる気かよ?』
『聖書暗唱10回!』
『はあ?』
『ミサに遅れた罰だよ』
『そんなもん、まともに聞く方がどうかしてるぜ。来いよ』
『でも……!』
問答無用で太陽の下へ引き摺り出すと、あいつは眩しそうに睫毛を瞬かせた。
木洩れ日に融ける金色の髪が息を吹き返したように光を放つ。
『は……はっくしゅん!』
『ほーれ、ぶり返した』
『違う、これはっ』
無邪気で反抗的な人間らしい表情が顔を覗かせ、俺は少しほっとした。俺たちとは別の存在、言うなれば天上の者……という不思議な幻想は消えていく。
『ユリウス、だったか?』
『……うん。君は、ク、ラウス?』
俺はもう片方の手を摑み、両手で小さな手を包み込んだ。
『お、よく覚えてたな』
『覚えてるよ、それくらい……』
握り続けていた手は少しずつ温まってくる。さっきの抵抗は何処へやら、大人しくしているところをみると本当に寒かったようだ。
『熱は?』
『熱なんて、夕べのうちに下がったよ。ねえ……いい加減に離してよ』
『まだ指先が冷たい。これじゃ鍵盤が叩けねえぞ』
『大丈夫だよ。実技レッスンは午後からなんだから』
そう言って、あいつは手を振りほどき、俺のことを軽く睨んだ。さっきよりも顔が赤い。また熱が上がったのではないかと俺は不安になる。
けれども、それを指摘する前に、あいつは走り去っていってしまった。
天から下りてきた天使が、また天へ帰っていく……。再び、そんな幻想が俺を支配する。
だが、あいつの手を握っていた左手の温もりは、しばらくの間、消えなかった。
天から降りてきた天使が、再び天へ帰っていくように
俺の躰の中心が光で満たされ始めたのは、この瞬間からだったのかもしれない。
![]()
![]()
![]()
先刻まではあんなに嫌なやつだったのに……。どうして急に態度が変わるんだ?
意地悪なやつは、どこまでも意地悪だった。自分の味方は一人もいないと、常に思い知らされてきた。
男でも。女でも。
他人でも。身内でさえも。
この学校が独特なのか。それとも、彼だけが特別なのか。
無礼でお節介な上級生。あまり関わるのは危険かもしれない……。
正体がばれないようにしなくては。
絶対に。
我が友よ……、
汝ら
我を恤れめ、
我を恤れめ、
我を………。