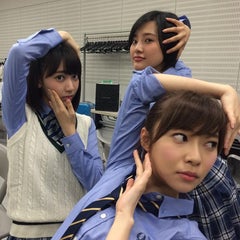モカさん(仮名・当時15歳)に取材した日のことは、今も僕の心に印象深く残っている。そのインタビュー動画は500万回再生を超え、僕のチャンネルで最も試聴されている。さまざまなメディアでも取り上げられ、大きな反響を呼んだ。本書において、彼女のことに触れないわけにはいかないだろう。僕が彼女と出会ったのは2022年2月の終わりだった。

その日の昼12時、僕はJR新宿駅の東南口でホームレスの取材をスタートした。しかし、この日はことごとく取材を断られた。取材を承諾してくれる人が一向に見つからない。東南口から東口へ、東口から西口へ、そして西口から歌舞伎町へと向かう間、10人ほどのホームレスに声をかけてみたものの、良い返事をもらうことができなかった。すでに時計の針は15時を回っている。2月の寒さは厳しかったが、3時間も歩き回った僕のシャツの背中にはほんのりと汗が滲んでいた。
歌舞伎町の中へと入っていった僕は、ゴジラの頭部を象った巨大なオブジェで知られる新宿東宝ビル、通称ゴジラビルの植え込みのあたりにたどり着いた。腰ほどの高さまである植え込みの側面にもたれかかり、少しだけ足を休める。3時間歩き回ったのに取材対象者を見つけられず、僕は疲れと焦りを感じながら「ふぅ」と弱々しく息を漏らした。腰かけるのにちょうど良い一段低い高さの植え込みもあったが、そちらの植え込みには囲いの上部にトゲ状の突起が付いていた。そのトゲトゲを眺めているうちに、最近よく耳にする言葉がふと脳裏に浮かんだ。
中学3年生のモカさんに学校について尋ねてみると、こんな答えが返ってきた。
「私、小学校4年生からほとんど学校には行ってないんですよ」
ホストのお兄さんの仕事が終わるのはいつも朝方で、モカさんはそれまでの時間を歌舞伎町の路上やネットカフェで過ごしていた。時には、ホストクラブのバックヤードでお兄さんの仕事が終わるのを待たせてもらうこともあるそうだ。もちろん警察に補導されて、実家に連れ戻されることも何度もあった。しかし、そのたびに実家を抜け出し、お兄さんのいる歌舞伎町へと舞い戻る。そんな日々を繰り返してきた。結果、歌舞伎町にたどり着いた10歳から今まで、学校にはほとんど行っていないという。
トー横界隈の古株と思われたくない
諸説あるが、「トー横界隈」や「トー横キッズ」といった言葉やカルチャーが生まれたのは2019年頃。モカさんと僕が出会ったのは2022年で、彼女が歌舞伎町に通うようになったのがそこから5年前。出会ってから1年が経ちこの本を執筆している2023年から数えると6年前の2017年。モカさんが歌舞伎町で過ごすようになった当初、まだ「トー横界隈」や「トー横キッズ」という言葉は存在しなかったのではないだろうか。当時の彼女がここで知り合った家出少年・少女のコミュニティーこそが「トー横界隈」の走りであったに違いない。
今ではトー横界隈と呼ばれるようになった植え込みの近くに座るモカさんに、僕は「じゃあ古株ですね。トー横界隈のスタート時からいるんだから」と何気なく言った。するとモカさんは、少しだけ困ったような素振りで、髪をいじりながらこう答えた。
「うーん……。それ(古株であること)を言うと、みんな怒るんですよね。古いからってイキがってるなよみたいになるんで。そういうのはみんなには言わないようにしてます」
僕は驚いた。自分の知る限り、どの世界も長くいる者は敬われるのが自然な風潮だろう。しかし、トー横界隈にはそんなものはないようだった。近年「マウント」という言葉をよく耳にする。今の若い人たちはマウントにとくに敏感という印象を受ける。年配者であっても、人はマウントを取ろうと機会をうかがい、誰かにマウントを取られることを恐れ、マウントを取ろうとする者は敵と見なされるケースも多い。トー横界隈も例外ではなく、あいつはマウントを取ろうとしている、と思われるだけで周囲から敵意を向けられる対象になりかねない。それを恐れてモカさんは、自分が数年前から歌舞伎町に通っていることを周りには隠していた。
反対に、最近になってトー横にやって来る子に対して、モカさんは自分との違いを感じているという。新しい子たちのことをモカさんは「新規」と呼んだ。
「TikTokとかで動画が上がってるから、トー横にあこがれてる子が増えちゃって。家庭環境が悪いわけでもないし、本人にとってはつらいんだろうけど、食べるご飯があって帰る家があるのに『死にたい』って言ってる子たちも最近は増えてきました」
さらに「新規同士でマウントを取り合うケンカもある」とモカさんは教えてくれた。
夜はホテルかカスタマ
では、現在の彼女は歌舞伎町のトー横界隈でどのように生活しているのか。
僕が「今はどこに行こうとしてたんですか?」と尋ねると、「トー横に人がいなかったら広場のほうに行こうかなーと思って」と屈託のないしゃべり方で応じるモカさん。トー横の路地の一角に着くと、彼女はパーカーの袖から小さな手の先っぽだけを出して両腕を広げ、「ここが、いつもみんないる場所」と教えてくれた。そのときには仲間たちの姿は見当たらない様子だったが、モカさんは「あ、夜はいっぱいいますよ」と付け加える。
彼女によると、トー横界隈には同じような境遇の仲間が集まっており、夜はホテルの1室を割り勘で借りて、寝泊まりに使っているという。ネットで予約した部屋に複数の若者たちが出入りする形だ。支払いは自動精算機という場合も多いが、ホテルのフロントなどに出向く場合は、成人している仲間がやってくれる。ホテルだけでなくネットカフェの狭いブースを複数人で使い回すこともあるらしい。
ちなみに、一般的なホテルやビジネスホテルの場合、1室を複数人で使うのは利用規約違反になる。もちろん、1室2名といった宿泊プランどおりの適切な使用であれば問題ないのだが、ホテル側に無断で複数人が部屋に出入りして寝泊まりするというのは、宿泊者名簿の記載を宿泊施設に義務づけている旅館業法、1部屋当たりの利用人数を制限する消防法などに触れる法令違反となる行為だ。2022年4月には警視庁立ち会いのもと、トー横界隈近隣のホテルに新宿区の立ち入り検査が入ったこともある。
モカさんから話を聞いているうちに、少しだけ雨がパラついてきた。降り始めたばかりの小雨とはいえ、冬の雨は冷たい。僕はモカさんといっしょに雨をしのげる場所へ移動することにした。トー横の路地を歩きながら、世間話をするように取材を続ける。
「トー横キッズの人たちって雨が降り出したらどこに移動するんですか?」
「雨が降ったら……ホテルに戻るか、ドンキとか、ゲーセンとか」
「あ、なるほど。でも夜になると(ゲームセンターは)閉まっちゃいますよね」
「夜は、雨でも外にいる子もいるし、ホテルに帰る子もいる」
濡れてしまうのが気になるのか、モカさんは前髪のあたりを手でカバーしながら話を続ける。
「ホテルにも10人くらい集まってるんで、別に中にいようと外にいようと楽しさは変わらないんですよね」
そう言ってモカさんは笑う。歩いていると「CUSTOMA」というアルファベットが並ぶ看板が見えた。ホテル代わりに使っているネットカフェのことをモカさんが「カスタマ」と呼んでいたことを思い出す。
「あ、ひょっとしてあれですかカスタマって」
「そうです。カスタマっていっぱいあるんですよ。これは『グラン』」
彼女が教えてくれたように、店舗の正面に「GRAN CUSTOMA」という文字が照明によって明るく輝いている。あとで調べてみたところ「カスタマカフェ」は東京、埼玉、千葉のターミナル駅を中心に店舗を展開する漫画喫茶・インターネットカフェで、歌舞伎町の「GRAN CUSTOMA」には、複数人で泊まることができる広めの個室、シャワー、ランドリーなどがある。トー横キッズの寝泊まりには確かに便利な施設だ。
モカさんは、トー横界隈のことを何も知らない僕の質問に、嫌な素振りを見せずににこにこと付き合ってくれた。僕らは近場にあったビルのひさしの下で雨宿りしながら取材を続けた。
10歳から歌舞伎町で過ごす
僕は、彼女と会った直後に交わした会話を思い返した。両親がいる家に近寄らず「いちばん最後に帰ったのは2年前」だとモカさんは話していた。
歌舞伎町で10歳から現在まで約5年間もの期間を過ごし、直近2年間は一度も家に帰っていないと語った彼女。「さすがにご両親から連絡があるのでは?」と聞くと、モカさんは食い気味に「ないです」と答えた。その瞬間だけ、彼女の目が少しだけ曇って見えた。取材中にどんな質問を投げかけても、飄々と、淡々と、時にはにこやかに答えてくれた彼女が、このときだけは胸の内に渦巻く激しい感情を露わにしたように僕には思えた。
両親からの連絡は「ない」と言い切ったモカさんは少しの沈黙のあと、こうつぶやいた。
「どうでもいいと思う……」
これを聞いて僕は、両親が自分の娘のことをどうでもいいと思っている、という嘆きの言葉だと理解したのだが、もしかしたら彼女が両親のことを「どうでもいい」と突き放していたのかもしれない。
現在の両親はモカさんに対して無関心だという。
モカさんは精神科病院に5カ月間ほど入院した経験がある。僕が話を聞いたのが2月で、前年の年末まで入院していたという。つまり、両親のもとに帰らずにいるこの2年の間に起きた出来事だった。当然、両親にもモカさんの入院を知らせる連絡が入ることになったが、そのときの両親の振る舞いをモカさんはこんなふうにばっさりと切り捨てた。
「心配なフリだけして、迎えに行くフリだけして、終わり」
両親は病院の職員に対して世間体を気にして「心配なフリ、迎えに行くフリ」をしているのだと彼女は淡々と話した。そうした大人に対する諦めや、ある種達観したような観察力は、彼女が親から虐待を受けていたことと無関係ではないように僕は感じる。
こんな話を聞いたことがある。
虐待を受けながら育つ子どもは、自分の身を守ろうとする防衛本能によって「どうすれば愛されるのか? 愛してもらえるのか?」ということに注意を向けるようになる。その結果、周囲の大人に対する観察力が異常に発達するという。
衝撃的だった、彼女の様子
さっき出会ったばかりの間柄にすぎない僕の質問に対して、複雑すぎる家庭環境や入院歴といったプライベートな事情をモカさんは語ってくれた。彼女は達観した観察力によって、僕のことを「危ない大人ではない」と判断してくれたのかもしれない。僕のほうも、モカさんの過剰に赤く塗られたアイシャドウに慣れてきた気がした。
続けて、モカさんは実の父親との間に起きた出来事を僕に打ち明けてくれた。
「実の父親から性的虐待を受けていたんです」
モカさんの実父は、母親に性的虐待を、モカさんに対しては殴る蹴るなどの暴力を振るっていたという。そんな生活が続いたあと、両親は離婚。父親に引き取られたモカさんは、これまでの殴る蹴るの暴行に加えて、性的虐待も受けるようになった。父親からの性的虐待という過去を、取材しながらある程度は想定していたので、モカさんの告白した内容を僕は静かに受け止めた。だが、僕にとって衝撃的だったのは、彼女がつらそうな様子をほぼ見せなかったことだ。
「普通ではないと思ってたけど、これがお父さんから私への本当の愛情なんだなと思った」
モカさんは、まるで父親と遊園地に行った記憶を思い出すかのように、軽やかな表情でそう語った。幼少期から殴る蹴るなどの虐待を受けて育った彼女にとって、唯一父親が“優しく”接してくれた時間だったのではないだろうか。
だからこそ、客観的に見れば性的虐待でしかない出来事が、彼女にとって“父親との楽しかった思い出”に変換されている。そんなふうに思考を巡らせると同時に、僕は心の底から違和感を覚えずにはいられなかった。父親からの性的虐待について話すモカさんの顔には、中学生らしいあどけない表情が浮かんでいたからだ。