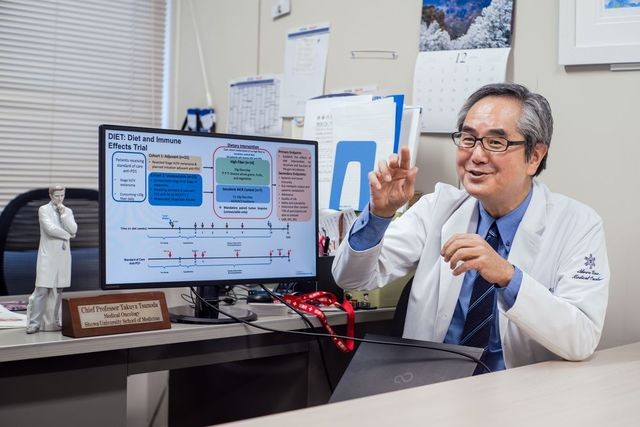https://www.asahi.com/relife/article/14211637
「多様な腸内細菌をもっている人ほど、がん免疫療法が効きやすいという話はお伝えしています。そして有用菌であるビフィズス菌をはじめとする多様な腸内細菌を増やすためにいろいろな野菜をたくさん食べて、食物繊維を多く摂取するようにアドバイスしています。」
腸内免疫は免疫の7割とか8割とか言われていますから、当たり前と言えば当たり前ですね。癌治療も、戦いの時そして戦いの後も免疫力が鍵になるようなので、ここはできるだけ腸内フローラを良い状態にした方が良さそうです。
「がんの薬物療法といえば長らく抗がん剤が主流でした。複数の抗がん剤を併用するなどして、延命はできましたが、副作用が強いという難点がありました。
2000年代に登場した分子標的薬は、がん細胞のみにある特定の分子だけを標的にするため、効果的に攻撃でき、正常な細胞へのダメージを低く抑えることができる薬です。
ただ、がんを抑える抗腫瘍(しゅよう)効果はすぐれていますが、長期的にみると抗がん剤と同様に生命曲線は右肩下がりとなり、生存率はゼロへと近づいていってしまいます。」
抗がん剤は副作用により生活の質を低下させますので、患者の年齢によっては抗がん剤治療をするかしないか、本人の人生観次第だと思います。
また長期的にみるとと言われても、目先のハードルをクリアしないと長期もないわけですので、やはりある程度の副作用は許容しなければならないかも知れません。
「一方、免疫チェックポイント阻害剤では、効果が出て3年生きられると5年後も10年後も生存していられる。つまり3年経過したあと、生命曲線は下がらず、ゼロになりません。
この生存曲線がカンガルーのしっぽに似ていることからカンガルーテール現象と呼ばれています。こうした現象を示すがんの薬はがん免疫療法(免疫チェックポイント阻害剤など)だけです。」
治療技術の進歩なんでしょうね。
「ただ、免疫チェックポイント阻害剤の種類や併用療法が増えたとしても、それだけで、すべてのがん患者さんを治すことはできないと思います。やはり患者さん本人の体質、つまり腸内細菌を変える必要があります。
腸内細菌をがん免疫療法に生かせれば、がんを薬で治せる時代がやってくる。がんは糖尿病や高血圧と同じように、慢性疾患になりつつあると思っています。」
腸内フローラ、頑張って育てます!