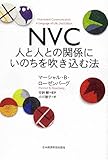人とぶつかることが多かったり、
しあわせになりたいと思ったり、
スピリチュアルな世界へ入ると
『赦し』
のテーマとどうしても
向かい合うことになります。
最終的にはこれしかない、
といってもいいくらいのテーマ。
ただ、感情を感じて
赦そうと考えればそうなるわけでもない、
ということもほとんどの方が
体験されているのではないかと思います。
再読していてこのことに関して
あぁ、ほんとうにそうだなと
思いださせてくれた、
マーシャル・ローゼンバーグの
NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法
からシェアしますね。
(P226)
失敗した自分を厳しく非難することで「教訓から学ぶ」道がないわけではないが、そういうかたちで学び、変わってゆくために費やされるエネルギーとは、どういうたぐいのものだろうか。それを思うとわたしは心配になる。恥の意識や罪悪感といった破壊的なエネルギーによって変わるのではなく、自分の人生を、そして自分以外の人の人生を豊かにしたいという明確な意識に促されて変わることが望ましいとわたしは考える。
(中略)
わたしたちの言語には、恥の意識と罪悪感をすさまじくかき立てる暴力的な言葉がある。わたしたちはこうした言葉で自分を評価し、そうした言葉はわたしたちの意識の奥深くに刻み込まれている。そうした言葉抜きで生活することは想像するのも難しい、という人もたくさんいるだろう。それは、「~すべき」という言葉。「もっとよく考えるべきだった」あるいは「あんなことをすべきではなかった」などと使われる。これを自分に向けると学ばなくなってしまう。なぜなら、「~すべき」という言葉は、ほかに選択肢がないことを意味しているからだ。人は、どんなかたちであっても強要されることに抵抗しようとする。強要は、自分の自律性を脅かし、選択の自由というわたしたちが強く必要としていることを妨げるからだ。それが自分の内側の「~すべき」という横暴さであっても同じことだ。
(中略)
「わたしたちはほんとうに禁煙しなきゃダメだ」あるいは「エクササイズを増やさなくては。ほんとうにどうにかすべきだ」
彼らは「しなくてはならない」ことを言い続ける一方で、実行に移すことには抵抗する。それは、人は奴隷になるために生まれてきたわけではないからだ。わたしたちは、「~すべき」と「しなくてはならない」という命令に屈服するようにはできていない。外部からの命令でも、自分の内部からの命令でも同じこと。その命令に屈服して行動しても、そこにはよろこびも生き生きとしたエネルギーも感じられない。
赦すことが、赦すべきに変わるとき、
抵抗するようにできている。
「自分の人生を、そして自分以外の人の人生を豊かにしたいという明確な意識に促されて変わることが望ましいとわたしは考える。」
この動機も強制だと受け止めると「~すべき」に変わってしまいますね。
ちゃんと、わたしは考えるという風に訳されています。
そしてこの考え方にわたしは賛同します。
人を批判したり、どうにもならない現状をなげくことに時間をかけるのではなく、人生を豊かにするためにはどうすればいいか、にエネルギーを注ぐ。
この意識の変革には
時間がかかります。
わたしもしょっちゅう忘れます。
根気強さが必要です。
~すべきという考え方になっていたら、
自分は今選択肢をなくしていると気づくこと。
そこから、はじまるのですね。
(画像をクリック)