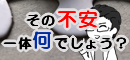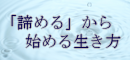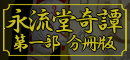創作コラボ企画「オトメ酔拳」スピンオフ
蜂蜜酒の精霊ベレヌス=メブミードの過去の物語です。
===========================
翌朝、侍従の呼び声で目を覚ましたヴィラは、自らの体が驚くほど軽いことに気づいた。長年悩まされ続けていた腰の痛みや、ときに頭痛まで引き起こす肩の凝りがすっかり消えている。まるで魔法にでもかかったかのような気分だった。
だが次の瞬間、消えたのは体の不調だけではないことに気づく——あの男の姿がない。蜜のような金色の髪と澄んだ泉のような青い瞳を持つ美しい男。楽器をつま弾くように優しく熱情を湧き立てる繊細な指や、背筋をゆっくりと撫で上げるような甘く艶やかな声を持つあの男はどこへ行ったのか。
「テロンを呼べ」
「テロンをですか?」
「そうだ、二度も言わせるな」
「申し訳ございません! 今すぐ!」
侍従はそういって慌てて部屋を飛び出していった。ヴィラはまだ眠りから覚め切らない頭で昨夜の記憶を順にたどる——好みの男娼を探すためにテロンを伴って城下の酒場へ向かい、そこであの男を見つけた。いや、初めに目を止めたのは全く違う男だった。褐色の肌と銀色の髪を持つたくましい男で、南の大陸から来たといっていた。その男に決めようとしていたところで、あの男が——。
「お呼びでしょうか、ヴィラ様」
侍従に連れてこられたテロンが恭しく一礼しながらも不服そうな表情で言った。
「昨夜のことは覚えているか?」
「昨夜ですか?」
ヴィラの問いの意味を推し量ろうとするように聞き返しながら、テロンは素早く部屋の中を視線だけで確認する。そこにいるのは、ベッドの上に身を起こしたヴィラ一人だ——一人?
「昨夜は、いつものように城下へお供しましたが、それが何か?」
「酒場で男に会ったな」
昨夜の男はどこへ行ったのだろう。途中で追い払われたためこの部屋に入るところまでは見ていないが、ヴィラがあの男をベッドに引き込まないとは考えられないし、男が外へ出ていったとも考えられない。誰もこの場所に近づけるなといわれたテロンは部屋から少し離れた場所で警護の任務に就いていたため、男が外へ逃げたとしたら姿を見ているはずだからだ。
だがテロンはあの男が逃げるところを目撃していない。さらに不思議なのはヴィラの着衣もベッドも全く乱れていないということだ。まるで男など最初から存在していないかのようだった。
「はい、おっしゃる通りです。昨夜は酒場で男に会い、その者をここに連れてきました。私はヴィラ様の申しつけで部屋から離れ、そのあとは一晩中警護の任に当たっていましたが特に異常はみられませんでした」
「物音などは聞いておらぬか」
「ええ……その……」
ヴィラに問われてテロンは答えに窮する。争うような声や物音などは聞かなかったが、同時に、いつもであれば聞こえるはずの物音も聞こえなかった。今思えばそれこそ“異常”というべきかもしれないが、はたしてそれを口にしてよいものか。
「なんだ、はっきりと申してみろ」
「……何も聞いていません」
悩んだ末、テロンは事実だけを答えた。テロンは何も聞いていない。ヴィラの淫猥な喘ぎ声すらも。
「ヴィラ、なにをしているんだね」
その声を耳にした瞬間、テロンは即座にひざまずき首を垂れる。その目の前をフランが足早に通り過ぎ、わずかにひるがえったローブの裾が彼の頭をかすめていった。
「まぁ、フラン。どうしたの、こんなところまで」
「お前を呼びに行かせたのにいつまでも来ないから気になっただけだ。……何か問題でもあったのか?」
フランはそういうと侍従とテロンをにらみつける——鋭い視線にさらされているのを感じ、二人は思わず身震いした。もしヴィラが二人に何らかの咎があるといえば、フランは何の躊躇もなく彼らの首をはねてしまうだろう。
「いや、大したことじゃないよ。そんなことよりもさ……ねぇフラン。イドリスとの交易はうまくいきそうかい? あの国には美容にいい油の採れる木があるらしいじゃないか。早くそいつを手に入れておくれよ」
テロンはそっと胸をなでおろす。どうやら、連れ込んだ男がこつぜんと姿を消したという話は避けたいらしい。外部の人間の立ち入りを極端に嫌うフランがこの話を知れば、男娼遊びを禁じられてしまうかもしれないと思ったからだろう。
「ああ、話は順調に進んでいるよ。うまくまとまればイドリスの毛織物や香油が手に入るようになる」
「フラン、あんたはいつだって私を満足させてくれる最高の男だよ。私が欲しいものを誰よりもよくわかっていて、なんでもくれるんだね。愛しているよ」
ヴィラはそういうとフランに抱き着き唇を重ねる。その言葉が本心であるかどうかは誰にもわからないが、この言葉一つでフランはヴィラの意のままになってしまうことは誰もが知っていた。
フランはヴィラの唇をむさぼりながらテロンと侍従を身振りで追い払う。二人は内心安堵しながら態度だけは恭しく部屋を後にした。
「ところでヴィラ、あれの様子はどうだ?」
「ああ、あれね」
二人が立ち去ったのを確認してからフランが言うと、ヴィラはフランの腕にしなだれかかりながら鼻だけで笑いながら答える。どうやらうまくごまかせたらしい。
「食事はちゃんと取っているし病気一つしてないよ。余計なことも言わないし泣きもしない、静かなもんさ。妙な知恵もつけてないから五年もすればフィンにちょうどいい人形になるだろうよ」
「そうか。子供さえ産ませれば用はないとはいえ、それなりの体である必要はあるから病気には気をつけねばな」
「そうだね、多少はそそる女に仕上げておかないと、あの子がかわいそうだ」
「おいおい、私は出産に耐える体という意味で言ったんだぞ」
「なんだ、それじゃまるで家畜じゃないか。ひどい男だねぇ」
「正妻などその程度のものだ。本当に大切なのは正妻じゃない方の女だよ」
「あら、嬉しい」
そういうとヴィラは再びフランに口づけをする。しばしの間、二人は互いの唇と舌をむさぼり合い、あたりには淫猥な音と喘ぐような呼吸音だけが響いた。体の奥が燃え上がり、激しい情欲にかられたフランはヴィラを押し倒すと、獣のように荒々しくヴィラの乳房や陰部を愛撫し始める。
「んっ……」
ヴィラはその愛撫に快感を覚えているような声を上げるも、内心ではうんざりするような心持であった。己の欲望を満たすことしか考えていないかのような——あるいは力強く征服することだけが正しいと信じているかのような乱暴な愛撫に快楽を感じることもあるが、多くの場合は快楽とは程遠く時に苦痛ですらある。ヴィラにとってフランとの交わりはもはや退屈な作業としか感じられず、男娼との交わりも時間が経てば同様のものであった。新鮮に感じられるのはわずかな間だけで、しばらくすればその感覚も薄れてつまらなくなってしまう。
だが、昨夜のあの男はこれまでの男たちとは全く違った。繊細で柔らかい指が体の奥深くに眠る快感をゆっくりとかき乱し、まるで蜜で煮詰められているように熱く溶けるような感覚だった。ただ触れられているだけでそれほどの快楽が得られたのだから、さらにその先となれば——。
「……いかんいかん」
フランは我を取り戻したかのようにそうつぶやくと、ゆっくりとヴィラから体を離して身なりを整える。何か重要なことを思い出したかのような体を装っているが、その表情には明らかな焦りと悔しさが滲みだしていた。
「今日は私もあれのところへ行こうと思ってね」
「おや、何か気になるのかい?」
「少し妙な夢を見てな……気にするようなことではないのだが」
いつもであれば、中途半端に情欲をかきたてておいて突然切り上げるフランに対して腹を立てることが多いヴィラだったが、この日はなぜか安堵すら感じていた。
「夢ねぇ……。まぁ、行ってみれば気も晴れるだろうさ」
ヴィラはそういってベッドから身を起こすと、乱れた髪を整えながら先に立って歩きだす——フランは彼女の不興を買わずに済んだことに胸をなでおろした。
彼女と肌を重ねることができなくなって何年の時がたつだろう。自分の身に何が起こってそうなったかも皆目見当がつかず、人脈を使って様々な地域の秘薬を試してみたものの改善の兆しは見られず不満は積もる一方だった。相手が変われば何かしら反応があるかもしれないと考え若い娼婦を買ったこともあるが成果は得られず、娼婦の死体だけが増えた。
フランは自身の手でヴィラの欲望を満たすことができないと悟り、その代替としてヴィラに男娼をあてがっている。それはヴィラを愛するがゆえの選択であったが、その苦痛と屈辱は耐えがたいものであり、時には嫉妬で気が狂いそうになる夜もあった。
そんな日は大量の蜂蜜酒を飲んで無理やり眠りにつくことにしているが、蜂蜜酒を飲んで寝た日は必ずと言ってよいほど夢を見るのだ。西方に残してきた正妻が突然現れる夢、朽ち果てた城にたった一人で取り残される夢、殺したはずの男娼やバイルン家の使用人たちに取り囲まれる夢——昨夜は先代バイルン公が健在だったころの夢を見た。
家督を継ぐ以前、一度だけ謁見した先代バイルン公は、武勲に秀でていることで知られていることから想像できる通りの厳めしい人物で、その目に見据えられただけで背筋が凍り、言葉を発するたびに大地が微かに震えているかのような気がした。
一方、その妻は春の陽のように穏やかな微笑みを絶やさない人物であった。彼女がどこで生まれ、どのような経緯でバイルン公の妻となったかは誰も知らなかったが、彼女が奏でる竪琴の音色の美しさや、歌として告げられる預言によってバイルン公が数多くの勝利を収め、国を発展させてきたことは誰もが知っていた。若かりし頃のフランは彼女の美しさに一目で魅了され、彼女のすべてを自分のものにしたいと願っていた。
夢の中でフランは彼女を捕らえ、犯し、すべてを手中に収めようとしていたが、その欲望は満たされることなく、彼はあえなくバイルン公の剣によって裁かれてしまった。それはまるで、国を簒奪して自らの子を後継者に仕立て上げようとする企てが失敗に終わることを預言しているかのようで——。
「これは……どういうこと?」
ヴィラが呆然と立ち尽くしながら呟く。思考の海から現実に引き戻されたフランは、ヴィラの肩越しに開け放たれた塔の中を見て小さな悲鳴をあげた。埃とクモの巣に覆われていたはずの部屋は塵一つなく清められ、乱雑に積み上げられていた家具や調度品はまるで誰かが住んでいるかのように整えられている。入り口から正面に見える位置には隠していたはずの先代バイルン公夫妻の肖像画が飾られ、まるで二人がそこに住んでいるかのようだった。
「ちょっと、どうしたの?」
「お前か? お前があの絵を飾ったのか? あの肖像だ!」
「違うよ! 私だったら驚くわけないだろう? 昨日はこんな状態じゃなかったんだよ。一体誰がこんなことを……」
「まさか、あれか? あれが脅しのためにこんなことを……」
「それこそあり得ない話だよ。あれはロクに口もきけないし歩くのだってやっとだ。大体、あの高さにあんな大きな絵をかけるなんて子供一人じゃできっこないよ」
「お前、誰かをここに連れてきたりしていないだろうな? 男娼どもはどうだ? 紛れ込んだりしていないだろうな?」
そんなことあるわけないだろう——と言おうとしてヴィラは口をつぐむ。昨夜の男は忽然と姿を消し、その行方はいまだわからないままだ。そもそも、自分がいるうちは他の男を引き入れないことを約束させておきながら、肌を重ねもしないまま姿を消してしまうなど不可解としか言いようがない。
「まさか……」
あの男は城内に入り込むために自分を利用したのか? だとすれば、これをやったのはあの男だろうか? いや、仮にそうだとしても何が目的でそんなことをしたのだ? 物を盗んでいくなら理解できるが、まるで誰かが住んでいるかのように部屋を整える理由がわからない。
ヴィラは青ざめた顔でわずかに震えているフランを残し、一人で塔の中に踏み込んで周囲を見回す。誰かが潜んでいるような気配はなく物音一つしない。綺麗に並べられたソファも使われたような痕跡もかった。
「ヴィラ! 正直に答えろ。何か心当たりがあるのか?」
「……朝起きたら、昨日連れてきた男がどこにも見当たらなかった」
ヴィラの部屋を訪れたとき、護衛の男が何やら深刻な表情を浮かべていたことを思い出す——そうか、あれはいなくなった男の所在を確認しようとしていたのか。
「なぜ黙って……いや、そんなことはどうでもいい。どんな男だ? すぐにでも探し出すぞ」
フランは責任を追及したい気持ちにかられたが、今はとにかく男を探すことが先決だ。その男が何者で何を目的としているかは不明だが、秘密を知られた可能性がある以上なんとしても消さねばならない。
「しっ! 静かに! 何か聞こえる」
言葉をさらに紡ごうとしたフランを制止すると、ヴィラは神経をとがらせた様子で周囲に視線を走らせる——聖堂から微かに竪琴の音が聞こえた。
「竪琴……?」
けげんな表情を浮かべるヴィラの言葉にフランはさっと顔色を変えると、大急ぎで聖堂に向かい扉を大きく開け放つ。
「誰だ! 誰がそこにいるんだ!」
天上から降り注ぐ祝福のように美しい音色が鳴り響く聖堂の奥にフランは向かって叫んだ。顔面は蒼白で目は大きく見開かれ、口元がわなわなと震えている。その異様な様子をみてただ事ではないと感じたヴィラは慌ててフランの元に駆け寄り、思わず息を飲んだ。誰も足を踏み入れないまま七年間放置されていたはずだというのに、床は毎日欠かすことなく磨き上げられていたかのように美しく、壁や祭壇には美しい花が飾られていた。
「これは一体……?」
「誰だ! 誰が竪琴を弾いている! 誰だ!」
フランは恐れると同時に体の奥底が熱くなるのを感じた。甘美で悩ましい音色はかつて焦がれた女性の面影を呼び起こし今朝見た夢の情景を思い描かせる。この音色を求めて何人もの楽師を雇ったが、記憶の奥に眠る音を奏でられる者は一人もいなかった。
「まさか……あなたなのですか、フェレイア様」
「偽りの王、日の没する地より来りて黄金の河に身を浸す。血塗られた手は仮初の栄光をつかみ欲におぼれた目はひと時の輝きを見る」
天井の調べのような竪琴の音に合わせて、地の底から湧き上がるような歌声が響く。その不気味な声は呪いのように背筋を這いあがり、不安と恐怖でフランとヴィラを凍り付かせた。
「だが彼らは知るであろう。すべてのものは正しき主へ還るということを。そして、血を尊ばぬ簒奪者には我らの裁きが下されることを」
「やめろ! やめてくれ!」
半狂乱になったフランが叫ぶと竪琴の音と歌声が途切れ、何者かの冷たい笑い声が響く——聖堂の奥、日の光が降り注ぐ祭壇の前に白い服の男が立っていた。流れる蜜のような金の髪と泉のように青い瞳の美しい男。
「そなたは昨日の……」
「ヒィィィ!」
ヴィラが何かを言おうとするのを遮るように、フランが声にならない悲鳴を上げる。不安、恐怖、熱情を次々と揺さぶられた挙句、殺したはずのドルイドが七年前と変わらない姿で目の前に現れたことで彼はもはや恐慌状態に陥っていた。呼吸すらままならず思考力は失われ、怯えて身を震わせることしかできない。
「フラン?」
「殺したはずなのに……殺したはずなのに……」
「殺した? あの占い師を?」
何が起こっているのか理解できないという表情でヴィラは聖堂の奥を見つめる。白い服の男。男娼が集まる酒場で会った占い師。純白の法衣に身を包んだ——法衣?
「そなた、何者だ?」
ミードは何も答えず静かに微笑む。艶やかなその笑顔はヴィラがこれまでに見た誰のものよりも美しくありながら魂が凍り付くほどに冷たい笑顔だった。
「何者だと聞いている!」
「ヴィラ、やめろ! やめてくれ!」
「フラン?」
「あれは七年前に殺した……」
七年前、初めて会った時にあのドルイドはなんといった? 確か、バイルン公の妻が輿入れした時にこの国に身を置いたと話していた。今から四十年近く前だ。だが、目の前にいる彼はどれだけ高く見積もっても四十歳以上には見えない。そうだ、あの日はロイド伯がそれを不審がっていた。
思えば不審なことだらけだった。外見はもちろん、痘瘡にかかったバイルン公に会うことを恐れる様子が全くなかったこと、狂気にかられて公女に襲い掛かろうとしたバイルン公が彼に触れられた途端気を失ったこと。そして、殺したはずなのに再び姿を現したこと。
「あれは人間ではない。人間ではなかったんだ」
「人間じゃない……?」
「人間なはずないだろう! 人間なら蘇ったりしない! 何年も姿が変わらず若いままであるはずがない!」
「そんな、まさか」
フランの言葉にヴィラの顔色が変わる——人間ではない? 蘇った? では何だというのだ? 私は一体、何を引き入れたというのだ?
「イヤァァァッ!」
ヴィラはけたたましい悲鳴を上げた。人間ではないと知った途端、昨夜の出来事は耐えがたいほどおぞましい記憶へと変貌し、触れられた髪や唇、胸元、体のすべてが汚されたように感じられる。彼女はその場に膝をつき、大声をあげて泣き始めた。
===================
Amazon Kindleにて電子書籍発行中☆
作品の紹介動画は「涼天ユウキ Studio EisenMond」または「作品紹介」をご覧ください。
雑文・エッセイ・自助
小説
■□■永流堂奇譚合冊版■□■
合冊版 永流堂奇譚 其の壱 (第一話~第三話+書き下ろし作品)

合冊版 永流堂奇譚 其の弐 (第四話~第六話+書き下ろし作品)
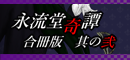
合冊版 永流堂奇譚 其の参 (第七話~第九話+書き下ろし作品)
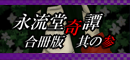
永流堂奇譚 第一部 分冊版
ENGLISH E-BOOKS
Start to live by resignation(Self-Help)

What the hell is that anxiety?(Self-Help)