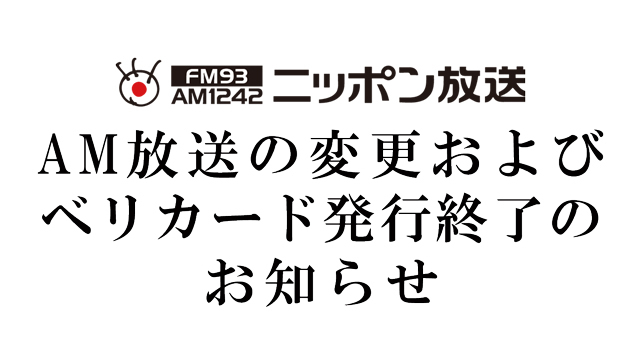ベリカード とは?
ベリカードとは語源が「Verification Card」と呼ばれ、【受信確認書】と意訳されたものです。
特に書式は決まってなく、各放送局が独自デザインで発行しているため、A4サイズのコピー用紙に印刷したものや、アマチュア無線愛好家が交換している「QSLカード」に倣ってハガキサイズに収めるなど創意工夫が見られました。
リスナーが受信報告書を送ると、放送局のご好意でベリカードが返ってくることがあります。
主に、
・受信日時
・周波数
・受信内容(〇〇時〇〇分▲▲秒に××という内容を受信・・・など)
・受信機器
・受信状態(SINPOコードという、5段階で自己評価したもの)
・返信先住所(受信報告書の記載主の住所氏名)
を受信報告書に書いて放送局が「確かに当局で放送したものです。ご報告ありがとうございました。」の意味で発行してました。
放送局にとっては、区域内の受信状況はもとより、区域外もどの辺りまで飛んでいるのかを知る指標になっていて、営業部においても放送局のPRとして広告代理店との折衝時に資料の一つにしてたようです。
今ですと域外はradiko全国配信で聞けますし、地方局にも全国からメールも届く時代なので、電波による指標は一定の役割を終えたと言えるのかもです。
ニッポン放送の場合のベリカードデザイン
現状
現在、IPサイマルラジオ「radiko」の普及の一方、広告費収入の減少、送信設備の維持費高騰、人件費増加などラジオ局も電波送信を維持するためのコストが割高となる中、放送電波受信による重要性が昔ほどでもない現状、ベリカードの発行というサービスも事務負担が大きい(=放送内容の確認が必要になる)ためかサービス終了が相次いでいます。
もっとも、テレビやラジオ番組の伝達手段を放送波で残してほしいという層は高齢者層ほど高いそうです。
AM局もFM転換を図ろうと地方部では廃局前提のAM休止実験を中継局レベルでやってますが、高齢者層の聴取が多い番組を抱えている局ですと、FM転換するとリスナーを大きく失うリスクが高く完全FM統一化に難色を示す局もあります。
HP上で告知する局もあれば、報告書を送って終了した旨が返信されるケースなど様々ですが、ラジオそのものというより放送電波技術を趣味とする人が減っているのだと思います。
もっとも、radikoプレミアムに入っても月385円のため高価な受信設備を購入するよりサブスクが低価格なので、必ずしも電波でなければ・・・という時代ではないのかもです。
しかし、IPサイマルラジオは電波ではないし、回線品質の担保はNTT等の通信事業体がやっているため放送局が管轄する設備ではありませんのでベリカードの対象外となっています。
経緯など
昔は各局内の技術社員がアマチュア無線愛好家を兼務してるケースがあって、その一環でベリカード返信が盛んになり1970年代に「BCLブーム」と呼ばれるほど電波受信を趣味とする人が雑誌を通じて増えたといわれてます。
アマチュア無線自体も連動するように芸能人でも趣味と公言する人もいました。
そしてベリカードのデザインも各局ごとに趣向を凝らすなどデザイン面でも更改があると、その区切りで受信報告が集まるなど時の変化で様々なデザインを楽しむのも趣味の一つだったと思います。
ただ紙の印刷費も近年高騰していて、放送局でも無償サービスに限界が来てるともいえるのは事実。
実際、紙の番組表も印刷取りやめして公式サイト上への掲載のみ(印刷会社に出してた原稿をPDF化して表示や印刷は各自で…の方式)に移行した局もあります。
今でもラジオを好む人はコロナを通じて一定数は推移してるそうですが、車の中でラジオを聞いてたとしても受信報告まで動く人はそうそう多くないと思います。
並行するようにアマチュア無線も若年層の減少が課題になっていて、アマチュア無線でもQSLカードが届いたとしても中年~高年齢者層からのものがほとんどです。
通信手段のほとんどがネット上で済んでしまうご時世、古くからある趣味が一つずつ消滅していくように思います。
ベリカードは切符などと同じようにコレクターにとっては楽しみの一つですが、これからはスリム化が進んで収集が難儀していく時代になると思います。