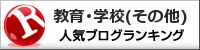よろしければ、クリックお願いいたしますm(__)m
「流れを作る」とは
こんにちは。
よく論文では、「流れを作る」ことが大事、と言われます。
このブログを見て頂いているということは、もしかすると、あなたも教授からそのような指摘を受けたことがあるかもしれませんね。
では、「流れを作る」というのは、どういうことでしょうか?
「流れ」とは、「論理の流れ」を指します。この流れを作ることは「論理構成」とも言います。
「論理」とは、「議論・思考・推理などを進めていく筋道」「物事の道理」などのことです(精選版 日本国語大辞典)。
「流れ」の例
では、もう少し、「流れ」について考えてみましょう。
論文ではなくてすみませんが、料理にも「流れ」があるので、それを例に考えてみましょう。
例えば、卵焼きの作り方を誰かに教えるとき、あなたはどのように説明しますか?
Aさん👩は、次のように説明しました。
「卵を器に割って、箸でかきませておく。
次にフライパンに油をひく。
コンロに火をつけて、フライパンを少し温める。
かきまぜておいた卵をフライパンに入れて焼き、形を整える。
次にBさん🧑は、次のように説明しました。
コンロに火をつけて、フライパンを少し温める。
卵を割り入れて、箸でかきまぜる。
フライパンに油を入れる。
あなたは、AさんとBさんのどちらの説明をもとに卵焼きを作りますか?
AさんとBさんの説明は、どちらも「卵を箸でかき交ぜる」「フライパンを温める」「フライパンに油をひく」というように、同じ作業を行います。
しかし、順番つまり「流れ」が違いますね。
Aさんの説明を参考に作ると、一応、卵焼きが出来上がると思います。
しかし、Bさんの説明を参考に作ると、卵焼きができなくもないですが、おいしい卵焼きにはなることは考えにくいです。
このように、「流れ」が的確でないと、最終的に良い結果(この場合は「おいしい卵焼き」)は得られません。
論文も似たようなところがあります。
例えば、「A社の成功要因」をテーマとした論文を作成する場合、どのような「流れ」にすべきでしょうか。
一例としては、A社がどれくらい成功しているか、これまでどのような経営を行ってきたのか、その中でも他社とどのような違いがあるのか、、、などを述べて、成功要因を導き出すことが考えられます。
これらの要素を章立て(目次)にしていくわけですが、いきなり、第1章で成功要因を書いてしまったら、「流れ」ができているとは言えませんね。
もちろん、論文は卵焼きの説明のようにはいきませんが、何を先に述べ、どれを後に述べていけば、相手(読み手)に納得してもらえるかを考えながら、構成を組み立てていくとよいでしょう。
大変ですが、論文作成がんばりましょう(^^)/
・・・。
もし、どうしても対応ができない場合は、当社でサポートを行っています。
お見積りは無料です。少人数で運営していますので個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
時間が経つほど対応が難しくなりますので、お気軽にお問い合わせください(^^)。
↓ ↓ ↓