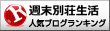世をこめて 鳥のそらねは はかるとも
世に逢坂の 関はゆるさじ (清少納言)
奥会津から帰った翌日、蕎麦碁会メンバーDさんのお宅で新年会が行われた。参加したのは、
主宰Aさん(東京都出身)、師範代Bさん(北海道出身)、Cさん(静岡市出身)、勧進元Dさん(水戸市出身)、Eさん(山口市出身)、Fさん(福岡市出身)、そして私の都合7名。
(全員集合前に飲みだす 本当によく飲みよく笑う人たち)
まずはDさんお手製の雑煮を食いながら乾杯。雑煮は関東風の角餅おすましスタイルである。
(正統水戸雑煮かどうかは不明)
両親が山梨県出身の我が家も長年この雑煮とほぼ同じものを食っていたが、結婚と同時に家内(京都出身)が丸餅白味噌雑煮を持ち込んだ。その後長いこと両者並立の時代が続いたのだが、いつの間にか丸餅白味噌に収れんしてしまった。
加齢とともに白味噌のトロリとした中に丸餅が溶け込んだゲル状の雑煮がより旨く、よりソフトに感じられるようになったのがその理由である。今年の三が日も都内で17人のお年寄りが餅を喉に詰まらせて救急搬送されたそうだが、この大半は角餅雑煮の仕業であろう。
それはともかく、日頃ワーワーうるさいメンバーの皆さんがケチもつけずにおとなしく雑煮を召し上がっている。どうも皆さん関東風雑煮にそれほど違和感がない様子。
帰宅後さっそく調べてみると、おそるべきことに(そうでもないか)今回の参加者全員が「おすまし文化」域内出身なのであった。
(広大なおすまし文化圏 「雑煮文化圏マップ」農林水産省HPより)
雑煮は餅の形状(丸餅・角餅)と汁(おすまし・白味噌)の組み合わせで4パターンに大別できるが、実際には「角餅白味噌」という組み合わせは存在していないので3パターンが全国に分布している。
左上:山口の雑煮(丸餅おすまし)
右上:福岡の雑煮(同上)
右下:鳥取の雑煮 これは雑煮でなく関東では「田舎じるこ」、関西では「ぜんざい」と呼ばれてます!
左下:高松の雑煮(あん餅白味噌) 何故こんなことを?動機が理解できないものは怖い
丸餅と角餅の境界はどこか。
マップ上の丸餅角餅境界線に着目していただきたい。この境界線上にはかつて三関と呼ばれた関所(愛発(あらち現敦賀市 平安初期に廃止され逢坂の関に代わる)、不破(現関ケ原町)、鈴鹿)が設けられていた。
三関はもともとアズマエビスの軍事的脅威から畿内を守る防衛拠点であったわけだが、いつしか異風の文化を遮る結界の役割をも負うようになった。不朽の名著「全国アホバカ分布考」(松本修著)で明らかにされたように、言語の分布もこの三関の東西で大きく異なっている。
(古来「関東」とは不破の関以東の地域を指し、それは都人にとっては人外魔境であった
人里としては平安中期以降逢坂の関が洛内(都会)と洛外(田舎)を分ける境界となった)
これらのことから、ゆるふわ博士は我が国の雑煮発展史について以下の説を唱えている。
・ 餅の歴史は稲作文化が我が国に定着した3世紀頃に遡る。餅は神事との関連が強いことからその
形状は鏡餅にみられるようにすべて丸餅であった。
・ 11世紀以降武家社会の勃興とともに戦時の大量生産に適した角餅(切り餅)が発生した。これは関
東(広義の)で主流となっていったが、武家文化と一線を画す三関以西には伝播しなかった。
・ おすましがデフォルトだった汁の世界に白味噌が登場したのは18世紀末。同時期に畿内では「アホ」
も普及し始めたが、どちらも三関を越えることができないまま明治維新を迎え、現在に至る。
・ なお、山陰で白味噌があずき雑煮(単なる「おしるこ」ですけどね)を凌駕できなかったのは寒冷地で
はよりカロリーの高いあずき汁が重宝されたからだというのが通説である。
・ また白味噌が中国地方に浸透しなかったのは岡山きび団子のせいとの説もあるが定かではない。
・ 高松のあん餅雑煮はいわば特異現象であり、雑煮学的に大きな意味を持たないので無視してよい。
余談だが、
「生ハムとメロン」とか、
「パイナップル入り酢豚」とか、
「バター+ジャムトースト」とか、
世の中には「しょっぱいものと甘いものを混ぜて食うのが好き」という奇妙な人々が一定数存在するのである。