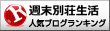甲斐国守護武田信昌によってもたらされた国の平和は信昌自身によって破られた。
明応元年(1492)信昌は長子信縄を廃嫡し次男の油川信恵に家督を譲ることを宣言、親子の対立は関東管領上杉氏、北条氏、今川氏の介入も招いて国内を二分する大抗争に発展したのである。
幼くして傅役に預けられる嫡男よりも身近で育つ次男の方がかわいくなるのは、織田信長、伊達政宗、徳川家光など枚挙に暇がないから、これも人情というものなのだろう。
信昌、信縄、そして信恵の死後もこの抗争は続き、守護職を継いだ武田信虎(信昌の孫、信玄公のオヤジ)が永正16年(1519)獅子吼城にこもって抵抗する今井氏(もともと武田支族)を降伏させて甲斐国を平定するまで戦火は30年に及んだのである。
なお、油川氏の名残は若林交差点やや北方の集落「油川」にその名を留めているが、「今井」という地名は北杜市内に見当たらない(今井姓自体は今でも小淵沢に多い)。
(増冨ラジウムライン松茸の店「想い出」から獅子吼城方面を望む)
享禄元年(1528)、国内統一を果たした信虎は諏訪侵攻を決意する。
北条、今川の領土を奪うのはたやすいことではなく、小海線沿いの信濃国佐久郡、小県郡は関東管領上杉家の威光が依然として及んでいて、領土拡張には諏訪進出以外に方途はなかったのである。
武田軍は富士見町Aコープ前に集結、諏訪侵入を試みるが緒戦に大敗、逆に諏訪勢に小淵沢、長坂町一帯を占領されてしまった。あわてた信虎は北の杜カントリー近くに笹尾砦を設けて諏訪勢の進出を食い止めようとしたが時すでに遅し、この大敗をきっかけにその後4年にわたり甲斐国内は騒乱が続いたのである。
その後薄氷を踏む勝利を何度か続けた信虎は、双葉ジャンクション近くの「河原辺の合戦」で国人衆・諏訪軍連合に大勝し、天文元年(1532)獅子吼城にこもる最後の抵抗勢力大井信元を降伏させて、ようやく甲斐国内から騒乱を一掃したのであった。
(信虎肖像画(甲府大泉寺所蔵) 信虎は絶頂期の天文10年(1542)、息子晴信(信玄公)のクーデターで駿河に追放された
この晴信のクーデターは「お家騒動あるある」、つまり自分を廃嫡して弟信繁を後継にしようとした信虎の機先を制するものだったという)
この1532年から信長侵攻の1582年まで50年にわたり甲斐国内から戦乱は消えた。武田家による
平和、すなわち「パックス風林火山」がもたらされたのである。
なお、天文9年(1540)信濃の村上義清勢が甲斐国内に侵攻、甲斐小泉駅近辺の小荒間で晴信が鎧袖一触これを蹴散らしたという逸話(小荒間合戦)が「甲陽軍鑑」にあるが、同書は甲州流軍学のマーケティング本という色彩が濃く、史家の間では同合戦は後世の創作とする説が強い。
風林火山の旌旗の下、八ヶ岳南麓は信濃経営の兵站基地としての役割を負うことになり、甲斐国人衆は長坂町大井ヶ森に集結するのが信濃侵攻の定法となったのである。
(大井ヶ森は松本方面、伊那方面、佐久方面、西上野方面のどこにでも展開可能な要衝にある)
武田家滅亡後戦略的価値を失った八ヶ岳南麓は今日に至るまで500年以上にわたって戦火を免れてきた。今では別荘族がウロウロするリゾート地として賑わっているという。
(躑躅が崎館跡(現武田神社) 「人は石垣 人は城」信玄公は生涯堅固な城郭を構築しなかった
甲斐国内で争乱は起こさない、という決意と自信の現れであろう)