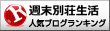「老後お世話になる公共施設」と言えば、図書館とプールである(そうでもないか)。
私が八ヶ岳南麓大泉で土地を探す際に最も重視した点のひとつが「図書館への通いやすさ」であった(大泉物件さがしの記事は → ここ )。
現実には「金田一春彦記念図書館」から4kmほど離れた所に居を構えたので、散歩のついでに、というわけにはいかないが、買い物ついでにクルマで寄ればいいから気にならない。
(金田一春彦記念図書館 八ヶ岳、甲斐駒を望む丘に建つ プールも併設されている)
一方杉並では徒歩圏内に阿佐ヶ谷図書館、下井草図書館がある。阿佐ヶ谷図書館はやや窮屈な印象があり、下井草図書館にお世話になることが多い。
(こうしてみても下井草図書館(右)の方がゆったりとした佇まいだ 巨大なハナミズキがシンボル)
八ヶ岳南麓に佇む金田一春彦図書館(以下「金春」という)と杉並の住宅街の下井草図書館を比較してみた(金田一春彦記念図書館の記事は→ ここ)。
蔵書・雑誌類の数
これはさすがに下井草図書館が圧倒している。正確な蔵書数は分からないが書架の数が段違いだ。
新聞、雑誌も倍はあるだろう。たとえば私が愛する週刊文春、週刊新潮だが、下井草には両方あるが
金春は週刊新潮のみである。
壁に「閲覧したい雑誌アンケート」というのが貼ってあったので週刊文春を希望したが、希望者は私をいれて4人(泣)、日暮れて途は遠い。
サービス
図書館の受付の方の応対は、どこも素晴らしい。
私を含め本を愛する人は心清き人、なのだろう。私を含めて。
金春が一歩上を行っているのは、帯のあらすじ部分を切り取ってわざわざ裏表紙に貼り付け、本の概要がわかるようにしていることだ。このひと手間、大変な作業であるが、私のような「衝動借り」タイプの本の借り手にとっては一縷の光明で実に助かる。
また、特製トートバッグがタダでもらえるのもなんともうれしい。
(これです 帆布製の立派なやつ)
それからもうひとつ、本の貸し出し期間が杉並は二週間だが、金春は三週間である。おそらく散歩がてら気軽に来れる人が殆どいない、という実態を反映しているのであろう。
混雑ぶり
下井草は大盛況である。
エアコンも効いて快適な無料休憩所なわけだから近隣の元気で暇なお年寄り(私もその一員)が群れ集っている。いきおい純粋に本を楽しむ方ばかりとはいえない部分もあり、マナーに関しては決していいとはいえない。
特に新聞雑誌コーナーの混雑は目を覆うばかり、かくして
「日経新聞を購読される方はカウンターまで」
「週刊文春、週刊新潮最新号はカウンターまで」
という、いわば需給調整が行われているというていたらくである。
これは「目に入ったのでつい借りました」という不心得者(愛読者たちにとって)を排除するという意味で
すぐれた効果があるのだろう。ロクに目も通さないくせに新聞雑誌をいつまでも占有している輩は本当に腹立たしいものだ。
一方金春は喧噪など全く無縁である。いつ行ってもせいぜい10人程度の本当に本を愛するお年寄りが静かに本を読んだり新聞を眺めている。
調べてみると図書館の利用母数が大きく違うのだから無理はない。
下井草 井草(16603)+下井草(18152)+(本天沼・白鷺の一部) = 約3万5000人
阿佐ヶ谷 阿佐ヶ谷北(24727)+本天沼(11471)+(天沼、下井草の一部) = 約3万7000人
金春 大泉(5217)+長坂(9239)+(高根町の一部)= 約1万5000人
という塩梅で、我々別荘族を加えても金春の利用母数は杉並の半分以下なのである(人口は2018年1月現在)。
買い物が不便、仕事がない、医者がいない、と不便な点も多々あるが、こと図書館事情という点では
田舎暮らしが圧倒的に恵まれている。
(定年退職からこっち借りる本にも次第に変化が・・・)