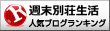(日本橋今昔)
コレド日本橋に行った。
東京駅からトボトボ歩いていると、小学校の音楽の教科書に載っていた歌を思い出した。
コレド日本橋七ツだち 初上り
行列揃えてアレワイサノサ
こちゃ高輪 夜明けて 提灯消す
六郷渡れば川崎の 万年屋
鶴と亀との米饅頭
こちゃ神奈川急いで 保土ヶ谷へ
こちゃえ、こちゃえ
この「七ツ」というのは何時だろう。
日本橋高輪間は約8km、日本人の平均歩行速度は5km/hだから(昔も大差ないはず)、日本橋から
1時間半歩いたところで夜が明けた、ということは「七ツ」というのは明け方の4時とか5時だ。
一方「丑三つ時」というのは午前3時頃である。この七ツと三つの刻みがさっぱり理解できない。
ググってみると、七ツとは概ね4時頃で「丑三つ時」の三つとは全く関連していないことがわかった。
「丑三つ時」の方は24時間を十二支で刻んだ時計である。
一方「七ツ」の方は12時間を2時間ずつで刻んでおり、
12時 1×9=九ツ
2時 2×9=18 ハツ
4時 3×9=27 七ツ
というふうに9の倍数をとって1の位の数字分だけ鐘をついたことに由来しているそうだ。なるほどね~。
(「ビバ!江戸」様のブログからお借りしました)
私はこの歌には1番、2番しかないと思っていて、長いこと「万年屋」のCMソングなのだろうと漠然と考えていたのだが、実は何十番もある戯れ歌で、音楽の教科書には子供たちに悪影響がない(とPTAのお母さん方が思う)部分2番のみが掲載されていたのである。
(万年屋 米饅頭より「奈良茶飯」が人気商品だったらしい 亀屋万年堂は全く関係がない)
恋の品川女郎衆に袖ひかれ
乗りかけお馬の 鈴ヶ森
こちゃ大森 細工の松茸を
登る箱根のお関所で ちょいと捲り
若衆のものとは受け取れぬ
こちゃ新造じゃないよと ちょいと三島
藤枝娘のしおらしや 投げ島田
大井川いと抱きしめて
こちゃいやでもおうでも 金谷せぬ
お前と私は草津縁 ぱちゃぱちゃと
夜ごとに搗いたる 姥が餅
こちゃ矢橋で 大津の都いり
この春歌も、「東海道中膝栗毛」と同じく文化文政期に庶民の間から生まれたものだろう。
往時は今以上に平和でサブカルチャー全盛の時代だったのかもしれない。そんな時代の香りが漂ってくるようだ。
呉服橋の辺りをウロウロしていて気がついた。私の目的地は「コレド日本橋」ではなく、「コレド室町」であった。こんなもん、いつできたのだろうか。
ちょっと来ないうちに街はどんどん変貌する。
東京オリンピックまであと2年、東京はどれほど発展していくのだろうか。
(「室町1」は2010年、「2」は2014年からあった模様・・・)