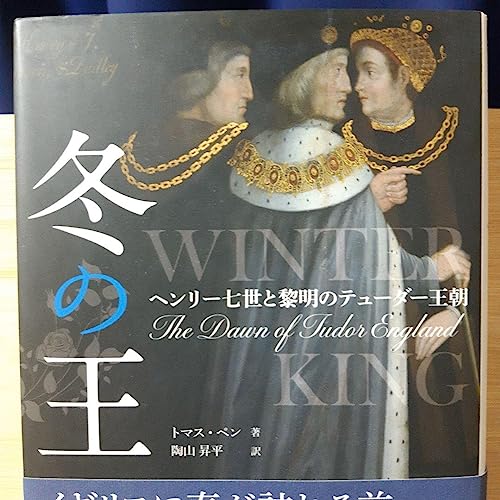こんにちは。
仙台駅構内にある、牛たん通り。
入店待ちの観光客が、通路に並んでいる。
(JR東日本総合サービスのホームページより)
たまたま~行列無しで、たまたま~お腹も
すいていたので、「思い切って」入ってみた。
おしゃれにデザインされた店、ではあるが、
「思い切って」入るような、高級店ではない。
ない、ない、ない。(重ね重ね失礼)
本当に「思い切って」牛たん店に入ったのは
昭和50年のこと。
雪が降る、寒い夜だった。
先輩の案内で、国分町近くの牛たんの店へ。
たしか「太助」だったと思う。
暖簾をくぐると、おじさんたちの視線が・・・。
(自意識過剰ではない)
うら若き?女性が連れ立って牛たんの店は、
ちょっと・・・の時代。
牛たんは、メジャーな食べ物とはいえず
私も、牛タンを食べるのは初めてだった。
牛たんを食べられるのは、呑み屋、酒場、
縄のれんの感じの店だったと思う。
(話を聞いた母は、眉をひそめていた。)
カウンターの中央に焼き台があって、
店内は、牛タンを焼く煙が、充満。
(換気扇などは機能してはいない)
桶に牛タンが積まれ、布巾が被せてあった。
牛タン、テールスープ、麦飯に白菜の漬物。
寺山修司主宰の天井桟敷、アングラと呼ばれた
演劇も、下火になりつつあったが、その夜は
早稲田小劇場の公演に行く予定だった。
調子に乗って、日本酒飲んで、ホカホカ温まり
全身、においプンプンで会場へ向かった。
もし、その後が、クラシック演奏会だったら
さすがに、無理だったでしょう。
案内してくれた先輩は、声楽家でした。
牛タンは、今やすっかり仙台名物。
帰省した折に友人親戚に発送、自宅用に買う。
仙台土産も時代で変わり、「萩の月」の出現
から、ずんだ系の勢力拡大、駄菓子の再評価。
(Eテレの「グレーテルのかまど」の
「仙台駄菓子」見ましたか?)
さて、4月の仙台駅で目にした行列は、
羽生結弦氏推しの友人から聞いていた
噂の「シーラカンス最中」。
復興アイスショー参戦記念のお土産で頂き、
私は試食済み。
人気はすごく、七夕の後も列を作っていました。
(4月、「シーラカンス最中」に並ぶ人々)
我が家は子どものころから、最中と言えば白松だった。
お土産に栗羊羹と最中は定番だった。
シーラカンス最中に並ぶ人々を見た翌日、
「寿三色最中」会社が自己破産申請という
いうニュースを見て衝撃を受けた。
「コトブキ、コトブキ、コトブキの三色も~な~か」
と、70過ぎた今でもすぐ歌えるCMソング。
しか~し・・、なんと、私は購入したことが無い。
妹に知らせると、即、電話口で
「コトブキ、コトブキ、コトブキの~」と歌う!
が・・なんと、妹も購入したことが無いという。
3色の餡が楽しめるという発想は素晴らしいし、
多分、仙台市民の多くに刷り込み成功している
稀有なCMソング!
それなのに、購入に繋がらなかったという
(我が家だけかもですが)厳しい現実!!
商売って、本当に難しい。
そして、変化するお土産人気の中でも、
「笹かまぼこ」は不動の地位を守っており、
それには、昔はなかった真空パック技術の
貢献が大きいし保冷剤等のおかげだと思う。
材料の魚の種類から、中に入る具も様々、
燻しやらバリエーションは無限に進化している。
それでも、店の人気ランキングのようなものは、
時々で変わっているようで、商売は大変です。
さて、堤通五番丁角に笹かまぼこ屋さん
があった。
大空襲で、一帯が焼け野原になる前からの店
なのか、そのあとから始めたのかわからない。
私が生まれた時には、あった。
正真正銘手作りの、笹かまぼこ!
痩せて背が高い、かまぼこ屋さんのご主人は、
奥さんと二人で、笹かまぼこを作っていた。
「笹かまぼこ」のみの製造、販売の小さなお店。
材料のすり身を作る機械が回る、
出来たすり身を、串に一本一本ぎゅっと付ける。
手作業だった。
(笹の葉型の枠で、一旦形を整えていたのかは
不明)
それを火の前に並べて立てて、ひっくり返して
両面を焼く。
(炭火?電熱機?だったのか不明)
焼きあがったら、串から抜いて、
大きな丸く平たい竹の籠の上に、ポンと投げる。
重ならないように、広げて冷ます。
ガラス戸越しに、のぞく子どもたち(私も)。
黙々と工程を進める仕事ぶりは、騒がず静かに
見ていなくてはと、子どもに思わせた。
笹かまぼこは、とても便利なおかずだった。
うちでは、お昼のおかずが足りない時や
味付けがほとんど無い、素朴な笹かまぼこは、
当然だけど、焼きたてが一番おいしい。