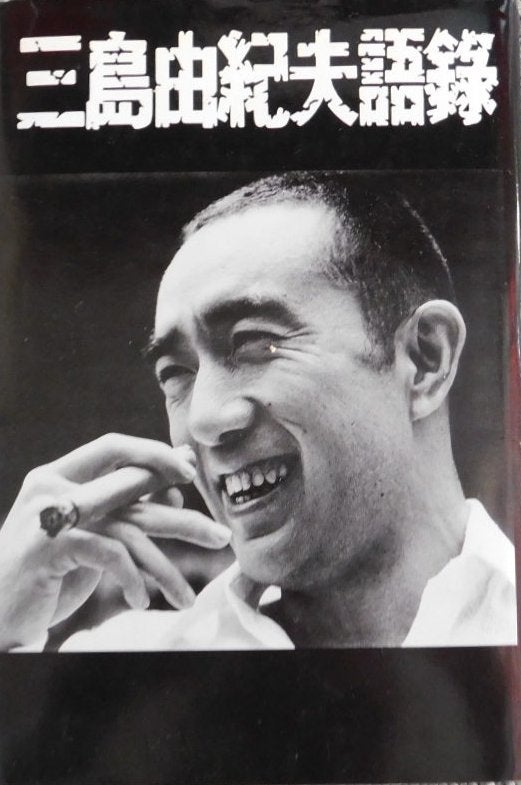『三島由紀夫語録』ー秋津 建
●「新知識人論」について
✪知識人の任務は、そのデラシネ性を払拭して日本にとってもっとも本質的もっとも根本的な「大義」が何かを問い詰めていればよいのである。安保賛成や反対は足下に踏み破り、有用性と無用性を乗り越えた地点で、ただ精神のもっとも純粋、正義のもっとも正しいものを開顕しようと日夜励んでいればよいのである。権力も反権力も見失っている、日本にとってもっとも大切なものを凝視していればよいのである。断乎として動かないものを内に秘めて、動揺する日本の、中軸の中軸に端座していればよいのである。私はこの端座の姿勢が、日本の近代知識人にもっとも欠けていたものであると思う。
✪村松剛氏は昭和46年11月1日、第11回公判の証人として出廷し、次のように述べている。「魂を失った軍隊に何ができるか、それを見せてやる---というのがいちばん大切なところだと思う。彼は、暗闇の中の一点を端座して見つめ続けること、死に至るまで魂の叫びを発し続けること、それが知識人の本当の任務だとしていた。これが今回の行動の大きな原因と考える。」(週刊読売昭和46年11月19日号)勿論右の抜粋文「新知識人論」が発表された時点での三島氏にすでに決起の決意が出来ていたことは、公判を通じて明らかにされたことであるが、村松氏のこのような見解は、三島氏に対する深い理解から出たものであろう。
村松氏には、三島氏の死後に『三島由紀夫--その生と死』(文藝春秋昭和46年5月1日)という著書がある。村松氏の三島氏との交友については前記11回公判の際、村松氏自身の口から、「同じ文筆業なので、かなり早くから知っていたが、とくに親しくなったのは、35年以降のこと。10年来の交友というわけだが、私の母と三島さんのお母さんが小学校で一緒だったこと、私の妹(筆者註、村松英子)が、三島さんの関係している劇団の女優だったことなどもあり、家族的にも付き合っており、普通の交友関係より親しかったと言える」と語っている。そして村松氏は、三島氏の決起の前10月7日頃、「彼が何か行動を起こすのではないかという危惧を持っていた。それで、やめてほしい、と頼みに行った」という。それが三島氏に会った最後であるというが、その時同席していたのが、伊沢甲子麿氏である。