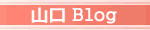”悪人の自覚”
「善人なをもて、往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいはく、悪人なを往生す、いかにいはんや善人をやと」
『歎異抄『より
『歎異抄』は、親鸞の弟子の唯円によって伝えられたものである。その中でもこれは有名な一節である。
善人すらなお往生(救い)をとげることが出来る、まして悪人が往生をとげないはずはないではないか。ところが世の人は、これとは逆に、悪人でさえ往生することが出来る、まして善人が往生しない道理はないと言っている。親鸞はそういう「世のひと」に一種の反語をもって向かっているのである。善人とは何か、悪人とは何か、同時に「救い」とは何か、そういう大切な問題がこの一節には含まれている
今日の我々の常識から言っても、善人ほど救われる存在だと思う。何ものかを信じて、悪人がもし救われるなら、善人はなおさら優先的に救われるはずだと思う。ところが親鸞はそれと反対に、悪人こそむしろ救われるべきではないかと言っているわけで、一見奇異に聞こえるが、ここに親鸞の「他力信仰」の核心がある。
まず、我々自身が、あいつは善人だ、あいつは悪人だと区別する場合がよくあるが、そのときの判断は一体正しいだろうか。善悪の区別を、我々は確実に決定できるだろうか。考えてみると、大へんあいまいである。たとえば何か法律上の罪を犯した人間は、世の中から見れば悪人である。しかし、そうでない人間はすべて善人であろうか。
ここで、大切なことは、他人よりも自分の心の中を振り返って見ることだ。自分は強盗などするはずがないと思っている。しかし、ひどく腹が減って、まったくお金がないという状態を想像してみよう。通りすがりの人を脅かして金を奪うことが起きるかもしれない。その可能性が全くないと断言出来るのだろうか。また、自分は女性を犯すことは絶対にないと思っている人でも、美しい女性に出会うと、心の中で犯していないだろうか。それは「心の中だ」と弁解しても、犯していることには変わりはない。
親鸞の指摘しているのは、外部にあらわれた罪だけでなく、心の中で犯した罪あるいは罪を犯す可能性である。それほど人間の心は不安定であり、危険な要素に満ちているということである。その他、人をおとしいれたり、嘘を言ったり、我々は毎日何かしら悪におちいっていないだろうか。それを反省し、救いがたい自己の悪人性を自覚し、ただひたすら仏の力に頼るような人こそ、仏の願いに近いと言っているのであろう。
また、自分は善人だと堅く思い込んでいる人がある。貧しい人にめぐみを施し、決して嘘を言わず、誰からも道徳的で立派な人だと思われ、自分でもひそかに誇っているが、しかし、その人は善人だろうか。
自分は善人だろうかと疑っている人はまだいい方だ。自分の行いを自慢する人がある。善人を看板にしている人もある。自分はこれだけいいことをしたから、必ず神や仏の報いがあり、救われるだろうと思っている。親鸞は、こうした態度を一切否定したのである。むろん善い行いを否定したのではない。そこに生じやすいうぬぼれ、またそこに潜む偽善に対して、鋭い批判をこころみた。人間の「はからひ(計算)」の虚しさを自覚した人の言葉として受け取るべきである。