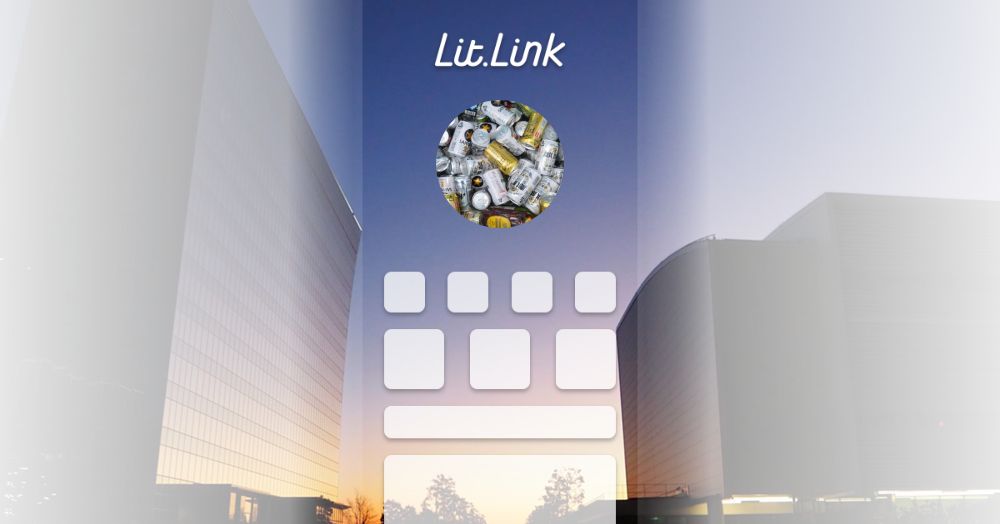
学び with 生成AI
須々木です。
年度が変わり、現在、サークル的にガッツリ学ぶターンに入っております。
RWは集団でいろいろやっているわけなので、何かを学ぶとき、いくつかパターンがあります。
大きく分ければ3つくらい。
① はじめからみんな結構わかっているパターン
この場合は、そこからさらに学びを深めたい状況なので、ディスカッションっぽい展開になりやすいです。
いろいろ意見をぶつけ合いながら、知識を深化させていく感じ。
みんな最低限の知識をもち、自分の言葉で語れる状況でスタートするので、わりとやりやすいです。
② 誰かがわかっていて、他の人はあまりわかっていないパターン
ある分野に関し、メンバー間で理解度に差があるパターンです。
たいていは、誰か一人が比較的よくわかっていて、それを他のメンバーに広げていく感じです。
サブカル界隈で言うところの「布教」っぽい展開になりやすいです。
理解度の差はあまり問題になりませんが、興味のレベルに差があるときは、うまくやる必要があったりします。
③ 誰もあまりわかっていないパターン
学ぶ必要があるという認識は共有しているけれど、みんな揃ってよくわかっていないパターンです。
当然、これが一番厄介です。
基本的には、教材を確保して、読み合わせみたいな感じですかね。
大学のゼミで論文を読み合わせするようなノリ。
そこまで固くはありませんが。
そして、今回の学びは、③のパターン。
みんな「わからんね!」というところからのスタートです。
本当に誰も教えようがないので、ひたすら調べるしかないわけですが、ここで記事タイトルにもあるとおり生成AI(ChatGPT)を活用しています。
もともと積極活用の方針ではなかったのですが、ちょっと試してみたら「結構活用できるな」となりました。
ChatGPTもかなり進化してきていますが、それでも全幅の信頼をおいて教えを乞うことはできません。
その前提で個人的に一番活用しやすいと感じているのが、到達目標(何を達成するために学びたいか)を明確にしたうえで、「どのあたりを学べばよいのか」というあたりをつける部分。
全然知らないものだと、どこら辺から手を付ければよいのかわかってくるまでに、そもそも一定程度のインプットが求められたりします。
学生など教師を頼れる状況だと、ここの部分をうまく導いてくれるわけですが、自学自習の場合はそうもいきません。
しかし、この「一定程度のインプット」は、タイパという意味ではなかなか微妙。
最小のコスト、時間で最大の効果を得たいのです。
その点、ChatGPTは、個別の情報の信頼性に多少難があっても、ざっくりどのあたりを学ぶと良いかはうまく教えてくれます。
言語化はさすがのレベルなので、学びの最初の方向付けにはもってこいです。
いろいろ関連する質問をぶつけていくと、よく吐き出すワードというのもありますし、徐々に学ぶべき対象のアウトラインが見えてきます。
普通に、要望に沿った良い感じのシラバスも出してくれますし。
アウトラインが見えれば、あとはさくさく調べて学べばよいだけ。
あと、まだそれほどやっているわけではありませんが、こちらが提示したものを批評してもらうという使い方には可能性を感じます。
創造的な思考は厳しくても、王道的な思考はなかなかハイレベルで、しかも言語化も得意。
添削にはもってこいです。
というわけで、生成AIに関しては、効率化をはかりうまく活用していこうとしています。
結局なんでも使い方ですよね。
sho