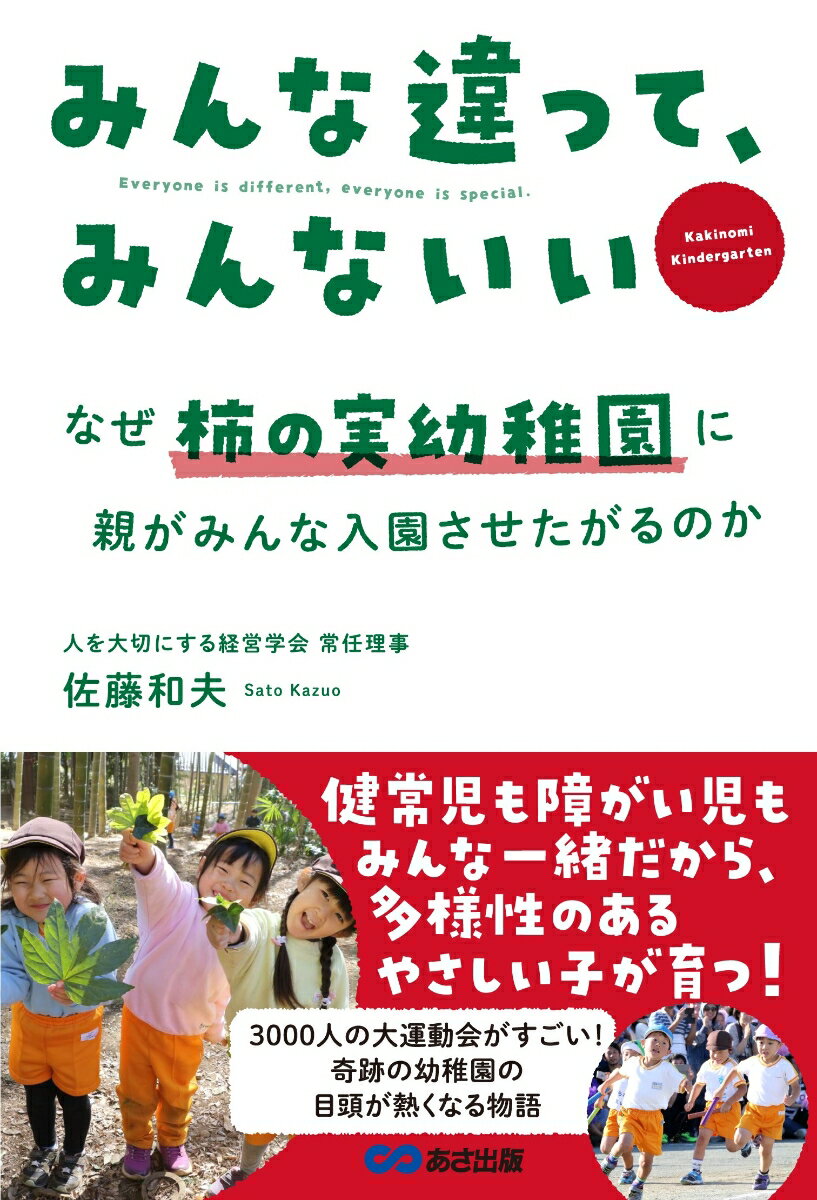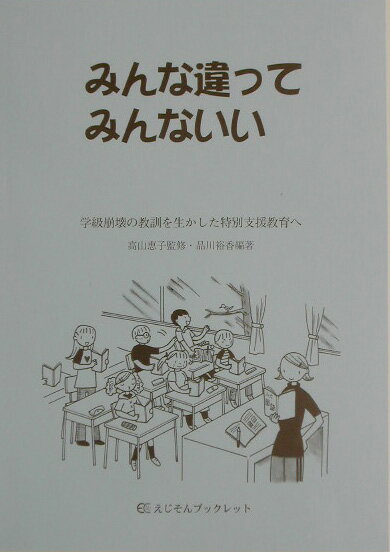Thank God, It's Blooomin'‼️🪴
まいど、ATSUSHIです😽
2月の中頃、米の買い占めが
ニュースになりましたね
まぁこれに関しては
ネット上で
犯人探しがやたらと広まって
一部では
海外の業者が違法に
買い占めてる
などという言説が広まっています。
この点は、先日書いた
ナショナリズムの高まりと無関係では
ないでしょう。
その数日後に、こんな記事も出ました。
そもそも足りてなかった説。
そして、農林水産省とJAの利権。
んー、この手の話は
推測の域を出ないというか、
第三者機関による本気の監査でも起きない限りは
陰謀論の域を出ないですよね…
残念ながら。
JAが個別の農家に対して
米不足の現在でも
減反政策を依頼してるという話については
納得はいきませんけどね。
その点に関しては、
JAがある種公的な機関として
方針というか、理由も含めて
説明義務があると思いますけどね。
さて、
昨今の若手就農者、特にSNSを中心とした
マーケティングを個人で行うことで
一定の成功を収めてる人がいて、
本人とは限りませんが
一定数、農協への批判とともに
これからの農業はBtoCつまり農家の自助努力
行き着く先は、市場原理に委ねる
というのが
あたかも真理であるかの如く語られることに
個人的には不安があります🫤
農業というのは
国家安全保障において
非常に重要なファクターです。
軍事防衛ばかりが語られがちですが
軍事
経済(食、資源、インフラ)
社会(自然、衛生、治安)
それぞれにおける安全性が一般に重要といわれます。
だからこそ、現在の日本国内における
米の不足は
めちゃくちゃ問題があるわけですが。
そこにきて、もし政府介入やJAなどの
調整機関が一切介在せず
市場原理にのみ委ねるとすると
海外勢にやられると思うんですよね。
ミクロとマクロの問題というか。
個別最適で考えると
高く売れればそれだけ利益が増えるので
買い手が日本人か否か、
怪しいかどうか、
そんなことは問題になりません。
あるいは、BtoCで勝てる人は
それで問題ないわけです。
しかし、中長期的な全体最適を考えると
はたしてそれで良いのか
となります。
めちゃくちゃザックリいうと
A国内に商売上手なB国の商人がやってきたとき、
個人単位の短期的利益を優先すると
B商人との商売が増えて
究極的にA商売が淘汰される。
すると、A国はB国に依存することになり、
場合によっては
A国は亡国の危機に瀕する。
そうならないために
A国は
B商人に関税をかけたり
A商人の優遇をはかるなどして
自国の保護をするわけですよね。
日本の今はAの状況を他人事とは思えない
そんな状況にあるのではないか?
それが現代のナショナリズムの一端ですね。
ということで、
一定の全体を調整する機関が必要な
理由としては
ひとつは、先にも挙げた国家安全保障、
自国内の食料を
確保できるかどうかの問題。
ふたつめは、
市場価格の制御問題。
今問題になってる20億トンの米の行方について
海外の方が買い占めてるとは
到底思いませんが
それでも
米が高くて買えないという地域や世帯はあって
メルカリなどのオンライン上に
海外からきた方がお米を出品している。
限定的ではあるけど
価格のコントロール権を
奪われてると言えなくはない。
市井は買うべきか買わざるべきか
死活問題ですからね。
みっつめが、BtoC農業の持つ潜在的な
差別性。
BtoCで成功する多くのケースでは
ブランド化=差別化
が前提だったりしますね。
ブランド化というのは
常に優位性つまり優劣をつけるという差別性を
はらんでいるということなんですね。
これ自体がダメということではなくて、
もし優劣をつけておきながら
「みんな同じ方法で自分で頑張ればいい」
といったことを言うとしたら
それはすごく暴力的だと個人的には感じますね。
と。
まぁ農業やってない人が
何を言ってもと言うところはありますが
世の中に「自力」という発言ほど
信憑性のないものはないので。
あらゆるヒトモノコトが
有機的に連関して社会は回っている。
それを忘れないようにしたいなと言う
徒然ぼやきでした!!
◆おしまい
楽天ルーム
最後まで読んでいただき
ありがとうございました‼️‼️‼️
ではまた〜
instagram: @atsushi_with_plants
ねこstagram: @ranchan1029
ポチッといただけると励みになります‼️
☺️🪴👍