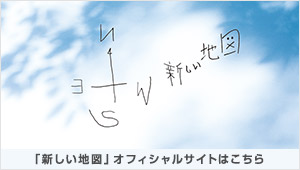惟光は光源氏の行方を探り当て、
果物などを差し入れます。
右近と会えば「やはりあなたの仕業ね」と責められるので、
直接顔は出しません。それにしても、
夕顔が源氏の君をここまで夢中にさせる女だったとは、
自分にもその気になれば手に入れる機会があったのに譲るなんて、
我ながら度量が広いよなあ、と呆れたことを思う惟光です。
二人を包む空は驚くほど静かな夕方です。
夕顔が「部屋の奥が暗くて気味が悪い」と怯えるので、
源氏の君は簾を上げて添い寝しています。
黄昏に浮かび上がる顔と顔。
ここにいる不思議を受け入れて少しずつ心を開く女が、
源氏にはとても愛しく映ります。
そばに寄り添っていても、何か不安そうな様子がいじらしくて、
格子を早々におろし灯をつけます。
「こんなに深い仲になってもまだ素性は明かしてくれないんだね」と、
源氏は恨みます。今頃は帝も私を探して大騒ぎだろう、と源氏は思います。
どうしてこんなことになったかは自分でもわからないし、
六条御息所は心を痛めて、きっと恨みに思っているだろう…
それは無理からぬことと、まずおいたわしく思い浮かぶのは
御息所のことです。でも、つい目の前のあどけない女と比べて、
もう少しこちらの息が詰まる重苦しさを
なくしていただけたらと心の中で思うのです。
夜。
まどろむ源氏の枕元に美しい女が座って
「お慕いしているのに、よくもこんな女と…
恨みに存じます!」と、
傍らの女に手をかけようとするではありませんか。
何者かに襲われるような気がして、
はっと目覚めると、灯も消え辺りは真っ暗闇。
ぞっとして源氏は太刀を引き抜いて置き、右近を起こします。
「宿直の男を起こし灯を持ってこいといっておくれ」
「暗くてとても行けません」「こどもではあるまいに」と源氏は笑い、
誰か呼ぼうと手を叩きますが、不気味な程音がこだまします。
夕顔はというと、ひどく体を震わせ怯え、
汗びっしょりで気も失いかけています。
「やたら怖がりの性分のですから、
どんなに怖いことでしょう」と右近。
そういえば心細そうに昼間も空ばかり見ていたな、
かわいそうに、と思い、源氏は「私が誰かを起こしてこよう」と、
右近を夕顔の側に残し戸を押し開けると、
渡殿の灯も消えていました。風が少し吹き、
しんとしてあたりは寝静まっています。
声をかけると番人の息子の声が聞こえました。
「紙燭を付けて参れ。随身に魔除けの弦を鳴らし声を絶やすなと命じよ。
こんなところでよく眠れるものだな。
惟光がいたようだが、どうした?」
「ご用もないので朝早くお迎えに参上すると、
下がりましてございます」。
男は滝口の武士だったので、弓弦を勇ましく鳴らしながら
「火危うし!」と言いながら、番人の居る方へ歩いて行きます。
「宮中では警護の宿直の点呼が始まった頃か」と、
源氏の君は胸の内でつぶやきます。
ならば、まださほど夜は更けてないでしょう。
一番好きな野菜を教えて!
▼本日限定!ブログスタンプ
お芋![]()