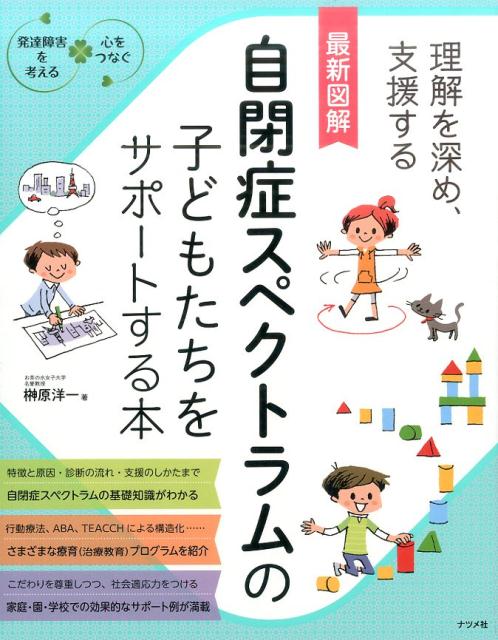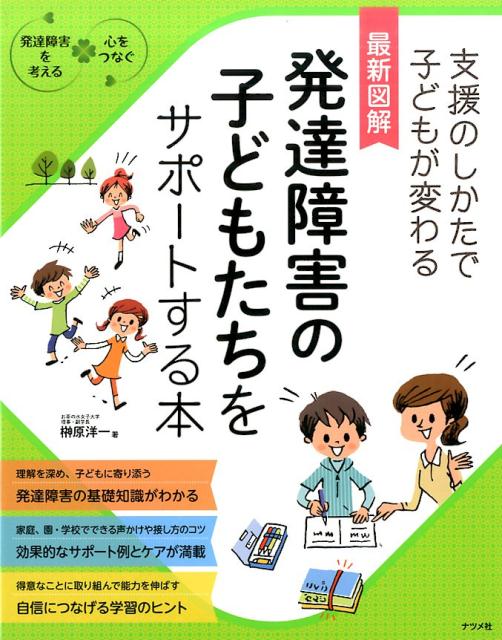カテゴリーA:アスペルガーやADHDについての本
『アスペルガー症候群と学習障害(ここまでわかった子供の心と脳)』
サイエンス本の中で読みやすく、なるほどな、の多かった1冊。
(☆やコメントは2020年頃に書いた超個人的感想&評価です)
榊原洋一 著
『アスペルガー症候群と学習障害(ここまでわかった子供の心と脳)』
講談社+α新書、2002初版
◎ おススメ度:☆☆☆☆☆
◎ 読みやすさ:☆☆☆☆
◎ 科学的情報:☆☆☆☆
◎ 知的好奇心:☆☆☆
◎ 実用的情報:☆
◎ 著者タイプ:小児科医
◎ 本のタイプ:アスペルガーと学習障害に特化したサイエンス本
◎ お勧めポイント:サイエンス本としては読みやすい
初版年は新しくはないのですが、内容がスッキリしていて読みやすい。そして、近年ではアスペルガーに特化した本が少ないので、切り口としても好きな本です。
いわゆる自閉症とアスペルガーの違いも分かりやすいですし、医学として発達障害の子供たちがどのように認知されて来たのかの変遷など、とても分かりやすいと思います。
といいつつ、目次を見て第3章から読みましたけど…![]() サイエンス本って大抵なぜか最初から読むと第1章で難破するんですよね…。サイエンス本が苦手な方は目次を見て部分読みをするのはとてもお勧めですよ。
サイエンス本って大抵なぜか最初から読むと第1章で難破するんですよね…。サイエンス本が苦手な方は目次を見て部分読みをするのはとてもお勧めですよ。
本書によると、英語の自閉症「autism」は、ギリシャ語で「自身」を意味する「autos」に状態を表す「ism」がついた言葉なんだそうです。
つまり「自身が強い人たち」なのであれば、やはり『自閉』という名称はある種、否定的で差別的だったのではないかなぁ、と日本語の診断名をつけた人を恨めしく思ってしまいますね。
色々な本を読んでみると、アスペルガー症候群を自閉症スペクトラムに含めた、今の形の医学分類になる以前は、体や言葉の発達には大きな問題なく育ち、集団生活や教育の場面で違和感が発見されることの多いアスペルガー、ADHD、学習障害がひとくくりで論じられる傾向もあったような感じですね。
この切り口もやはり、アリなんだと思います。
たぶんこの子たちは、私たちが子供の頃は『変わった子』として一まとめで、人間力のある教師・大人にきっと育ててもらってきたんだと思うので。
健康面や発達面でひっかかったことがないのに、園の生活にうまく馴染まない子、登園しぶり、登校困難、学校が怖い、そんな子供たちに『障害』とレッテルを張るのではなく、けれど違いや特徴の理解は広めてサポートしてあげたい、そんな著者の気持ちが感じられる本でした。
☆ ☆ ☆
オマケ:同じ著者の最近の書籍。
読んでいないのでレビューなしです↓↓
今日も読んでいただき、ありがとうございました![]()
「いいね」ありがとうございます![]()
![]() 私の本の選び方は5月最初の記事です
私の本の選び方は5月最初の記事です![]()