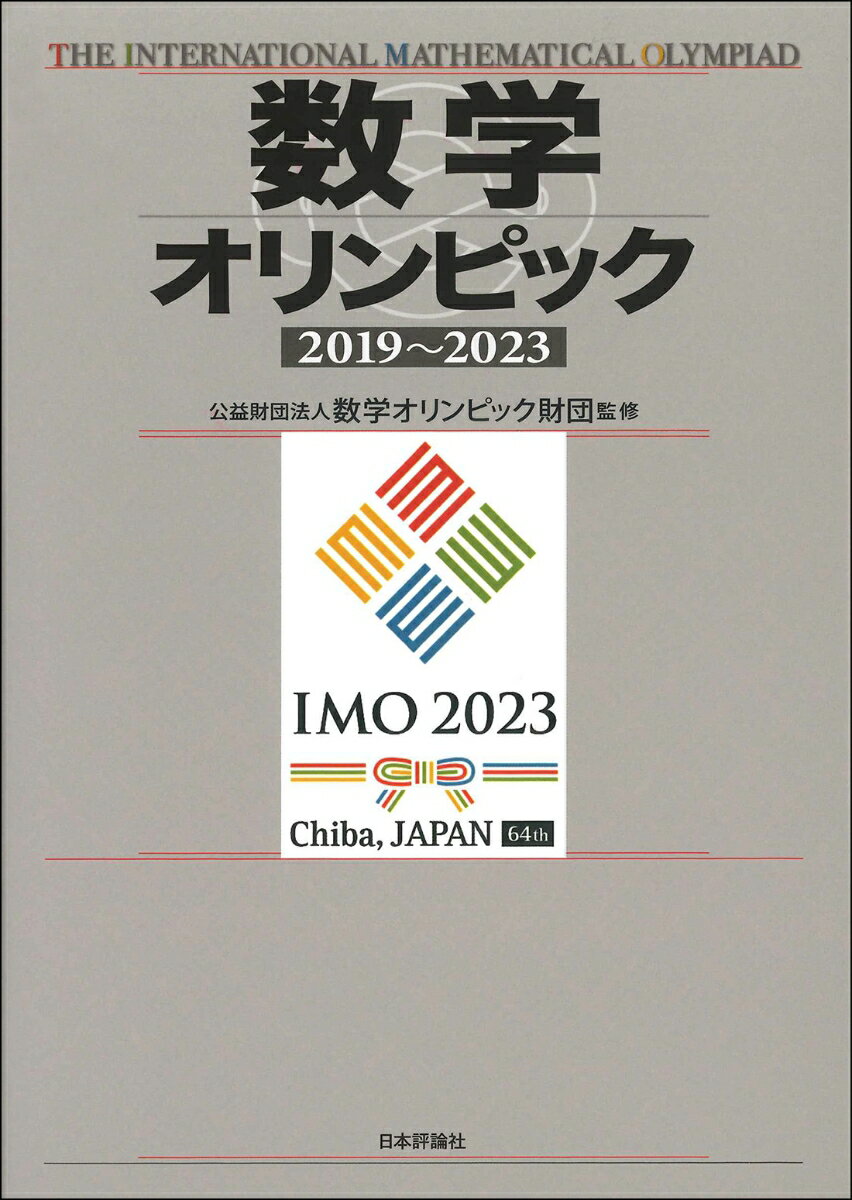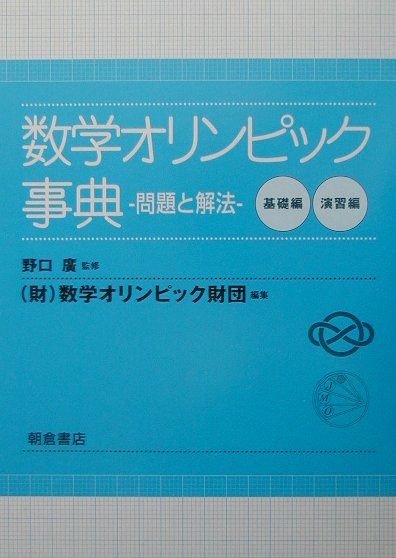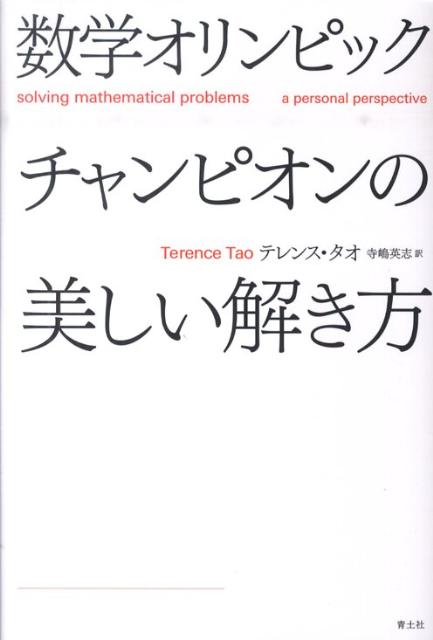今回は、日本数学オリンピック2012年予選第4問を取り上げ、解説します。
正の整数というのは、0より大きい整数のことです。
Aは3の倍数であるが9の倍数ではないから、Aを3で割った余りは3か6となり、Aの各桁の和は9で割ると3か6余ることになります(9の倍数判定法は、9で割った余りの判定法でもあることをしっかり押さえておきましょう)。
また、Aの各桁の積をAに足すと9の倍数になることから、Aの各桁の積を9で割った余りは、Aが9で割ると3余るときは6となり、Aが9で割ると6余るときは3となります。
Aの各桁の積が3の倍数となることから、Aの各桁には3の倍数が含まれることになりますが、各桁の積が9の倍数になってはいけないことから、Aの各桁には9の倍数(0、9)が含まれることはなく、また、3の倍数が複数個含まれることもありません。
結局、Aの各桁には3か6が1個だけ含まれることになります。
Aが1桁の数の場合、Aは3か6となりますが、各桁の積もそれぞれ3、6となり、条件を満たしませんね。
Aが2桁の数の場合、十の位と一の位は、3の倍数(3か6)と3の倍数でない数が1個ずつとなるので、3の倍数となることはなく、明らかに条件を満たしません。
Aが3桁の数の場合、最小のAを求めるので、百の位が1の場合から小さい順に調べていきます。
11□の場合、□に3か6を入れても3の倍数とならないので、条件を満たしません。
12□の場合、□に3を入れたときのみ、3の倍数であるが9の倍数ではないという条件を満たします。
123は9で割ると6余り、1×2×3=6も9で割ると6余るから条件を満たしません。
13□の場合、□に2か8を入れたときのみ、3の倍数であるが9の倍数ではないという条件を満たします。
132は、123同様条件を満たしませんね。
138は9で割ると3余り、1×3×8=24は9で割ると6余るからすべての条件を満たします。
したがって、最小のAは138となります。
なお、9の倍数判定法については、洛星中学校2002年後期算数2第1問(9の倍数判定法の証明問題)の解答・解説を参照するとよいでしょう。