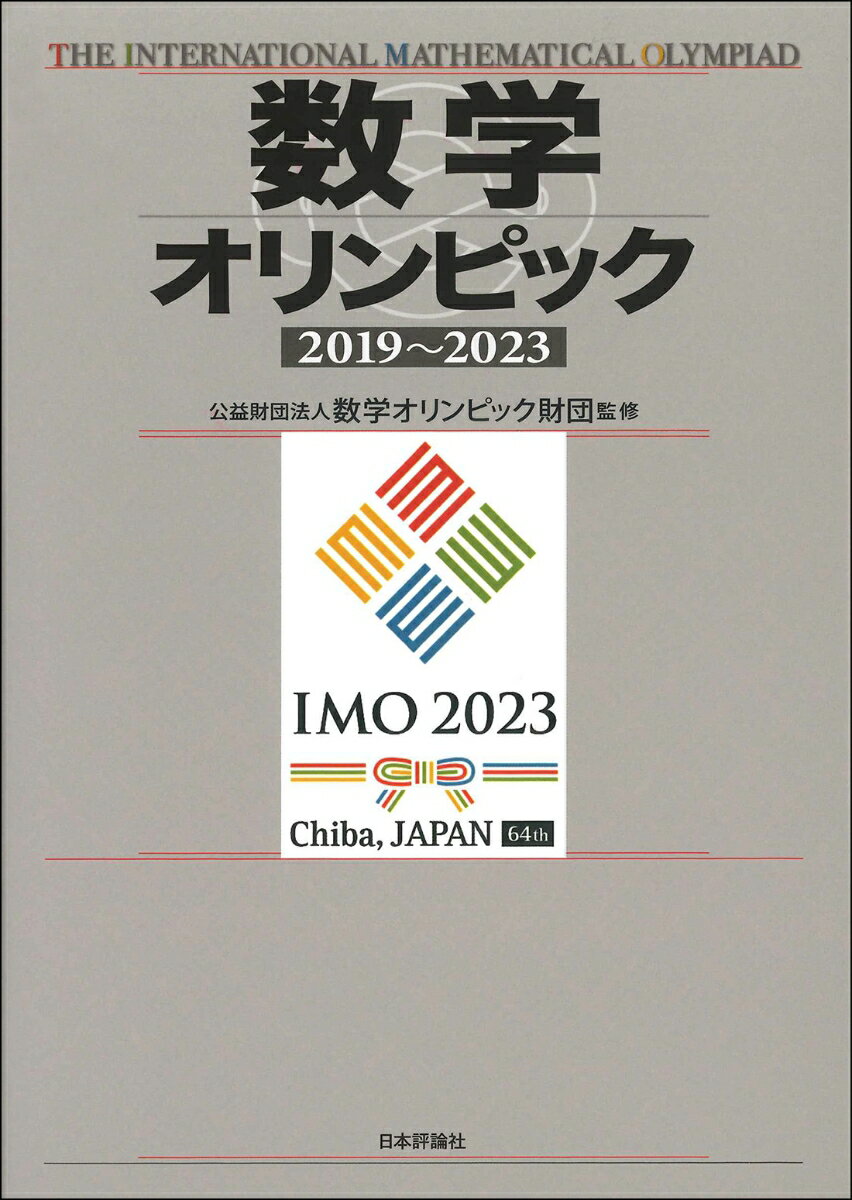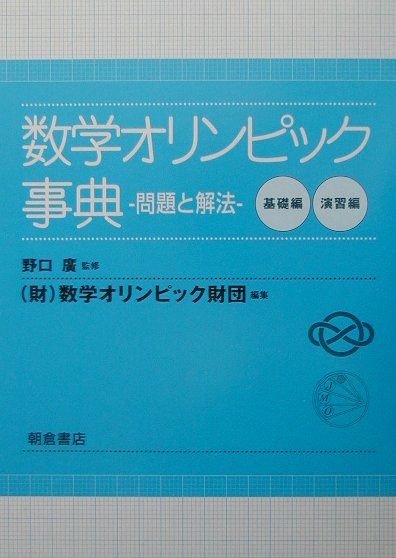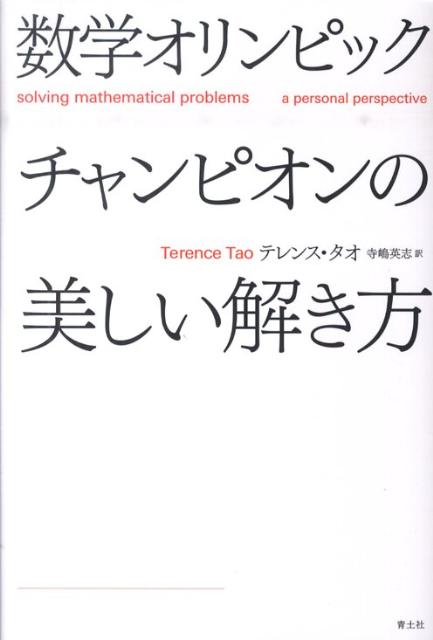今回は、日本数学オリンピック2009年予選第3問を取り上げ、解説します。
同じような問題が灘中学校で出されています(灘中学校2018年算数1日目第3問)。
さて、JMOの問題を解いてみましょう。
正の整数というのは0より大きい整数ということで、ab、bcはそれぞれa×b、b×cということです。
まず、与えられた2つの式の和を考え、分配法則(逆)を利用します。
a×b+a+c+b×c=36
a×(b+1)+c×(b+1)=36
(a+c)×(b+1)=36
a+cとb+1は36の約数のペア(ただし、2以上)となります。
次に、与えられた2つの式の差を考え、分配法則を利用します。
bc-c+a-ab=10
(b-1)×c-(b-1)×a=10(文字式計算の習熟度が低く、負の数を習っていない小学生にとっては、この変形が若干難しいかもしれませんが、例えば、200+17-17×11を計算する際、200に17を1個加えた後、17を11個取り除くのだから、結局、200から17を10個取り除けばいいと考えて、200-17×10=200-170=30と計算するのと同じことです。)
(b-1)×(c-a)=10
b-1とc-aは10の約数のペア(ただし、0以上(積が0でないから、実際は1以上)となります。
なお、与えられた2つの式において、上の式のaとcを入れ替えたものが下の式になり、23が13より大きく、b倍する影響力が1倍する影響力を下回ることはないので、cのほうがaより大きいことがすぐにわかりますね。
約数の少ない10のほうの約数のペアを書き出していきます。
(b-1,c-a)=(1,10)、(2,5)、(5,2)、(10,1)となり、bは2、3,6、11のいずれかとなり、b+1は3、4、7、12のいずれかとなります。
このうち36の約数となるのは、b+1が3、4、12のときとなり、(b+1,a+c)=(3,12)、(4,9)、(12,3)となります。
結局、(c-a,a+c)=(10,12)、(5,9)、(1,3)となり、あとは和差算を解くだけです。
(12-10)/2=1、10+1=11
(9-5)/2=2、5+2=7
(3-1)/2=1、1+1=2
したがって、(a,b,c)=(1,2,11)、(2,3,7)、(1,11,2)となります。